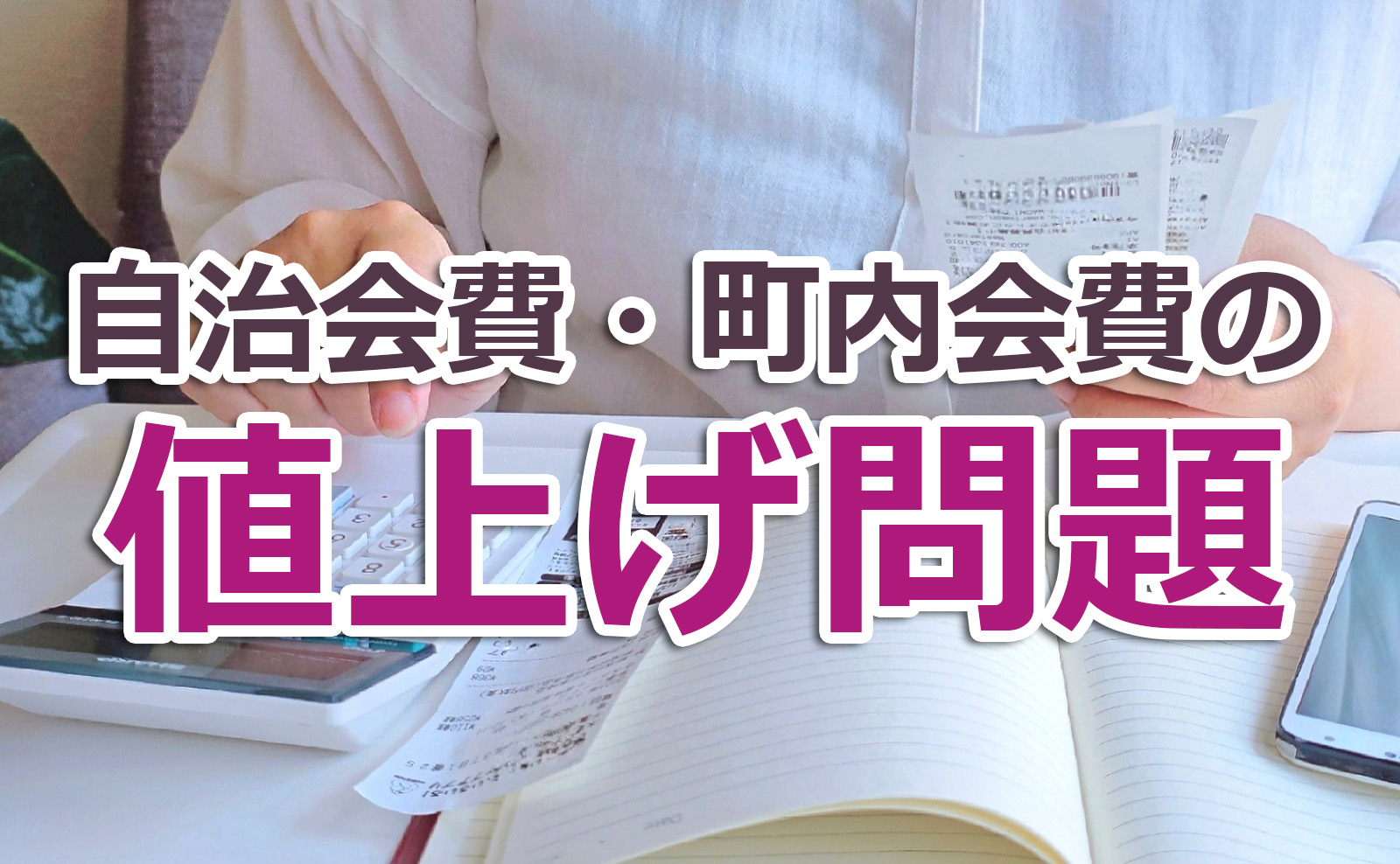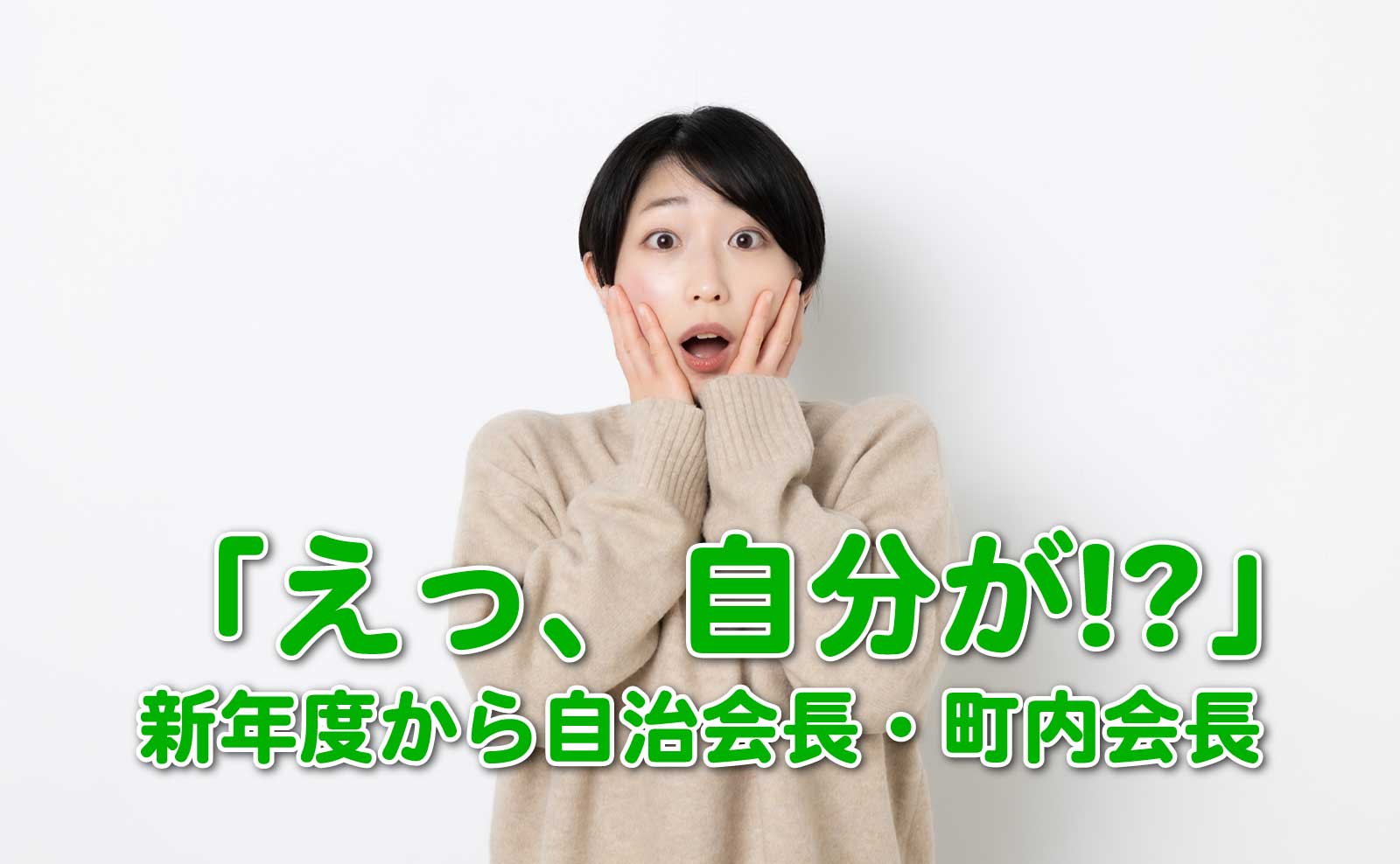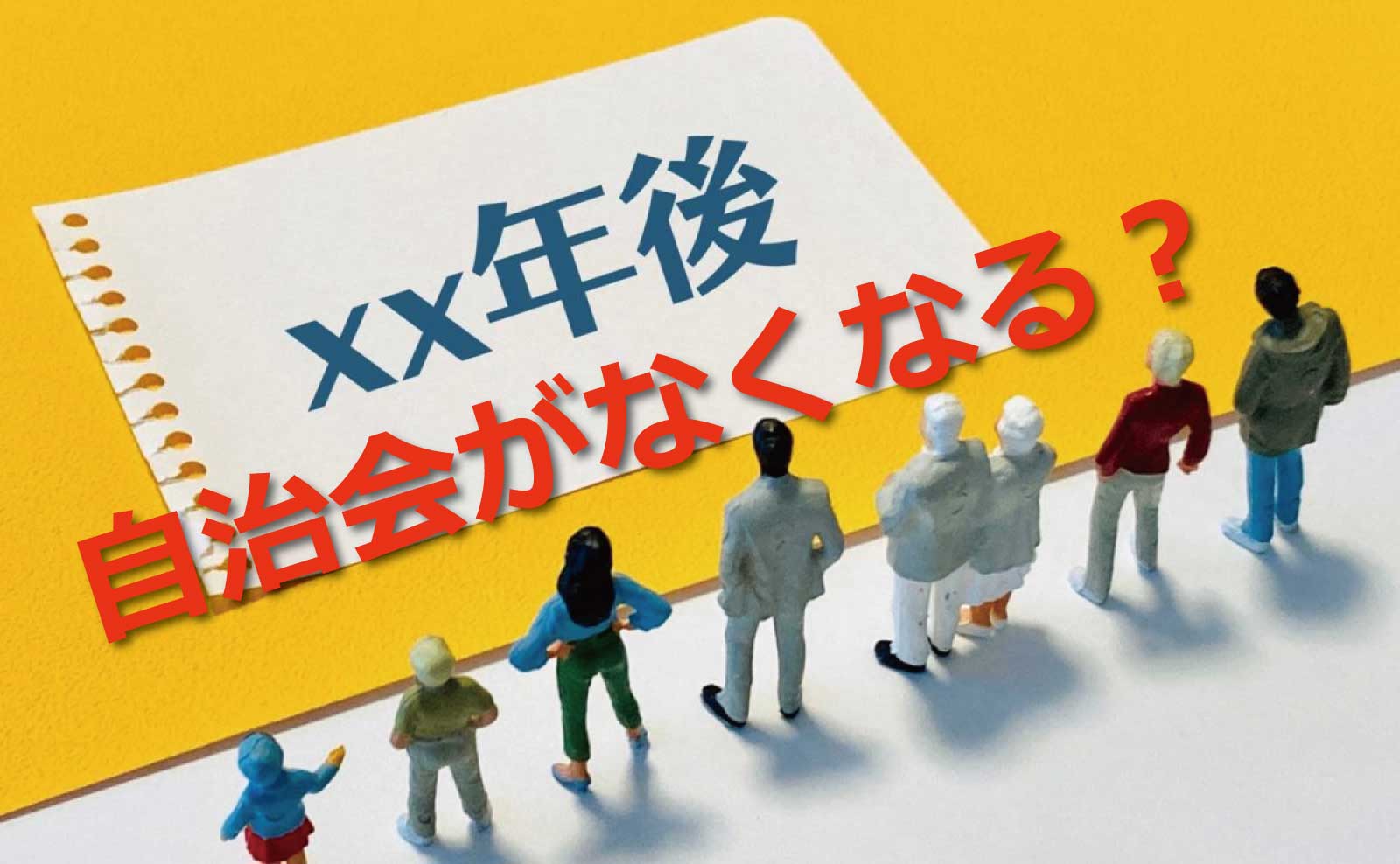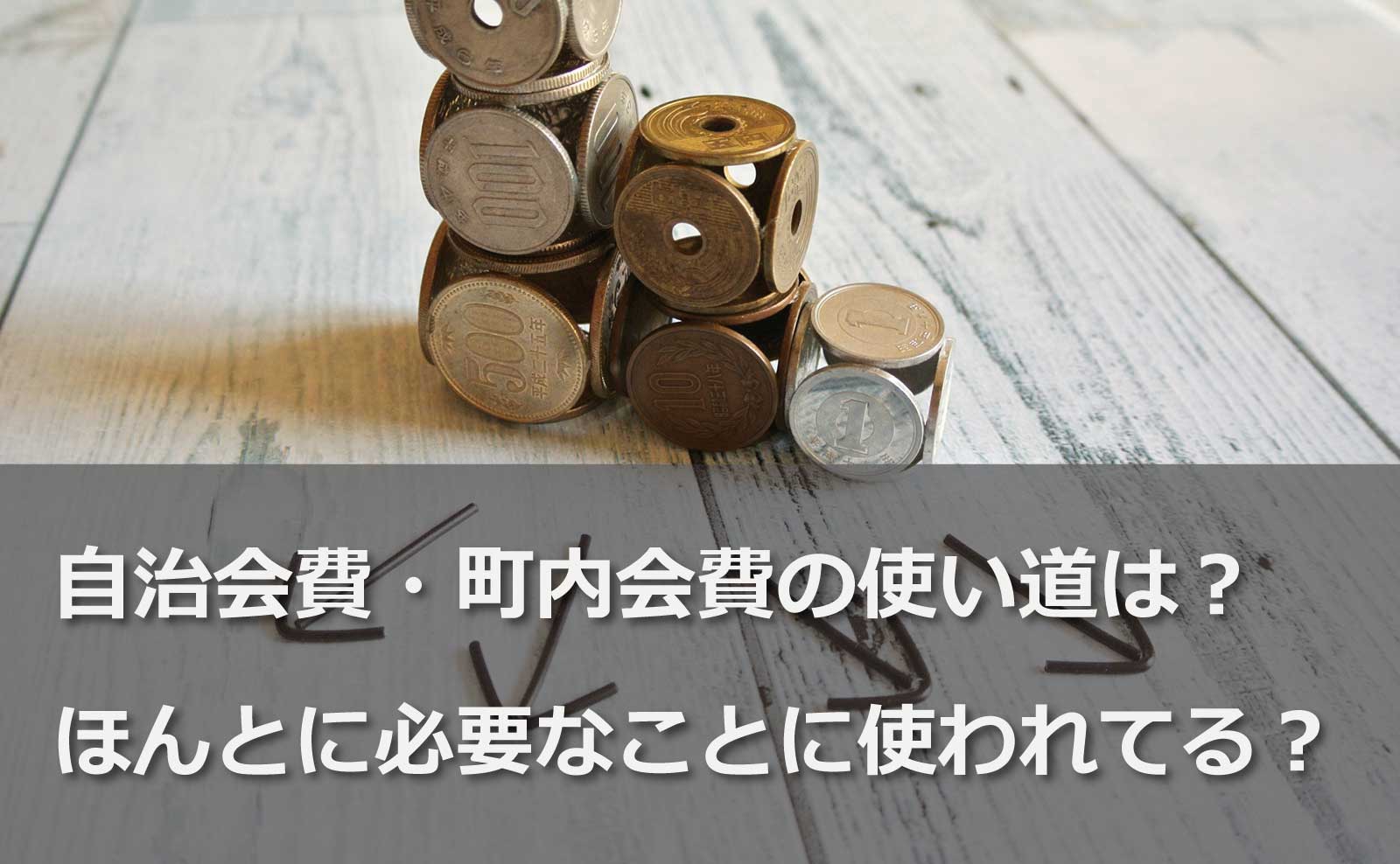新アリーナ建設をめぐる住民投票が意味するもの
豊橋市で長年にわたって議論されてきた「新アリーナ建設計画」が、ついに住民投票というかたちで市民の判断に委ねられることになりました。市政の転換点とも言えるこの住民投票は、単に一つの大型公共施設の是非を問うにとどまりません。そこには、これまで市民の声が政治にどう扱われてきたか、そして今後市民と行政の関係をどう築いていくのかという、より根源的な課題が横たわっています。
2年にわたって自治会長として地域に根ざして活動してきた私にとって、この住民投票は特別な重みを持っています。というのも、自治会や町内会の現場こそが、まさに「声が届かない」ことに最も敏感であり、最も現実的な問題として市政と向き合っている場所だからです。

自治会の現場で繰り返される「無視」の構図
私たち自治会長や町内会長は、日々、住民の声に耳を傾け、地域課題の調整役を担っています。回覧板の配布、防犯灯の設置、行事の準備、災害対応など、業務は多岐にわたりますが、最も重要な役割は「住民の代弁者」として、行政に声を届けることだと感じています。
しかしその声が、どれほど届いているでしょうか。
私の町内では、子どもたちの通学路が抜け道として利用され、車がスピードを出して通り抜ける危険な状況が長年続いています。幹線道路の渋滞を避ける車が、中央線も歩道もない住宅街の狭い道路に流入し、子どもたちの命が危険にさらされているのです。
この状況を改善しようと、校区推薦で選出されている市議に対して「ここをスクールゾーンにしてほしい」「せめて一度現場を見に来てほしい」と何度も要望してきました。しかし返ってくるのは、「反対する人もいますよ」「署名活動をしてからにしてください」といった、取り合う気のない言葉ばかり。現地視察さえ実施されず、安全確保よりも面倒事の回避が優先されているように思えてなりません。
これは私の町内だけの話ではありません。市内各地の自治会や町内会からも、「お願いしても何年も放置されたまま」「対応すると言ってそのまま音沙汰なし」という声を何度も耳にしてきました。
住民投票の実現は「変化」か、それとも「帳尻合わせ」か

こうした中で、新アリーナ建設をめぐる住民投票が実現するというニュースを聞いたとき、私は素直に喜ぶ気持ちと、冷めた視点の両方を抱きました。確かに、住民投票は市民の声を反映する重要な手段です。地域住民が主体的に意思を表明できるのは民主主義の根幹であり、歓迎すべきことです。
しかし、一方で「なぜ今なのか?」という疑問も拭えません。かつて市民団体が地道に住民投票を求め、署名を集め、議会に請願を出していた時期には、議会も行政もこれを正面から拒否してきたではありませんか。
浅井前市長時代、市は「丁寧な説明は尽くした」「手続きはすべて終えている」として、住民投票を必要としないとの立場を取り続けました。豊橋市が主催の説明会は形式的で、質問にも曖昧な回答が目立ち、住民の不安や疑問にはほとんど答えられていませんでした。
市民団体や住民団体では「本当にこのまま進めて大丈夫なのか」「経済的な見通しは甘くないか」といった声が多く上がっていましたが、行政はそれを単なる反対意見として処理し、事業を推し進めようとしました。
それが今になって、急に議会が住民投票に前向きな姿勢を示し、自民党市議団も「市民の声を聞くべきだ」と言い出したのです。この「変節」を、私たちはどう受け止めればいいのでしょうか。
都合よく使われる「市民の声」
私が最も懸念しているのは、「市民の声」が政治的なツールとして都合よく使われていることです。注目度の高い事業では、「市民の理解が必要」と言い、反対の声には「少数意見も尊重する」と言う。しかし、生活に根ざした地道な課題、例えば通学路の危険、街灯の不足、高齢者の見守りなどについては「合意形成が難しい」「予算の都合がある」などと言って後回しにされてしまう。
つまり、「市民の声を聞く」という姿勢自体が、実際には本気で聞く気があるのか疑わしいのです。声を聞いているふりをして、実際には何も変えない。そうした態度を私たちは、自治会活動を通じて何度も経験してきました。
それが、今回の住民投票では「市民の声を大切にしている」と、あたかも変化を遂げたように語られている。しかし、過去の経緯を知っている私たちから見れば、それは「帳尻合わせ」に過ぎないのではないかという疑念が残ります。
都合のいい場面では「市民の意思を尊重するべきだ」と前面に押し出しながら、不都合な要望や扱いづらい問題には「慎重に検討する必要がある」「反対意見もある」などと言って先送りにする。このような姿勢を目の当たりにしている市民の多くが、政治家の言う「市民参加」に対して疑念を抱くのも無理はありません。
豊橋新アリーナと同じ構図~浜松湖西豊橋道路にも通じる3つの問題点

アリーナ建設の経緯を振り返っていると、ふと頭をよぎるのが、現在計画が進められている「浜松湖西豊橋道路」の問題です。この広域道路構想もまた、自治会長として地域に関わるなかで「似た構図だ」と感じざるを得ない側面がいくつもあります。以下にその本質を整理してみたいと思います。
1. 十分な説明のないまま「合意形成済み」とされる構図
浜松湖西豊橋道路の計画について、どれだけの地域住民が内容を正確に把握しているでしょうか。自治体や関係機関から出される資料には「地域の理解を得た」「丁寧な説明を行っている」と書かれています。しかし、私たち現場の自治会に届いている情報は限定的で、説明会の案内すら一部地域では知らされていないケースもあります。
一方で、広域的な計画であることを理由に「合意形成済み」と見なされ、地域住民の声は事実上封じられています。アリーナ建設のときもそうでしたが、「説明会を開催した」「資料を配った」「ホームページに掲載している」というだけで、市民の納得や合意が得られたかのように処理される~この形式主義の姿勢が、浜松湖西豊橋道路にも色濃く見られます。
2. 質問しても回答されない、懸念に向き合わない行政の態度
新アリーナ計画と同様、浜松湖西豊橋道路についても「経済効果がある」「災害時に必要」といったメリットばかりが強調され、住民からの素朴な疑問には正面から答えようとしません。
たとえば、
- 「どのルートを通るのか?住宅地の近くを通るのでは?」
- 「自然破壊や農地の分断は起こらないのか?」
- 「地元の生活道路との交差点や影響は?」
こうした問いに対して、個別の懸念にはほとんど具体的な回答がありません。あたかももう決まった話であるかのように説明が進められ、地域住民の心配や代替案への検討は最小限に留められています。
3. 「地域の声」は聞く姿勢がある時だけ利用される
アリーナのときもそうでしたが、この道路計画でも「地域の声を尊重する」という言葉が使われています。しかし、実際には市民が慎重な検討を求める声を上げたとたん、「国家事業だから」「全体最適を重視しているから」という理由で、その声はかき消されてしまう。
市民の声は、都合よく使われるのです。賛同を得られる場面では大いに持ち出されますが、反対や疑問の声が出たときには「一部の意見」として扱われる。この態度の繰り返しは、地域住民に「どうせ何を言っても変わらない」という諦めを植え付けてしまいます。
真の「参加型市政」を実現するには
本当の意味で「市民参加型の市政」を実現するには、注目度の高い話題だけでなく、日々の暮らしの中にある声にこそ丁寧に耳を傾ける姿勢が不可欠です。自治会をはじめとした地域の最前線では、日常的に多くの声が上がっています。それはインフラや安全、福祉といった生活に直結するものばかりです。
にもかかわらず、自治体の施策は「上から与える」かたちになりがちで、現場の意見が反映される機会はきわめて限られています。私たちが求めているのは、大きな公共事業に対する賛否を問うこと以上に、「日々の声に誠実に応えてくれる政治」です。
市民の声は、政治の飾りでも免罪符でもありません。すべての政策の出発点であり、軸となるべきものです。
この住民投票は「信頼回復の第一歩」になりうるのか
今回の住民投票は、単なる建設の賛否を問うものではありません。それ以上に、「これまでの政治家の姿勢をどう考えるのか」「これからの市政に何を求めるのか」を問う機会でもあります。
私たち自治会や町内会は、長年地域に寄り添い、行政との橋渡し役を担ってきました。その中で感じてきた「無視される声」「都合よく使われる声」の現実を踏まえ、今こそ一人ひとりが「当事者」として意思を表明する時ではないでしょうか。
この住民投票が、誠実な市政への第一歩となるよう、そして地域の声が本当に政治に届く社会になるよう、私たちもまた声を上げていきたいと思います。