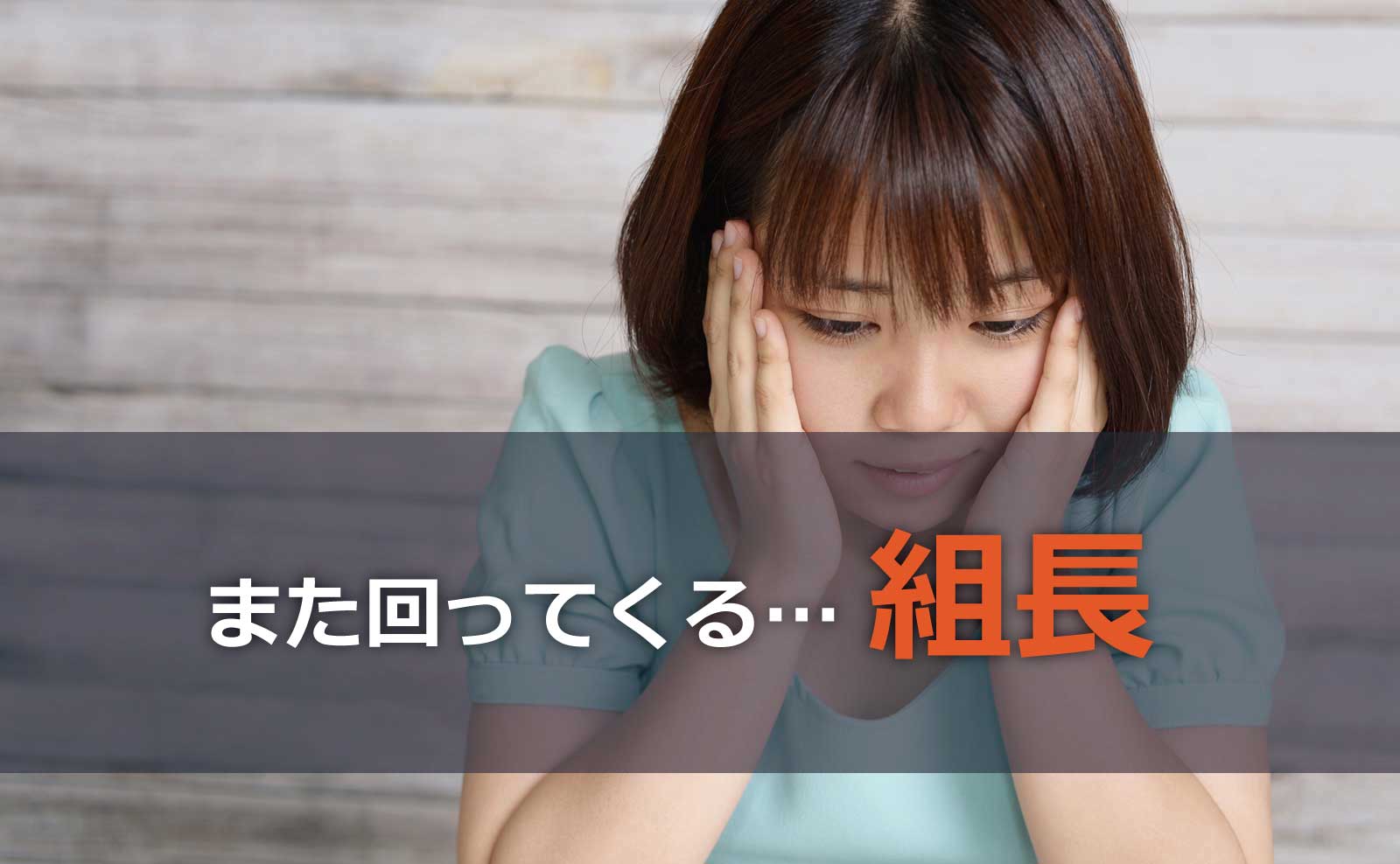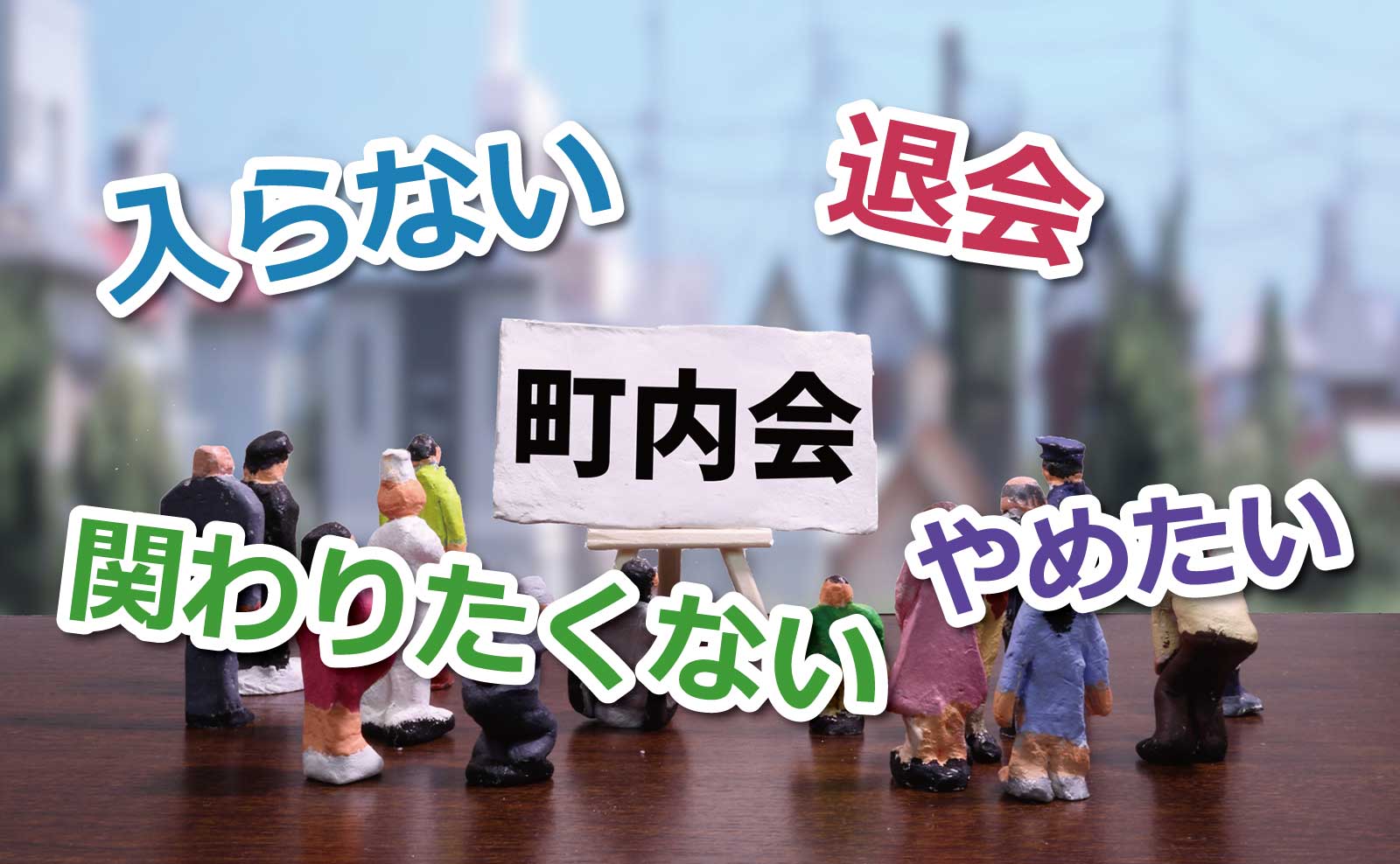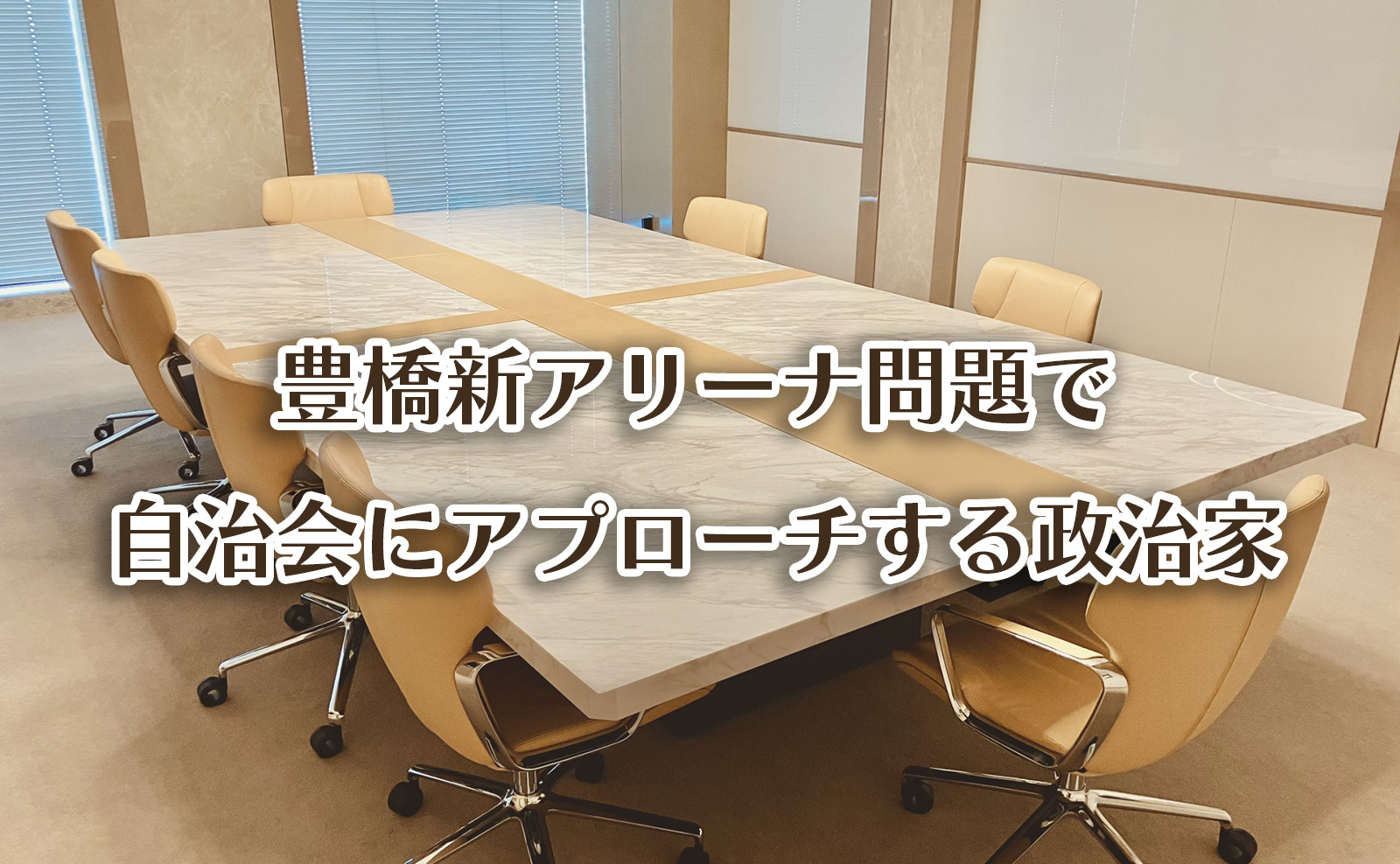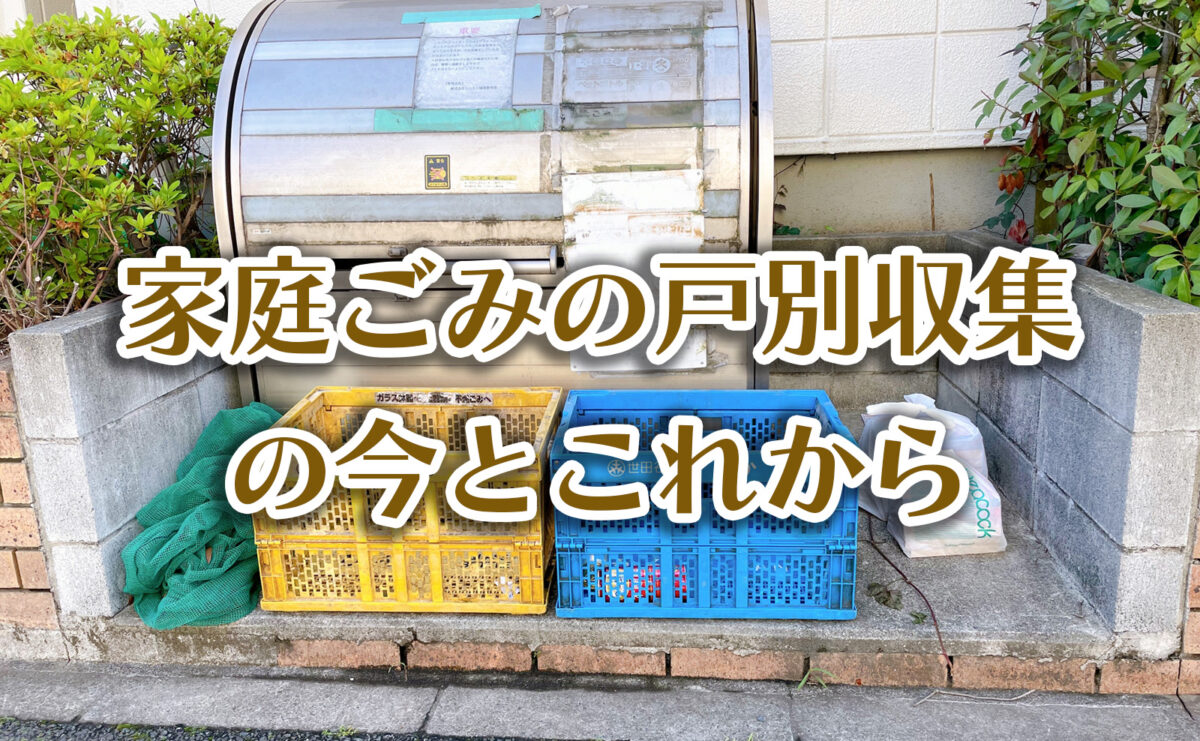
はじめに~変わるごみ収集、広がる戸別収集
私たちの暮らしに欠かせない「ごみの収集」は、長年にわたり地域のルールや慣習の中で維持されてきました。なかでも、日本の多くの地域で見られる「ごみステーション」による収集方式は、市民の協力を前提とした仕組みとして根づいてきました。しかし近年、このごみ出しのあり方に変化の兆しが見え始めています。その背景には、高齢化の進行や少子化、共働き世帯の増加といった人口構成の変化に加え、地域コミュニティのつながりの希薄化があります。
特に注目されているのが、「戸別収集」という新たなごみ収集方式です。これは、各家庭の前までごみ収集車が来てくれるという仕組みで、ごみステーションまで運ぶ手間を省くことができます。ごみ出しの負担が軽減されることから、高齢者や子育て世帯を中心に支持が広がっており、平塚市や鎌倉市をはじめとした自治体では、戸別収集の導入や試験運用が進められています。
しかし、戸別収集は単なる利便性の追求ではありません。ごみ出しの責任を明確にし、不法投棄の防止や分別の徹底といった副次的な効果も期待されています。その一方で、収集コストや人手の確保といった現実的な課題も浮き彫りになっています。
今回このように広がりつつある戸別収集の実態と背景、さらに導入にあたっての課題や今後の展望について、多角的な視点から考察していきます。これからの地域社会にとって、より持続可能なごみ収集のあり方とは何か…そのヒントを一緒に探っていきましょう。
世界のごみ収集方式と日本の特異性

世界のごみ収集方式の分類
世界各国では、都市の規模やインフラ、住民のライフスタイルに応じて多様なごみ収集方式が採用されています。世界銀行(World Bank)は、家庭系ごみの収集方式を大きく4つに分類しています。1つ目は「House-to-House(戸別訪問型)」で、契約業者や行政が各家庭を直接巡回し、ごみを収集する方式です。多くの場合、有料サービスであることが特徴です。2つ目は「Community Bins(共同容器型)」で、住民が地域に設置されたごみ箱に出し、収集車が定期的に回収します。3つ目は「Curbside Pick-Up(敷地前出し型)」で、住民がごみを自宅前に出し、それを行政が回収するものです。そして4つ目は「Self Delivered(自己搬入型)」で、住民自身が処理場や中継所までごみを運ぶ方法です。これらは地域性や社会構造により選択されており、各方式には一長一短があります。
日本の収集方式の独自性
日本におけるごみ収集は、上記の分類では一部が該当するものの、完全には当てはまりません。多くの自治体では、「ステーション収集」と「戸別収集」が混在しており、特にステーション収集は独自の運用方法を持つため、分類に迷う存在です。ステーション収集では、複数の世帯が共同で利用するごみ集積所に、ごみを決められた日に出します。これは「Community Bins」に似ていますが、自治体が設置・管理を行う海外の事例とは異なり、日本では利用者や自治会が設置・管理を担うケースが多いのです。一方で戸別収集は、「Curbside Pick-Up」に近い方式といえます。つまり、日本の収集方式は、制度上も運用上も中間的な性格を持っており、世界的に見てもやや特異なスタイルを取っているといえるでしょう。
ステーション収集の成立背景
日本のステーション収集は、高度経済成長期以降の都市化の中で発展しました。とくに1964年の東京オリンピックを前後して、ごみ収集に自動車が導入されたことで、家の前ではなく道路際にごみを一時的に集める方式が普及し始めました。当初は住民がプラスチックバケツにごみを入れて出していましたが、洗う手間などから徐々にごみ袋が主流となり、今の「ごみステーション」型のスタイルが定着しました。また、日本では自治会や町内会といった地域組織が、ごみ集積所の設置や管理を担うのが一般的であり、地域の自助・共助に支えられた制度ともいえます。このような背景には、共同体意識や地域参加の文化が根づいていた戦後社会の構造が色濃く影響しています。現在ではその仕組みが高齢化や地域コミュニティの衰退によって再考を迫られていますが、ステーション収集はまさに「日本型ごみ収集システム」の象徴といえる存在です。
日本におけるごみ収集方式の現状
日本のごみ収集方式の構成比(2020年調査)
国立環境研究所が2020年に全国の自治体(939自治体)を対象に行ったアンケート調査によれば、日本のごみ収集方式は以下の通りです。
| 収集方式 | 割合 | 内容の概要 |
|---|---|---|
| ステーション収集のみ | 56% | ごみステーションに出されたごみを一括収集 |
| ステーション+一部戸別収集 | 35% | 高齢者世帯などを対象に一部で戸別収集を併用 |
| 戸別収集のみ | 8% | すべての家庭を対象に戸別で収集 |
この結果から分かるように、日本の多くの自治体では、依然として「ステーション収集」が主流となっており、戸別収集を全面的に実施している自治体はごくわずかです。とはいえ、高齢者支援などを目的に一部で戸別収集を導入する自治体が増えてきている点は注目されます。
戸別収集のメリットとデメリット
戸別収集は住民の利便性向上とともに、ごみ出しの質にも好影響を与える可能性がある一方で、行政運営上の課題も伴います。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | ・高齢者や子育て世帯の負担軽減 ・ごみ出し責任の明確化による分別の促進・景観 ・衛生の改善 |
| デメリット | ・収集車が各戸を回る必要があり、収集効率が悪化 ・収集人員・車両の確保が課題 ・コストが高くなる |
特に高齢化が進む地域では、ステーションまでごみを運ぶことが困難な世帯が増加しており、戸別収集は有効な対策となります。しかしその一方で、収集コースが複雑になり、運用コストが跳ね上がるリスクも無視できません。
導入を妨げる主な課題:コストと人員確保
2020年の調査では、戸別収集を導入していない自治体に対して「導入しない理由」を尋ねたところ、以下のような回答が得られました(複数回答可)。
| 導入を妨げる要因 | 回答率 |
|---|---|
| 収集コストが高くなる | 81% |
| 人員・体制の確保が困難 | 79% |
戸別収集は、住民一人ひとりのニーズに寄り添った制度ですが、それを支えるには、安定した予算と人材、そして地域に合った柔軟な制度設計が不可欠です。多くの自治体が導入を慎重に進めざるを得ないのは、こうした現実的な制約が背景にあるためです。
このように、日本のごみ収集方式は「住民サービスの向上」と「運用の持続性」のバランスの中で模索が続けられており、今後も地域ごとの実情に応じた選択が求められるでしょう。
戸別収集の進展と自治体事例
平塚市の事例:利便性と管理負担軽減を両立

戸別収集の目的と導入背景
平塚市では、高齢化や核家族化の進行を背景に、従来のステーション収集方式に課題を感じたことから、一部地区で可燃ごみの戸別収集を導入。将来的には市全域への拡大を視野に入れ、段階的に対象地域を広げている。住民の生活スタイルの変化に即した柔軟な制度設計が求められていることが背景にある。
利便性向上・管理負担の軽減・景観改善
戸別収集によって、自宅前でごみを出すだけで済むため、特に高齢者や子育て世帯にとっては大きな負担軽減につながっている。また、町内会や自治会が管理していた道路上のごみ集積所を廃止することで、担い手不足の課題にも対応。加えて、ごみ集積所が道路からなくなることで、景観の改善や通行の安全性向上といった副次的効果も得られている。
対象外の例や注意点
開発行為によって設置された専用のごみ集積所については、戸別収集の対象外とされ、従来の方法で出す必要がある。また、収集時間が従来と変更になる可能性があり、住民側の情報共有と協力も求められる。戸別収集時には、ネットやバケツなどによる飛散・動物対策も必要。
鎌倉市の事例:段階的導入と制度の体系化

モデル事業から全市実施への流れ
鎌倉市では2012年から一部地区(七里ガ浜、鎌倉山、山ノ内)でモデル事業を実施。その後、収集経費や市民理解の課題を経て一時中断されたが、2024年に戸別収集に関する予算が可決。2025年度(令和7年)からは一部地区で、2026年度(令和8年)からは全市に拡大予定。10年を超える検討と住民との対話を重ねてきたことが特徴。
実施目的:ライフスタイルの多様化・高齢者支援・不法投棄対策
戸別収集の目的は多岐にわたり、高齢化社会への対応、働き方の変化に伴うごみ出し負担の軽減、ごみ出しルールの徹底による不法投棄の減少、そして分別促進によるごみの減量化などが掲げられている。市民サービスの質の向上と環境配慮を両立させる政策として位置づけられている。
集合住宅・事業所への対応と補助制度の整備
集合住宅では、敷地内に専用のごみ集積所がない場合、新たに設置する必要がある。鎌倉市ではその整備・維持管理のための補助金制度を設け、住民や管理者の負担を軽減。事業所についても、小規模な排出量の場所に限って戸別収集対象とし、許可業者との契約が困難な場合に配慮。全体として、地域全体でのルール整備と財政的な下支えが特徴的である。
平塚市は比較的軽量な制度設計で段階的に取り組みを進めており、鎌倉市は長期的な検討を経て制度化と予算化を図った点で対照的です。いずれも地域特性と住民ニーズに応じて柔軟に制度を運用しており、今後の他自治体の導入に向けた参考モデルとなるでしょう。
増える収集箇所、問われる持続可能性
収集箇所の急増が示す戸別収集の影響
ごみ収集方式の多様化により、収集箇所の数が大幅に増加しています。特に東京都内のある区では、2000年には約7,000カ所だった収集箇所が、2019年には2万カ所を超え、実に約3倍に膨れ上がりました。この増加の背景には、高齢化や地域事情によって、従来のごみ集積所が利用しにくくなり、個別の戸別収集対応が進んだことがあります。
また、狭小路地や未加入世帯による集積所利用の困難さから、従来型ステーションの廃止や分散化も要因となっています。戸別収集は住民の利便性向上に寄与する一方、行政側には収集コストと体制維持という新たな負担をもたらしているのが実情です。
利便性の代償としての集積所の分散と小型化
都市部・郊外を問わず、ごみ集積所は「使いやすく」「管理しやすい」方向へと変化しています。具体的には、大型で一括管理されていたごみ集積所が、利用者の利便性を重視して小型・分散型へと転換しつつあります。たとえば、郊外の農村部で主流だった小屋型集積所では、遠距離までごみを運ぶ高齢者が増加するにつれて、より近く・小さな設備へのニーズが高まっています。
また、都市部でも、ルール無視や不法投棄が発生しやすい「不特定多数型集積所」が減らされ、代わりに世帯単位または小集団単位での集積所が新たに設けられています。これにより、ごみ出しのルール徹底やトラブル回避が期待されますが、同時に収集箇所数は増え、行政負担は増しています。
管理担い手の減少と地域の変化
ステーション収集が成り立っていた背景には、自治会や町内会による集積所の設置・管理という「共助の仕組み」がありました。しかし、現在はその基盤が揺らいでいます。自治会の加入率低下や役員の高齢化、担い手不足が進み、ごみ集積所の清掃・見守り・ルール徹底といった役割が果たせなくなりつつあります。さらに、自治会に未加入の住民がごみを出せず、不満やトラブルの原因になることもあります。
こうした背景から、行政が集積所の設置・運営に一部関与せざるを得ないケースも出てきており、従来の「市民協力型」から「行政主導型」への転換が静かに進行しています。ごみ収集体制の持続可能性は、こうした地域の変化にどう対応するかがカギとなるでしょう。
- 戸別収集の拡大や集積所の分散により、収集箇所数が急増(例:東京都内で3倍)
- 利便性と管理のしやすさを求めて、集積所は小型・分散型へと変化
- 自治会の衰退により、集積所の管理担い手が減少
- 未加入世帯や高齢化によるトラブルが増加傾向
- 行政による直接関与の必要性が高まり、「共助から公助」への転換が進む
自治体と市民に求められる新たな役割

住民理解なくして収集方式の再編は進まない
ごみ収集方式を見直す際、技術的・制度的な整備と同じくらい重要なのが、市民の理解と協力です。とくに戸別収集の導入には、これまでの生活習慣を変える必要があり、収集場所や時間、出し方など細かいルール変更への対応が求められます。
また、既存のごみステーションが使えなくなることで反発が起こることもあります。こうした中で重要なのは、自治体が十分な説明と情報提供を行い、住民の合意形成を丁寧に進めることです。単なる制度変更ではなく、「地域の課題をどう解決するか」という共通認識のもとで進める必要があります。
ごみ排出の「当事者意識」を育てる仕組みを
戸別収集は、各家庭の前でごみを出すことになるため、ごみの出し方や分別のミスが可視化されやすくなります。このことは、ごみ排出に対する「自分ごと」意識を育てる契機にもなります。住民一人ひとりが「どんなごみを出しているのか」「分別は守れているか」を再確認し、結果としてごみ減量や資源化につながる可能性があります。
一方で、無関心やマナー違反が目立つ地域では、戸別収集の効果が限定的になることもあります。ごみ排出の責任が個人に帰属するという構造を活かしながら、市民意識の啓発や情報提供を強化することが不可欠です。
ICTと地域力を生かす新しい合意形成のあり方
ごみ収集の再編は、自治体と住民だけでなく、多様な関係者の連携によって進めるべき課題です。ICTの導入により、例えば収集日程の通知やルールの周知、ごみ出し困難者へのサポート情報の発信などが容易になり、住民の負担も軽減できます。また、担い手不足が深刻な地域では、若年層や企業・団体の力を借りた新たな運営体制の構築も有効です。さらに、地域住民の合意形成のためには、オンラインと対面を組み合わせた説明会や意見交換の場を設けることが重要です。「押しつけ」ではなく「共につくる制度」としての設計が求められています。
- 収集方式の変更には住民の理解と納得が必要
- 戸別収集はごみ排出への「当事者意識」を高める契機となる
- ICTの活用により、情報周知や支援体制の強化が可能
- 地域内外の多様な担い手と協力し、運営体制を再構築することがカギ
- 合意形成には対話の場と丁寧な情報提供が不可欠
戸別収集は「持続可能な地域づくり」の入り口
ごみ収集の方式は単なる生活インフラの技術的な問題ではなく、私たちの地域社会の在り方そのものを映し出す“縮図”です。高齢化、地域コミュニティの希薄化、担い手不足、そして多様化するライフスタイル…これらの課題に、自治体や市民がどう向き合うかが、ごみ収集の制度に如実に現れています。戸別収集の導入が進むのは、利便性だけでなく、こうした地域課題への対応としての意味も大きいのです。
ごみ収集は、「自治のインフラ」としての性格も持ちます。つまり、地域のルールや仕組みを市民が自ら守り、支えることで成り立つ制度です。従来のごみステーションは、自治会など地域組織の協力を前提として維持されてきましたが、その土台が揺らいでいる今、戸別収集は新しい仕組みとして浮上しています。その一方で、個別収集に依存しすぎると、地域とのつながりが薄れるという懸念もあります。
これからの地域づくりには、ごみ収集をきっかけに、「どんな制度がこの地域に合っているのか」「誰がどの役割を担うのか」を共に考える視点が求められます。一律の制度ではなく、地域の実情に応じた柔軟な制度設計。そして、自治体・住民・事業者が協働する仕組みづくり。戸別収集は、その最初の一歩であり、持続可能な地域づくりの入口です。私たち一人ひとりが「自分のまちの未来」を見据えて、制度を使う側からつくる側へと意識を転換していくことが求められています。