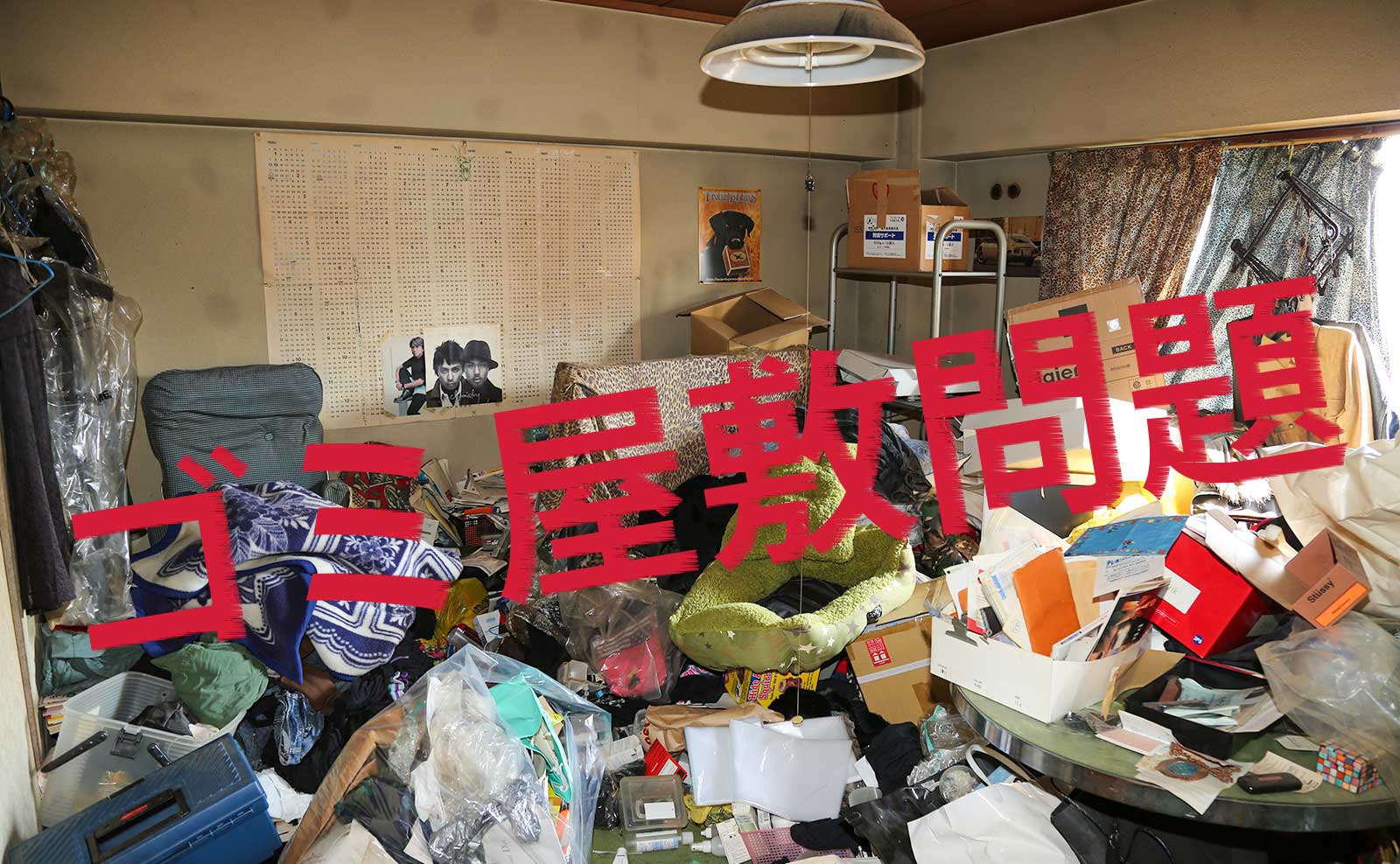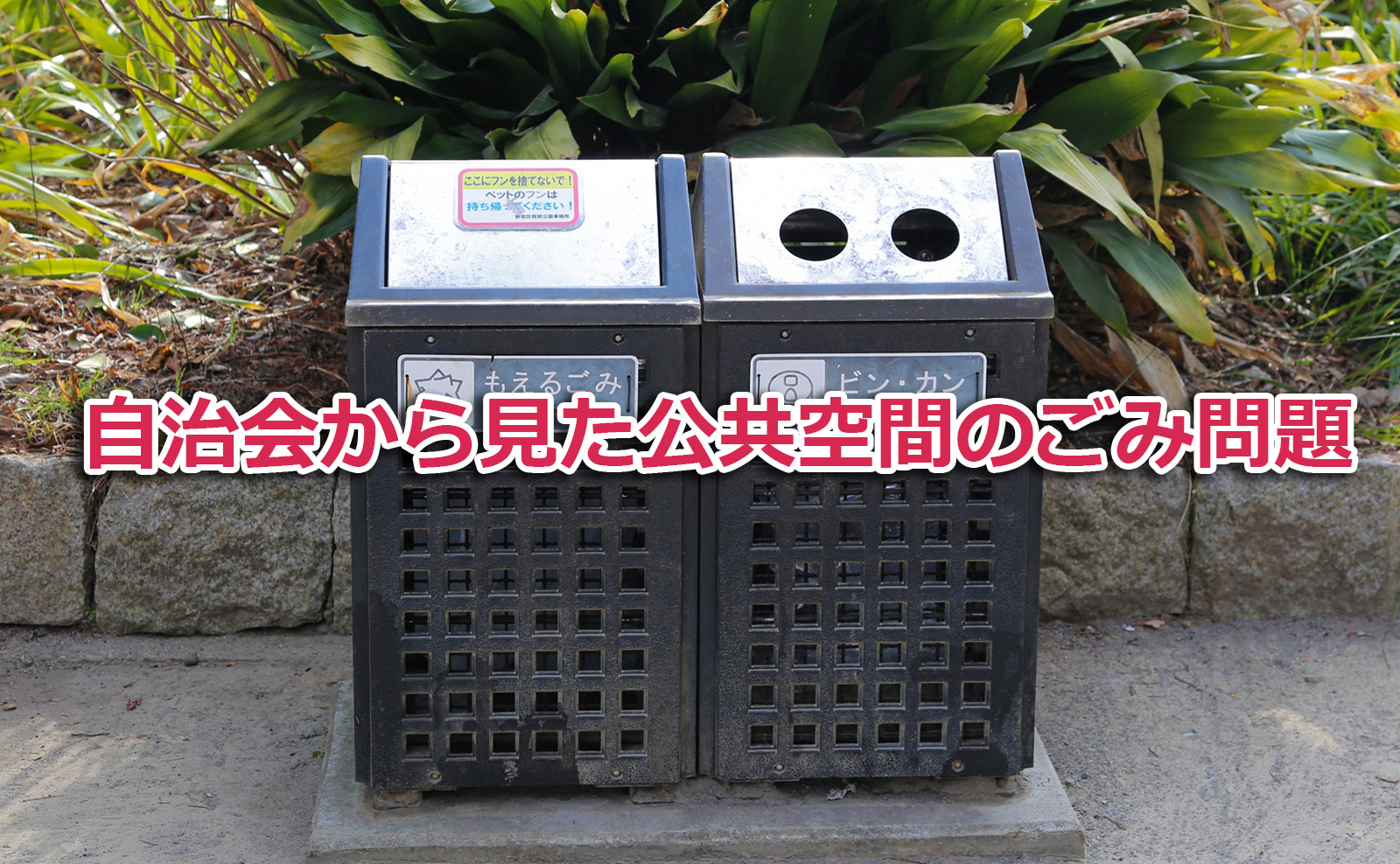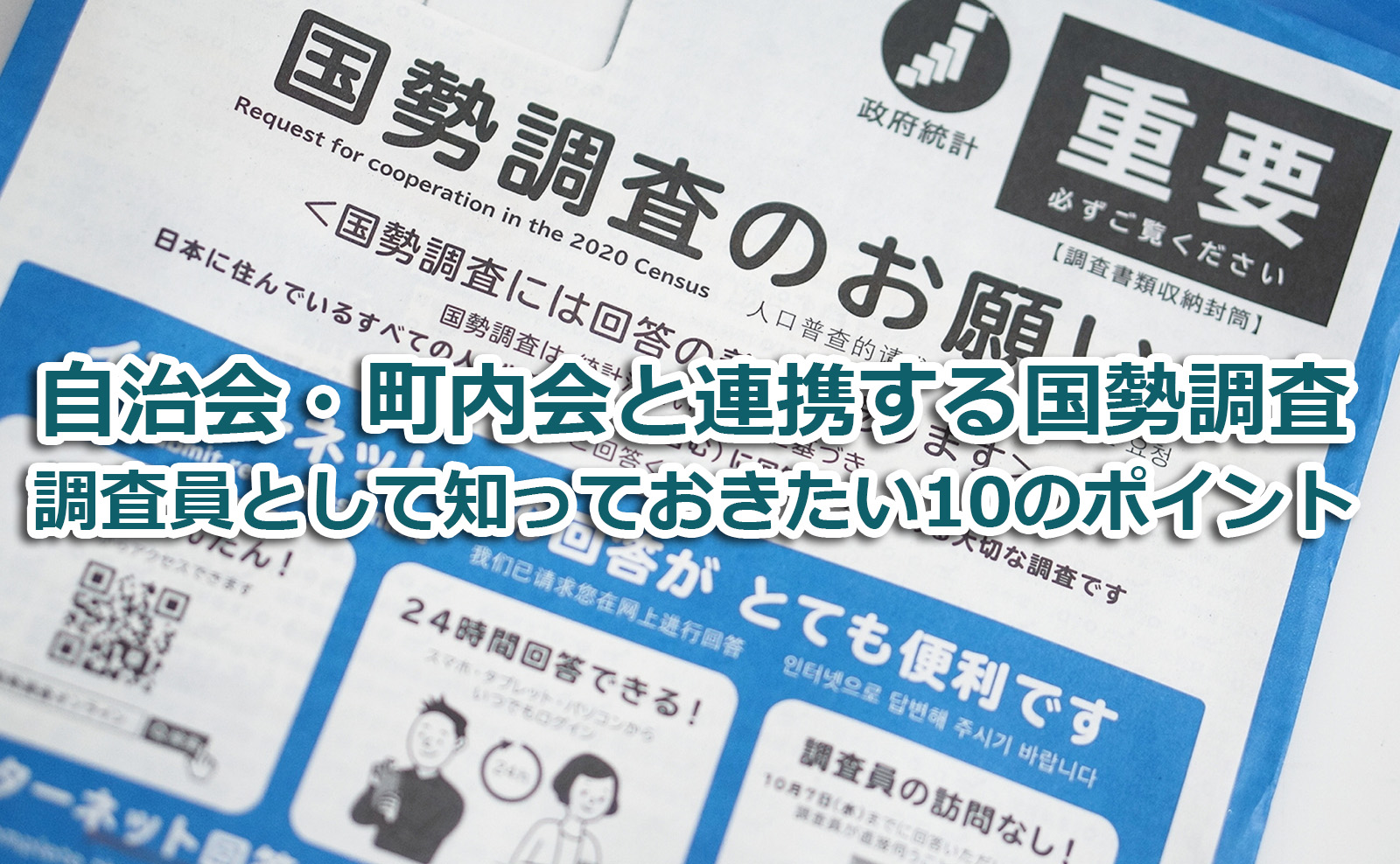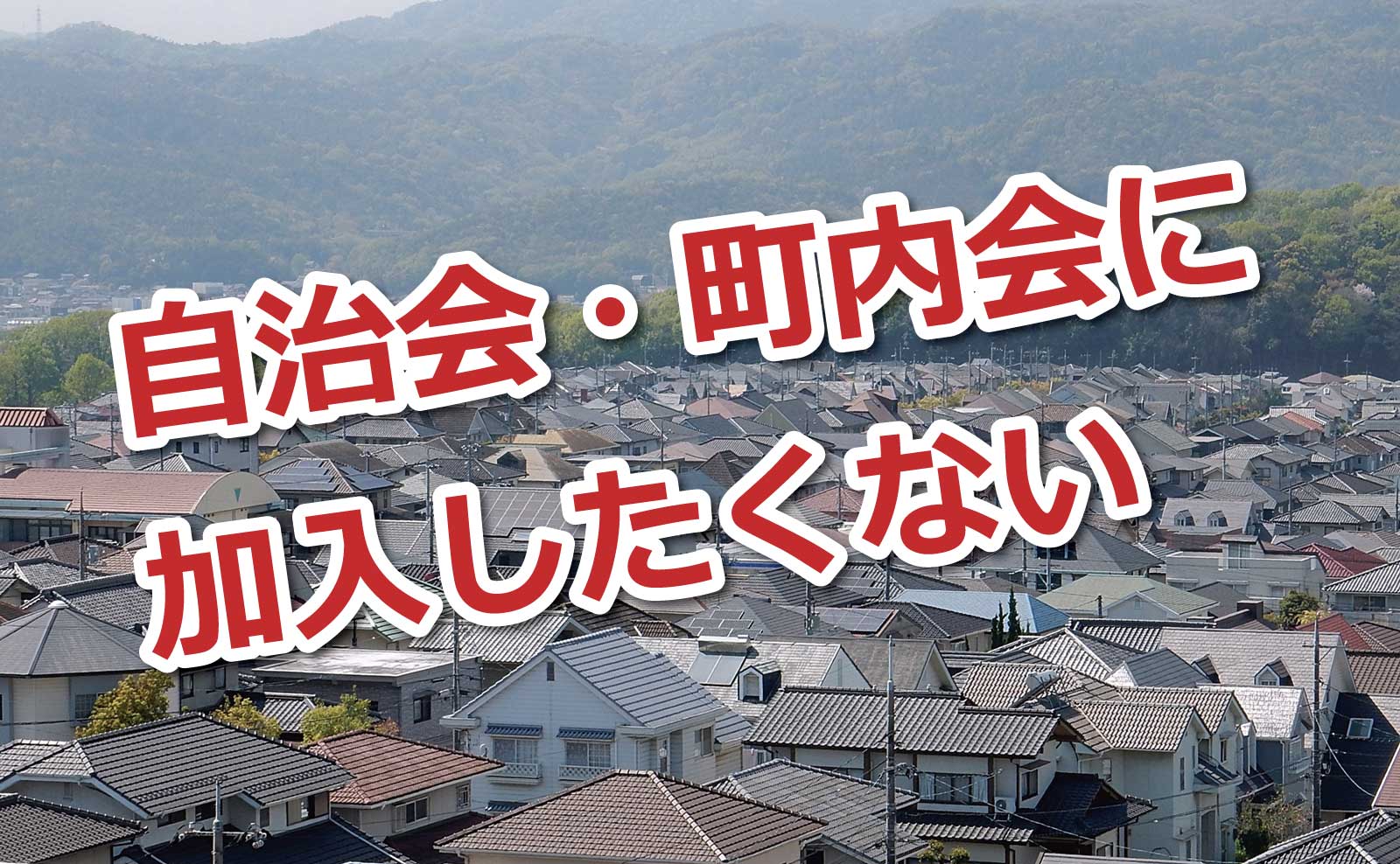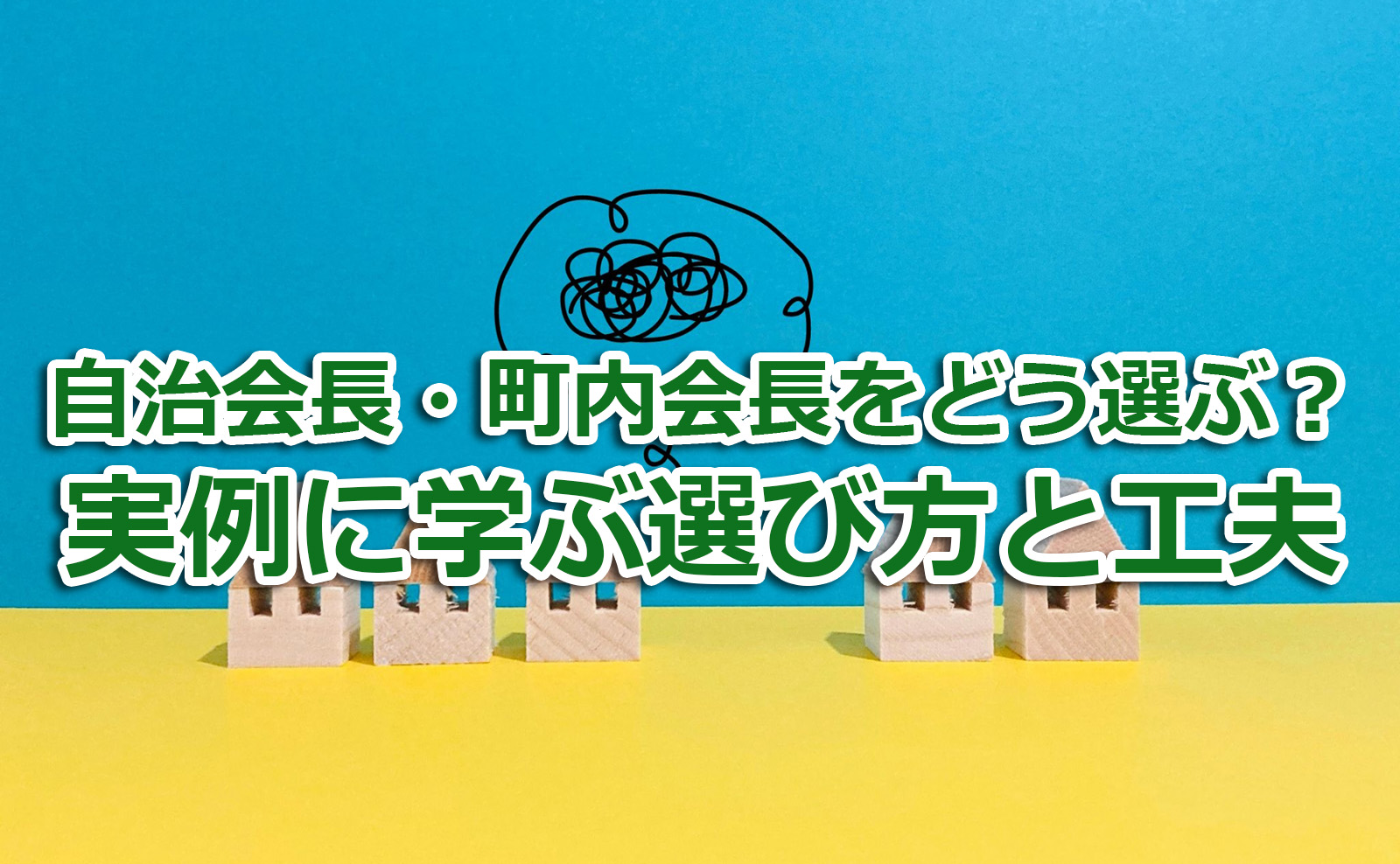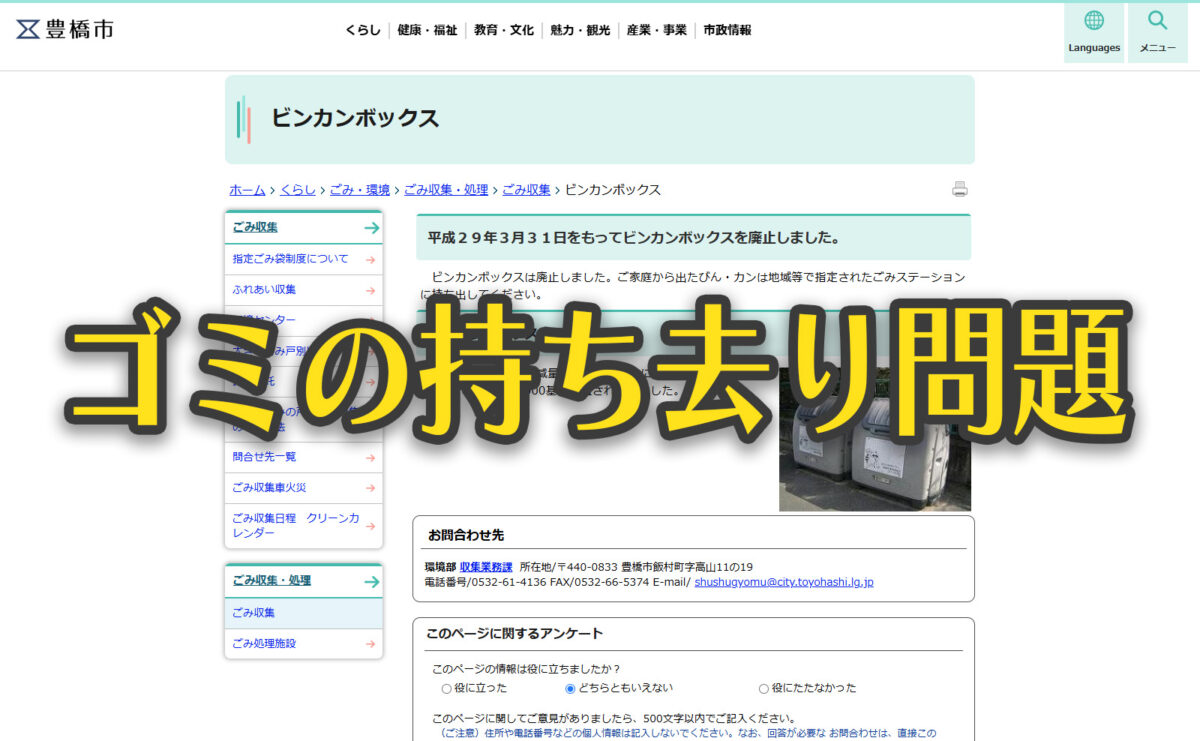
令和5年3月に環境省が発表した「令和4年度 資源ごみの持ち去りに関する調査報告書」によれば、全国1,741市区町村のうち約42%にあたる729市区町村が、資源ごみの持ち去り事案を認知していると回答しました。持ち去られる主な資源は空き缶・古紙・金属類で、市民からの通報が最多の認知手段です。問題としては「周辺住民からの苦情対応」が最多で、次いで「市収入の減少」が挙げられました。
対応策としては、パトロールや注意喚起、看板設置、警察との連携が多く、23.6%の自治体が持ち去り防止の条例を制定済みです。条例の多くは罰則規定(20万円以下の罰金など)を含みますが、施行上の課題として「違反者の特定の困難さ」や「実効性の低さ」が挙げられています。一方で、条例以外にも巡回・看板・立ち番・戸別収集などが一定の効果を上げており、自治体の工夫が求められる状況が明らかになりました。
https://www.env.go.jp/content/000121874.pdf
豊橋市のビンカンボックス
少し前の話になりますが、豊橋市では2017年3月にビンカンボックスが廃止されました。ビンカンボックスというのはおそらく豊橋市独自の仕組みで市内の約3000か所に設置されたガラス瓶、スチール缶、アルミ缶を捨てることができるボックスのことです。ボックスのサイズは縦横が1メートル弱、高さが1メートル強の大きさで開閉できるフタが付いています。
住民はこのビンカンボックスに空き瓶や空き缶をごみステーションの収集日と関係なく捨てることができます。市はこのビンカンボックスを定期的に空のものと置き換えて、回収した空き瓶や空き缶を資源として利用してきました。
そんな便利なビンカンボックスでしたがアルミ缶の持ち去りや空き瓶、空き缶以外のゴミの投入などの問題があるとともにビンカンボックスそのものの更新にかかる費用などから廃止が決定されました。その後は空き瓶空き缶はごみステーションに捨てるように変わりました。
豊橋市のごみの分別について
豊橋市のごみステーションに出すゴミの分別は以下のようになっています。
| もやすごみ | 木くず類、資源にならない紙くず類、皮革製品類、食用油 |
|---|---|
| 生ごみ | 食べ残し、調理くず |
| びん・カン | ガラスびん、空き缶 |
| プラマークごみ | 包装ビニール・食品容器・洗剤容器 |
| ペットボトル | 飲料用、酒類用、しょうゆ・みりんなど調味料用 |
| 危険ごみ | 蛍光管・有水銀の体温計、スプレー缶・針類・刃物類、充電式電池・使い捨ての電池・充電式電池が取り外せない小型家電 |
| こわすごみ | 小型家電類、その他日用品類 |
| 布類 | 衣類、シーツなど |
| うめるごみ | 陶磁器類、レンガ・ブロック類、ガラス類 |
このようなゴミの分別を行っている中で、びん・カンの収集日のアルミ缶、こわすごみの収集日の小型家電や金属類がごみ持ち去りの対象とされています。これらのごみの収集日には軽トラなどで外国人の人たちがごみステーションに乗り付けてめぼしいものを持ち去っていきます。
ごみを持ち去る側の事情
ごみを持ち去るのは「豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条例」により禁止されています。しかしながらごみを持ち去る彼らの事情、そこに至るまでの背景を想像したとき、単純に「悪」と切り捨てられない現実があります。
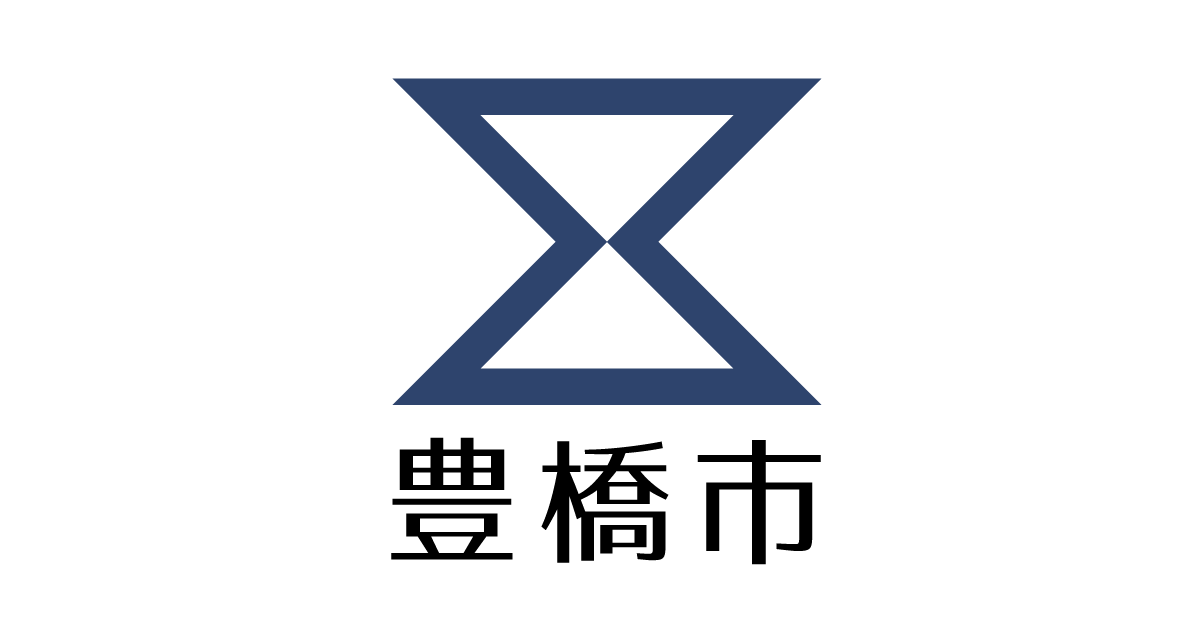
たとえば、日本に働きに来ている技能実習生の中には、契約不履行や長時間労働、賃金未払といった問題に苦しみ、実習を途中で辞めざるを得なかった人もいます。コロナ禍で多くの仕事が失われた2020年以降、その影響は外国人労働者や日雇いで暮らす人々にとって、とりわけ深刻でした。帰国もままならず、頼る家族もいない中で、「売れるごみ」を頼りに生き延びている。そんな人たちが、現にいるのです。
彼らがしているのは「窃盗」ではありますが、同時に「生きるための行為」でもあります。もしごみの持ち去りが、わずかな現金収入の唯一の手段だったとしたら。その行為を一律に排除し、処罰の対象とするだけで、果たして社会は健全なのでしょうか。
本来であれば、生活困窮者は生活保護などの制度に繋がるべきです。しかし、制度にアクセスできない、あるいは申請をためらう、そもそも制度の存在を知らない人もいます。支援の仕組みに乗れない人が、せめて自力で生活を支えようとしている。その姿勢すら、今の社会は「迷惑」として切り捨てていないか?そう問い直す必要があるのではないでしょうか。
ゴミの持ち去りに対して住民はどう対応すればよいのか
ごみステーションに軽トラックが現れ、収集日前にびん・カンや金属類を持ち去る光景を見たとき、多くの住民が不安や戸惑いを感じます。実際僕も何度も見かけましたが何か話しかける勇気はありません。日本語が通じるのかもわかりませんし何らかのトラブルになっても困ります。
そして彼らが生活のために、生きるためにごみの持ち去りという行為をしているということも想像できるだけに「条例」を根拠に咎めることができない気もします。豊橋市ではごみの持ち去りについて
- 20万円以下の罰金を科される場合があります。
- 行為者の氏名などを公表する場合があります。
としていますが、それでいいのか?という想いがあります。
ごみステーションに映る社会の矛盾
豊橋市のように、ごみの分別制度が整い、資源回収が効率よく進められている自治体では、持ち去り行為は明確に「ルール違反」とされます。しかし、実際にごみを持ち去る人たちの姿を目にしたとき、多くの市民は戸惑います。「注意すべきか」「見て見ぬふりをすべきか」その判断は簡単ではありません。
たしかに、持ち去りは条例違反であり、市の回収体制を崩すものです。一方で、それが「生活の糧」になっている人もいます。単にルールを守らせるだけでは、根本的な問題は解決しないのではないでしょうか。
ごみステーションという日常の一場面に、今の社会が抱える矛盾や行き詰まりが浮かび上がっているように思います。経済的に苦しむ人と、それを迷惑に感じる住民、そして取り締まりを行う行政。その三者のあいだにある距離感は、私たちの社会が抱えるすれ違いそのものです。
「正しい行い」と「思いやり」は、時にぶつかることがあります。そのとき、どちらか一方だけを貫くのではなく、両方を抱えながらどう向き合うか?それこそが、私たちに求められている姿勢ではないかと思います。