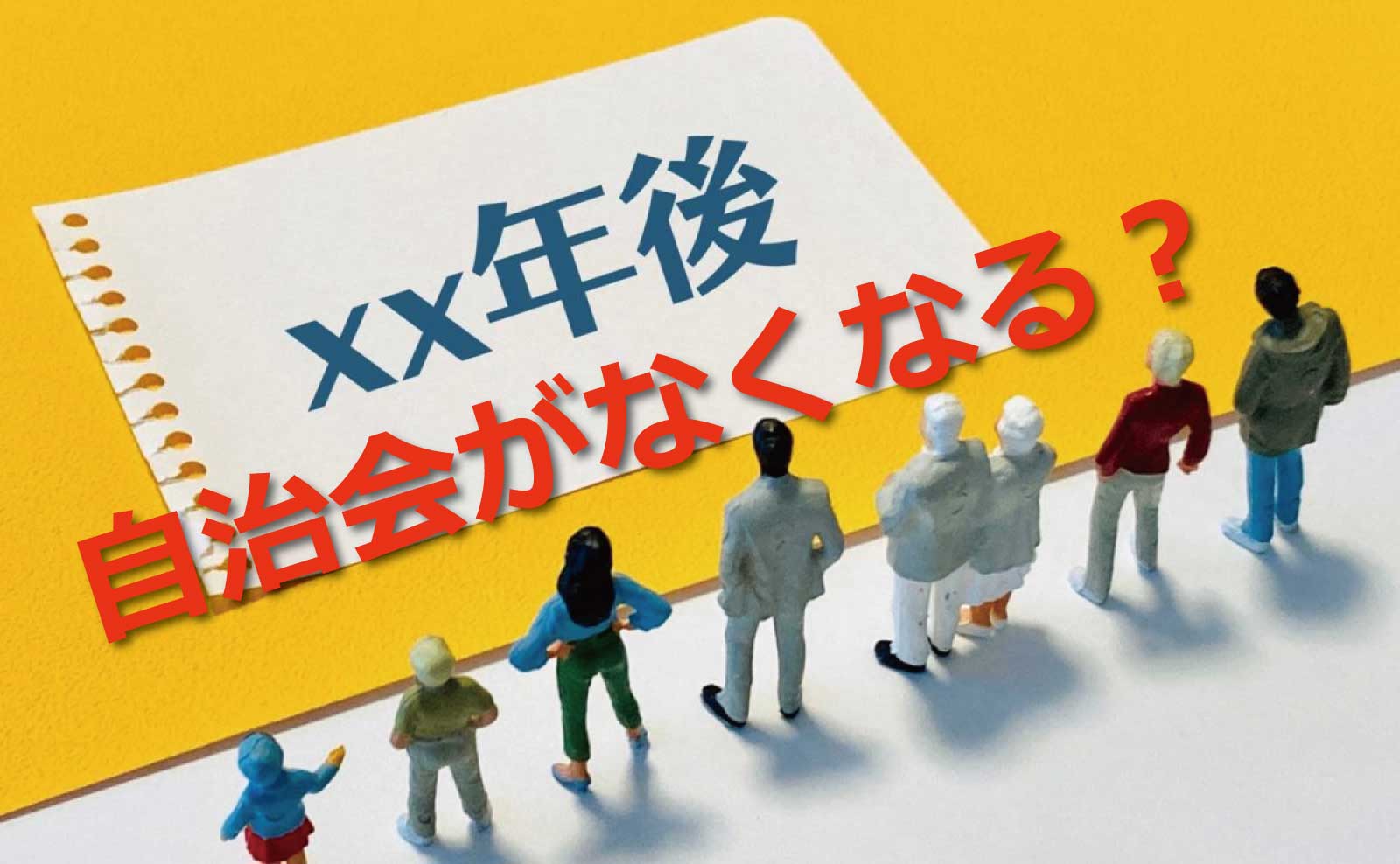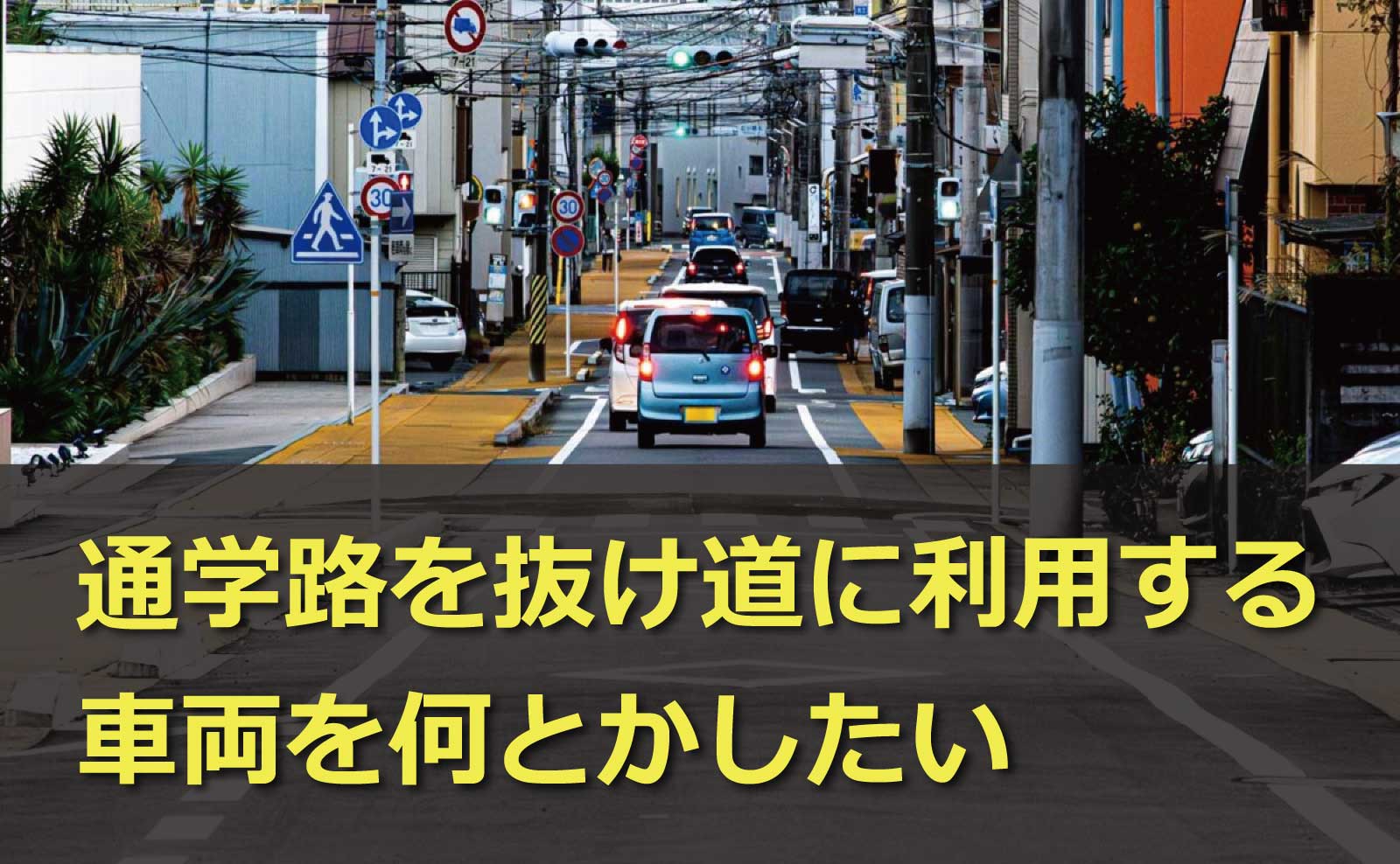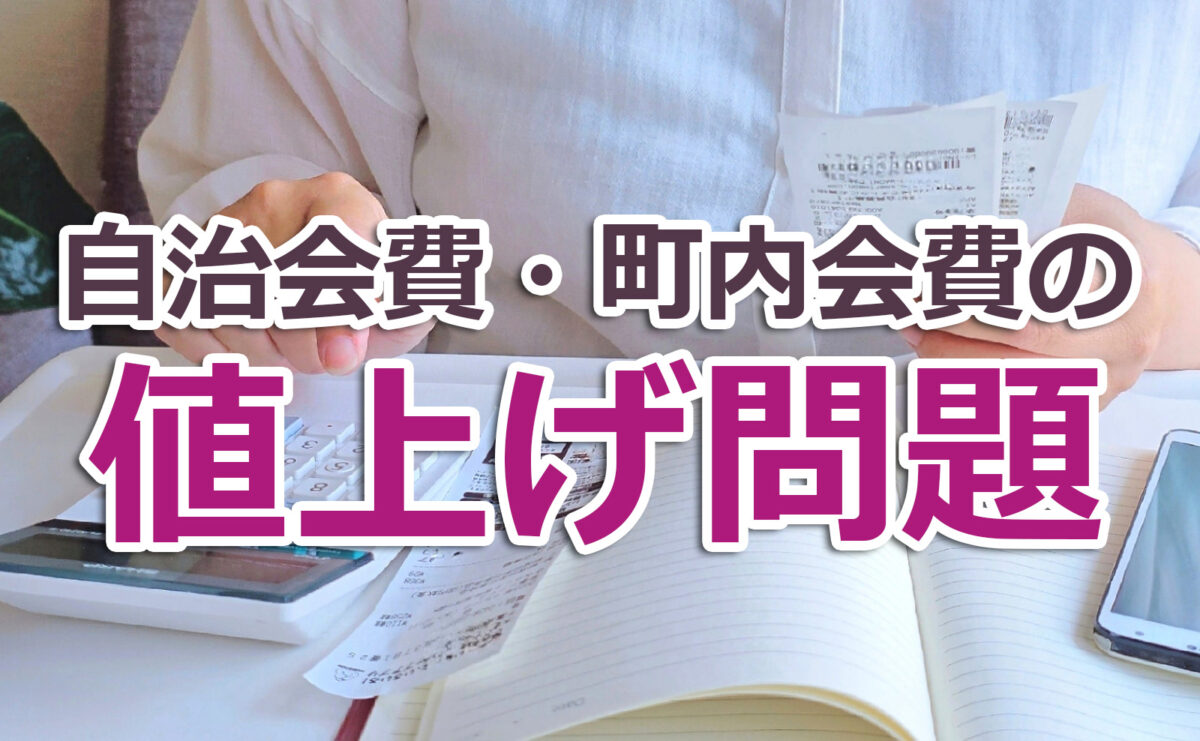
はじめに
近年の物価高は、私たちの日常生活だけでなく、地域社会の基盤である自治会の運営にも影響を与えています。電気代や印刷費、消耗品の価格が上がる中で、多くの自治会や町内会が「会費の値上げ」を検討せざるを得ない状況に直面しています。
しかし、値上げは単なる数字の問題ではありません。住民の生活に直結するだけでなく、自治会や町内会そのものの存続や地域のつながりに大きな影響を与えかねません。
「値上げに協力して地域を守ろう」という声がある一方で、「家計が苦しいのに負担は無理」「自治会や町内会の必要性を感じない」と反対する声もあります。ここでは、実際の事例や住民の声を交えながら、この問題を多角的に考えてみます。