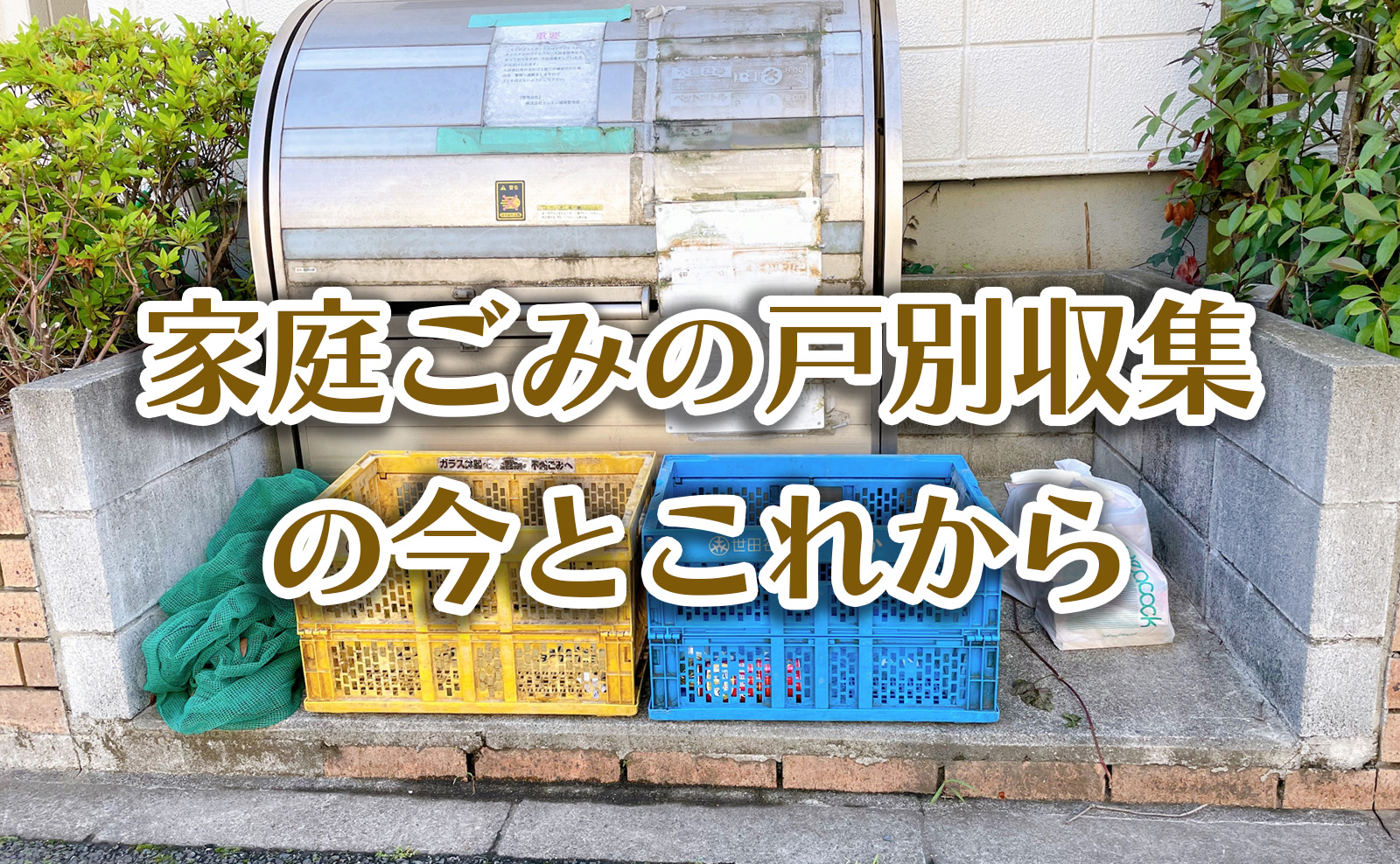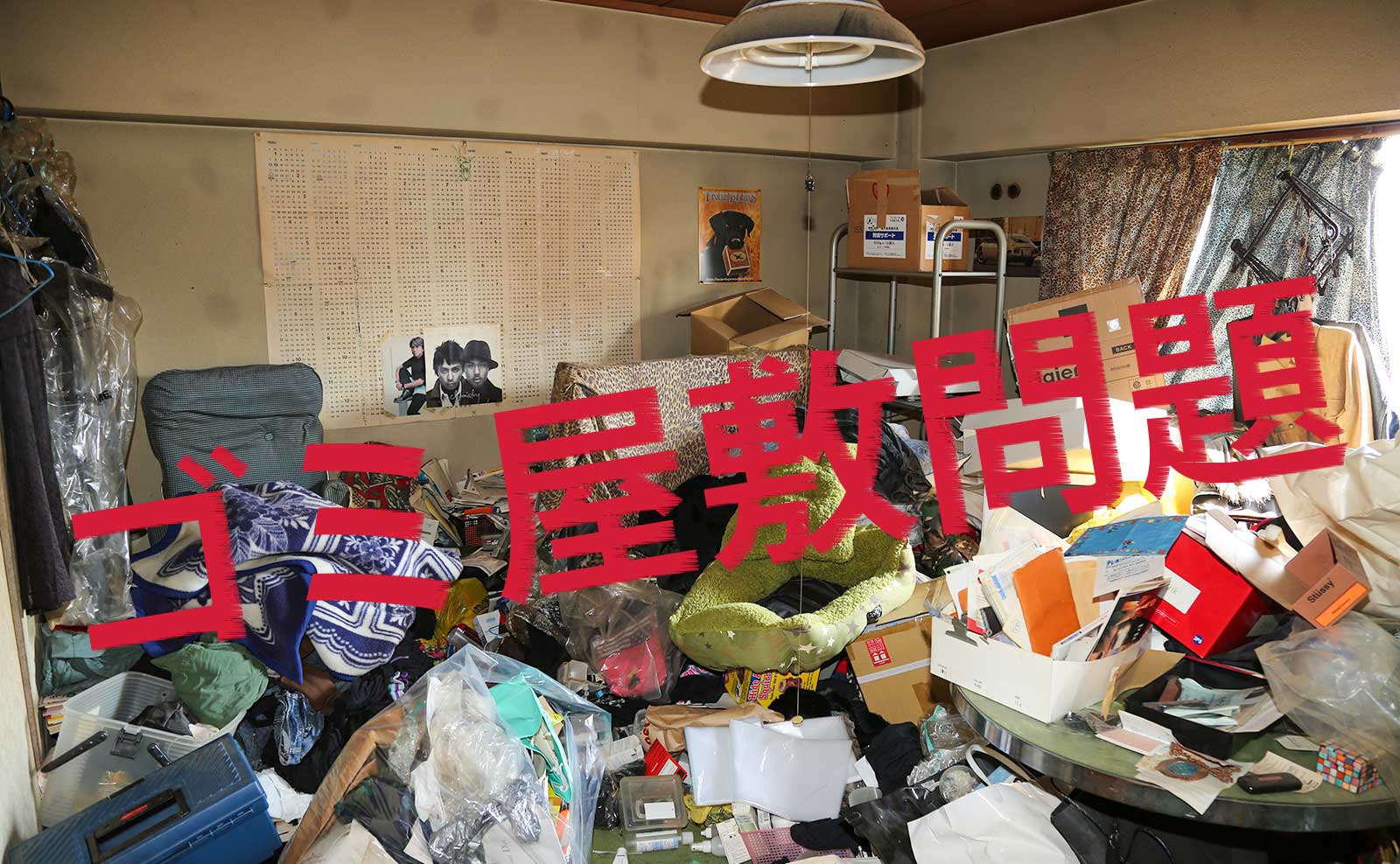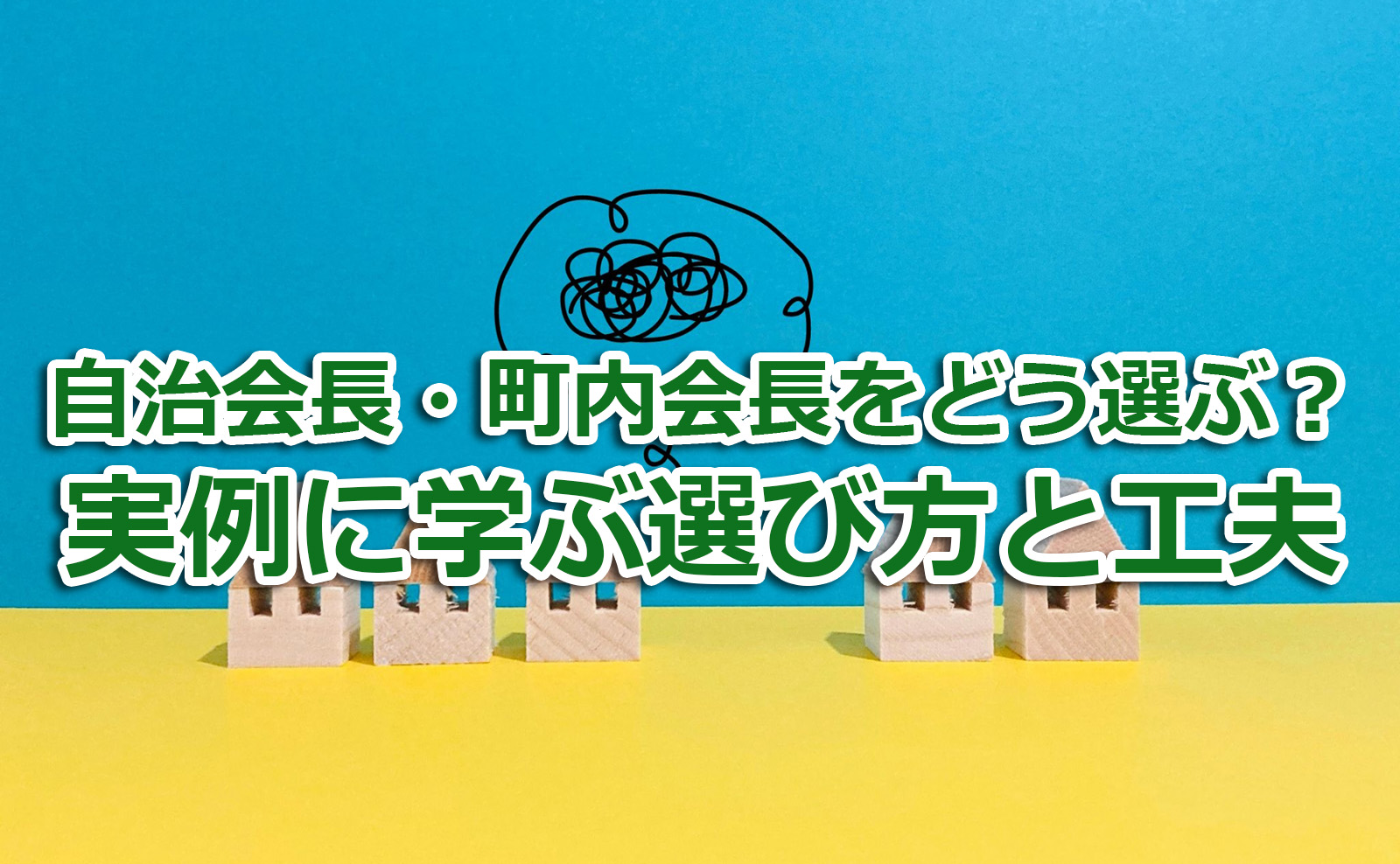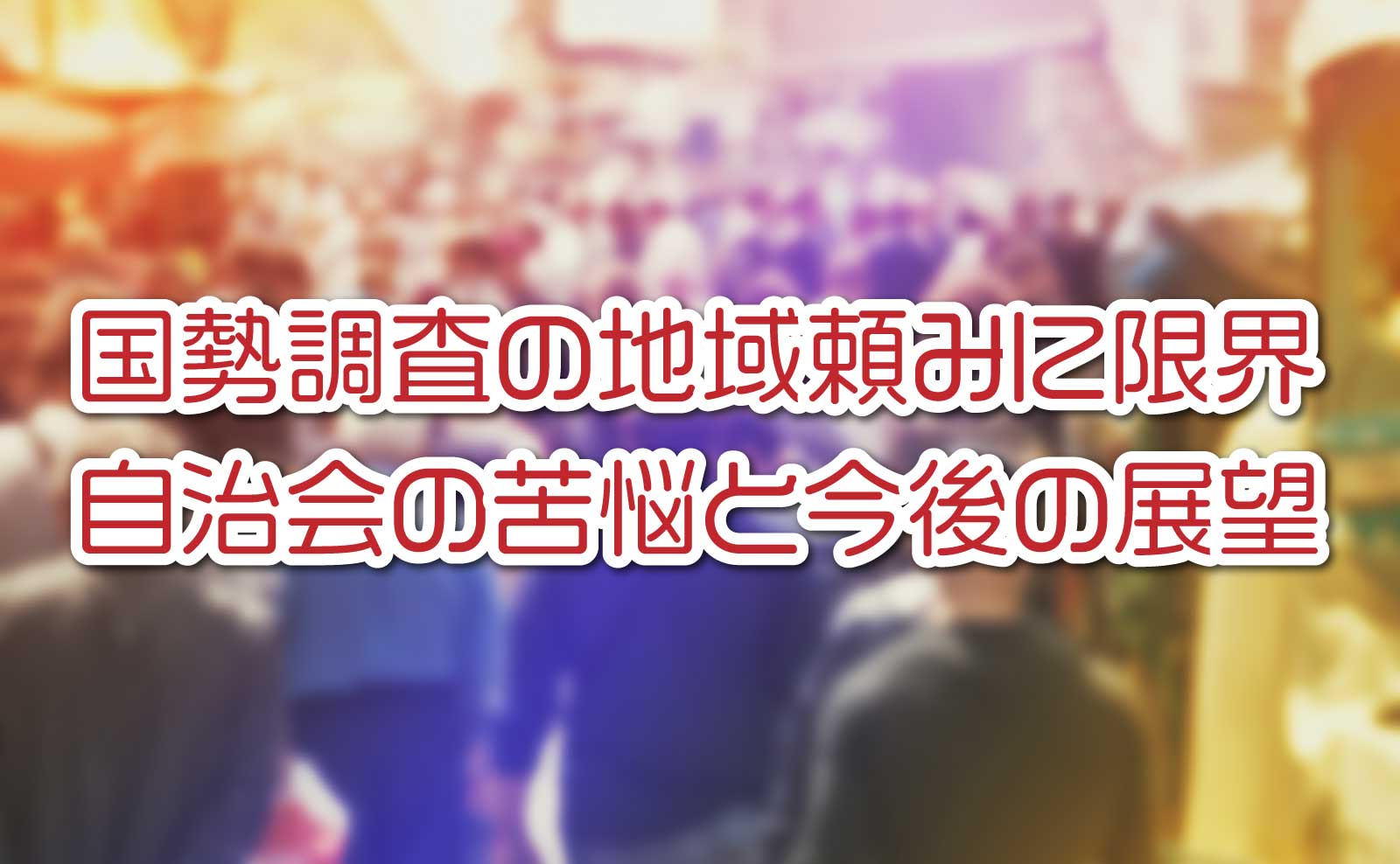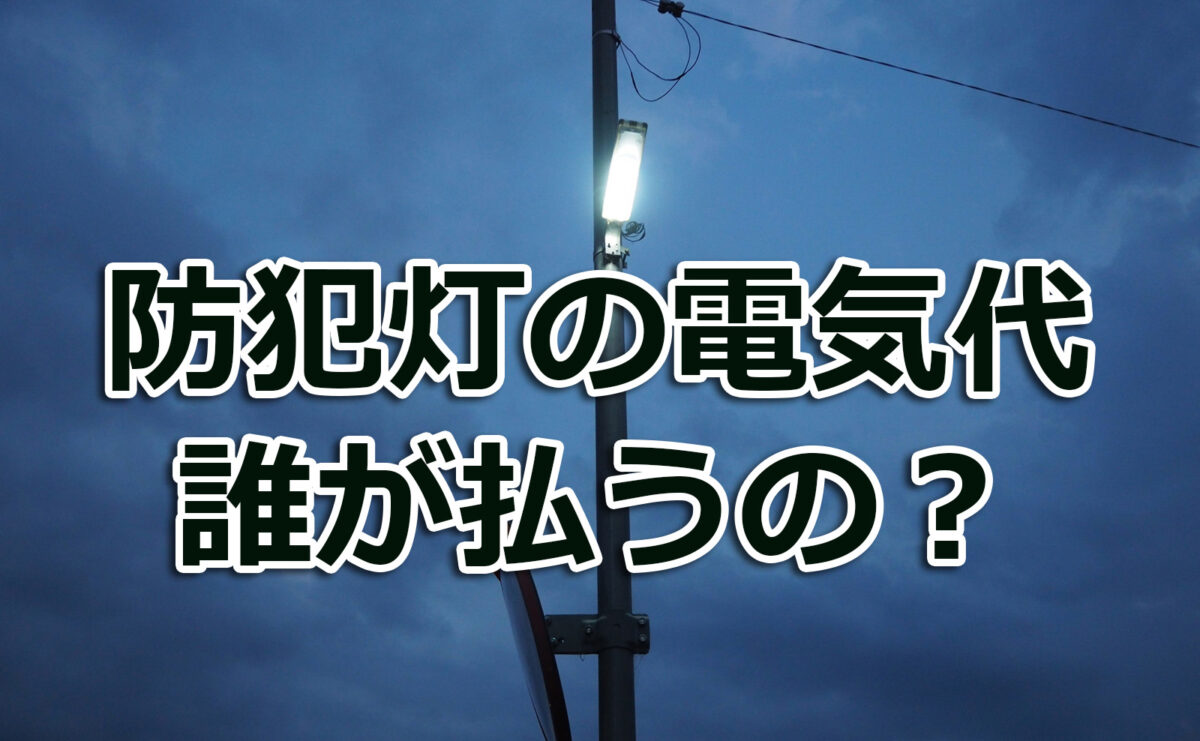
夜道を歩いていて、ふと見上げると、ポツンと光る防犯灯。そのあかりに「ほっとした」という経験を持つ方は多いのではないでしょうか。とくに住宅街や路地裏など、街路灯が少ない場所では、防犯灯の存在が安心につながります。事故や犯罪を防ぐ役割はもちろん、子どもや高齢者の夜の外出にも欠かせないインフラです。
けれども、この身近な灯りについて「電気代って、誰が払っているんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか。なんとなく行政が全部面倒を見てくれているように感じる方もいれば、「自治会がやっているらしい」と耳にしたことがある方もいるでしょう。実際には、自治体が管理する「街路灯」と、自治会や町内会が維持する「防犯灯」とでは大きな違いがあり、後者の多くは住民自身の会費で電気代を賄っています。
とはいえ、自治会や町内会にとって防犯灯の電気代は、決して小さな負担ではありません。世帯数が減った地域や高齢化が進んだ地域では「会費だけではまかなえない」「公平に負担しているのか疑問」といった声も出てきます。実際にトラブルの火種になることも少なくなく、「どうやって維持していくのか」は全国的に共通する課題となっています。
この記事では、防犯灯の電気代をめぐる仕組みや実際の事例、補助制度の活用方法、そしてこれからの解決のヒントについて、リアルな視点でわかりやすく整理していきます。身近な「まちのあかり」の裏側を、一緒に見ていきましょう。
防犯灯と街路灯のちがい

夜道を照らすあかりには、大きく分けて「街路灯」と「防犯灯」の二種類があります。どちらも私たちの暮らしを安全にする役割を果たしていますが、その設置や管理の仕組みはまったく異なります。
まず「街路灯」は、国道や県道、市道といった道路に沿って設置されている公的な照明です。道路管理者である行政が設置し、維持や電気代の負担も市や県が行います。つまり税金でまかなわれており、住民は直接お金を払っていません。大通りや駅前の広い道で見かける明るい照明は、ほとんどがこの街路灯にあたります。
一方で「防犯灯」は、住宅街の細い路地や袋小路、子どもたちの通学路などに設置されることが多いあかりです。こちらは多くのケースで自治会や町内会が設置し、電気代や維持管理の費用を会費から支払っています。規模も小さく、民家の軒先や電柱に取り付けられていることが多いのが特徴です。
この違いを知らないと、「どうして自治会が防犯灯の電気代を?」という疑問が湧いてきます。行政が管理している街路灯と同じように思われがちですが、実際には「地域の安全を住民自身で守る」という発想から、防犯灯は地域の自主的な取り組みとして広がってきました。そのため、電気代や球切れの交換費用まで、自治会の役員や会計担当者が頭を悩ませながらやりくりしているのが現状です。
街路灯と防犯灯の役割の違いを整理してみると、「なぜ自治会が電気代を負担しているのか」という構図が見えてきます。表向きはどちらも「まちを照らすあかり」ですが、裏側には行政と住民との役割分担が存在しているのです。