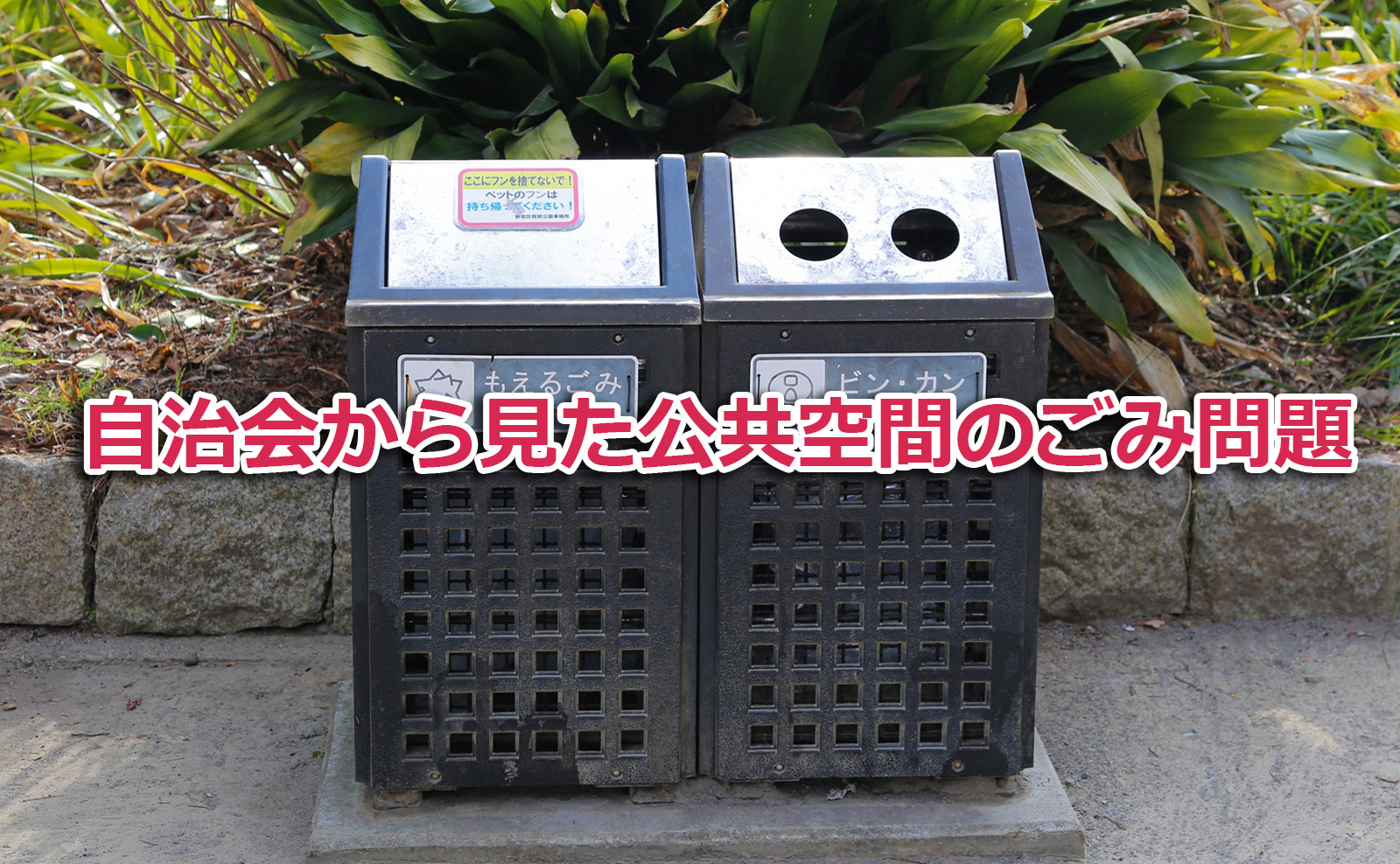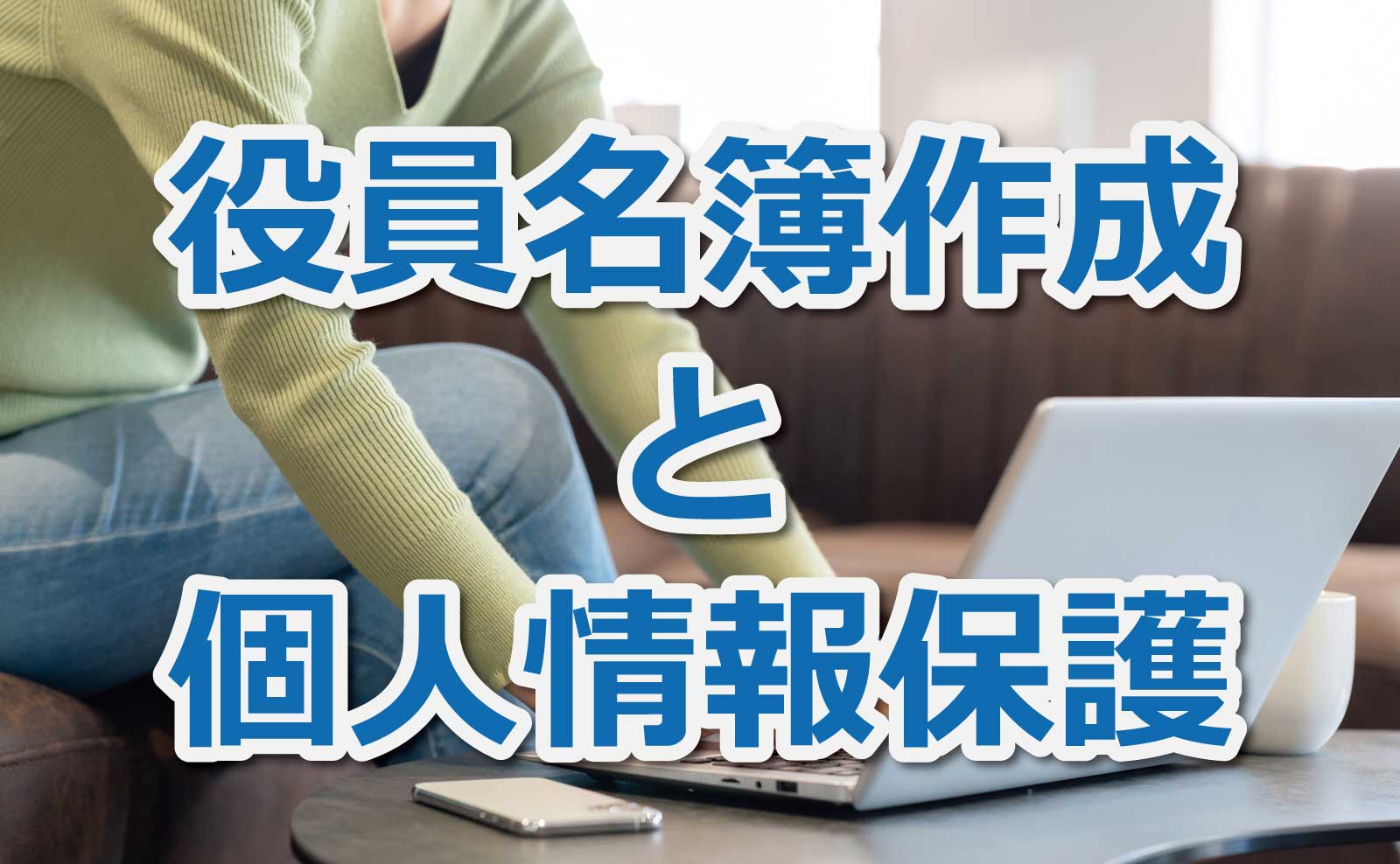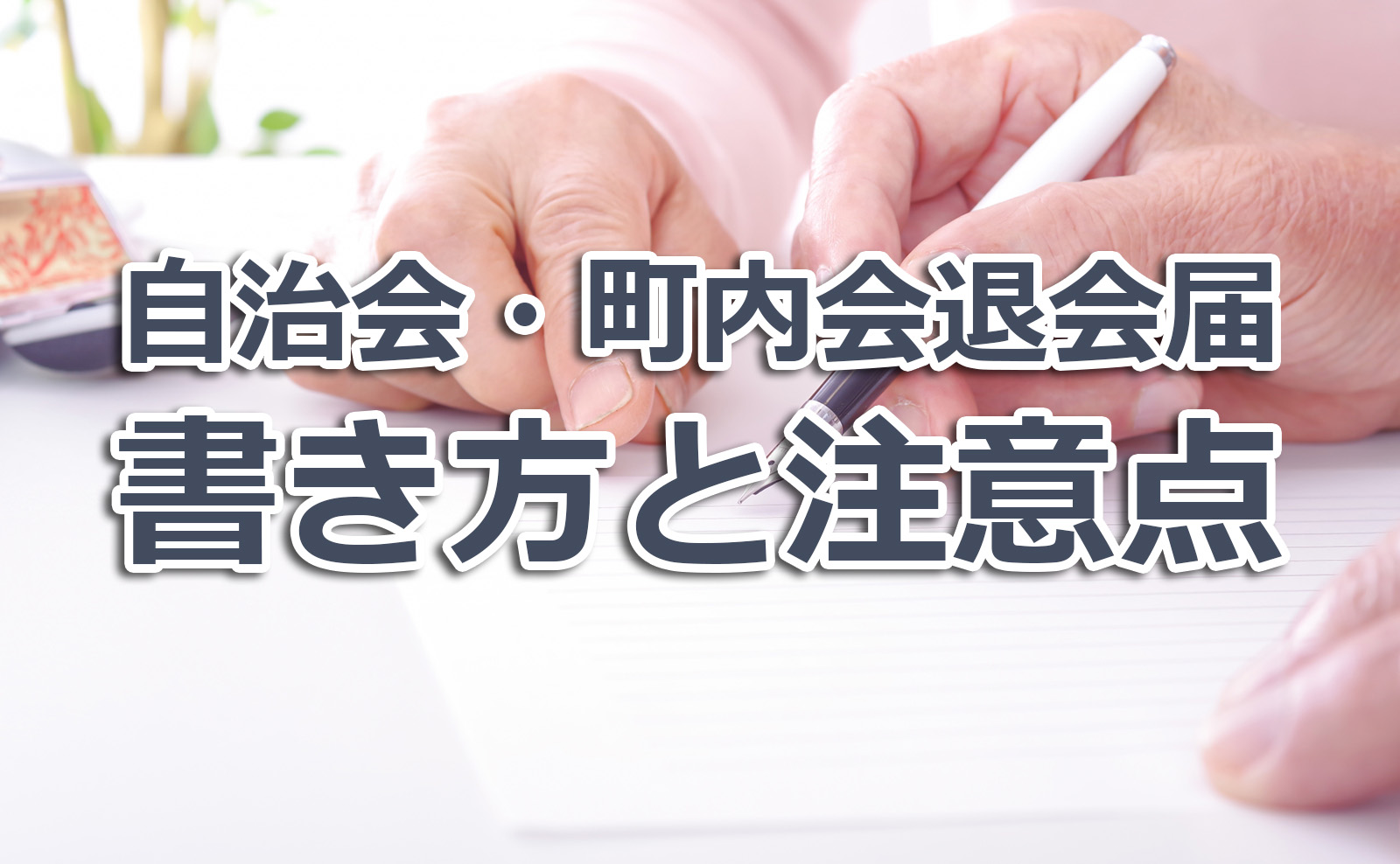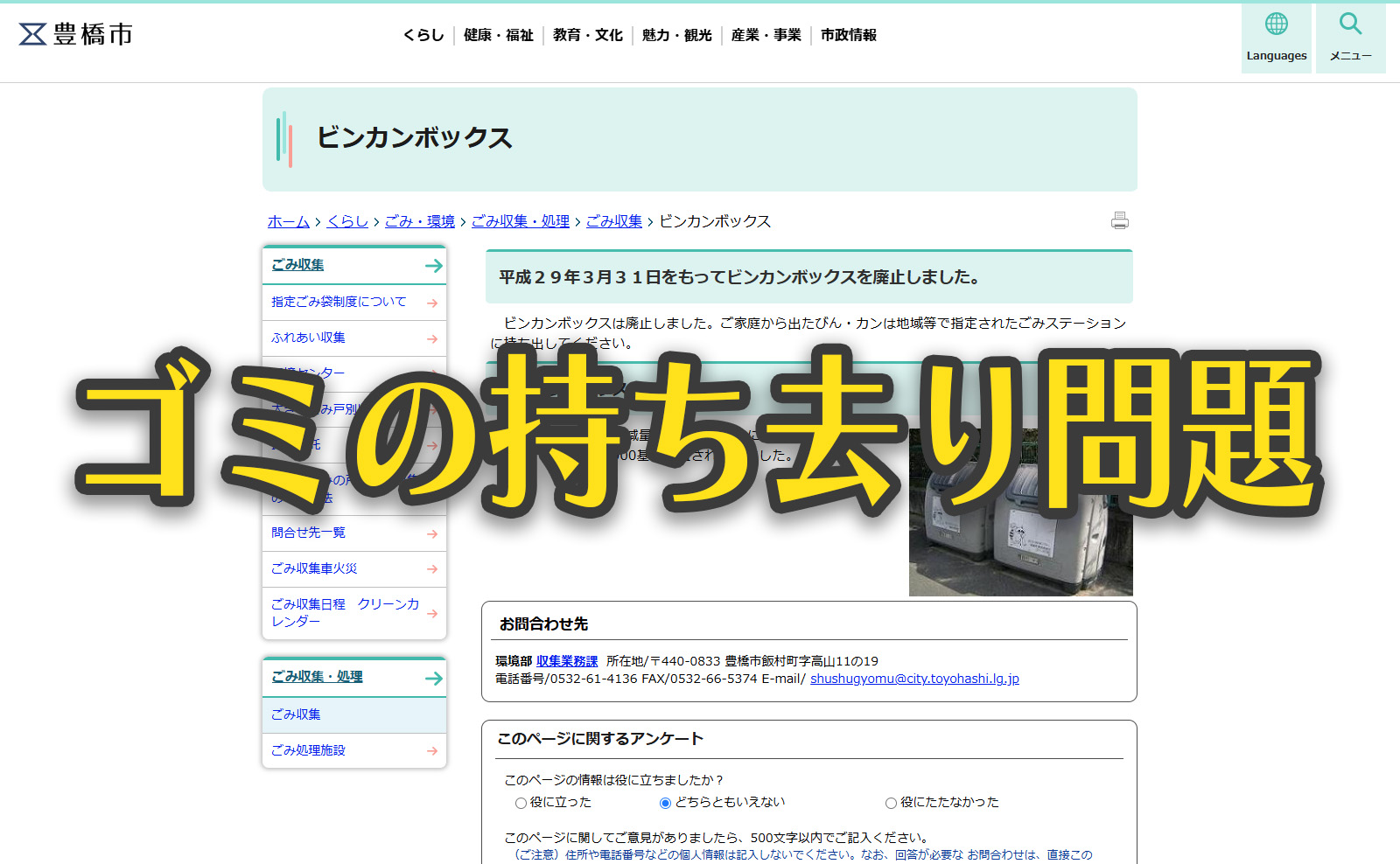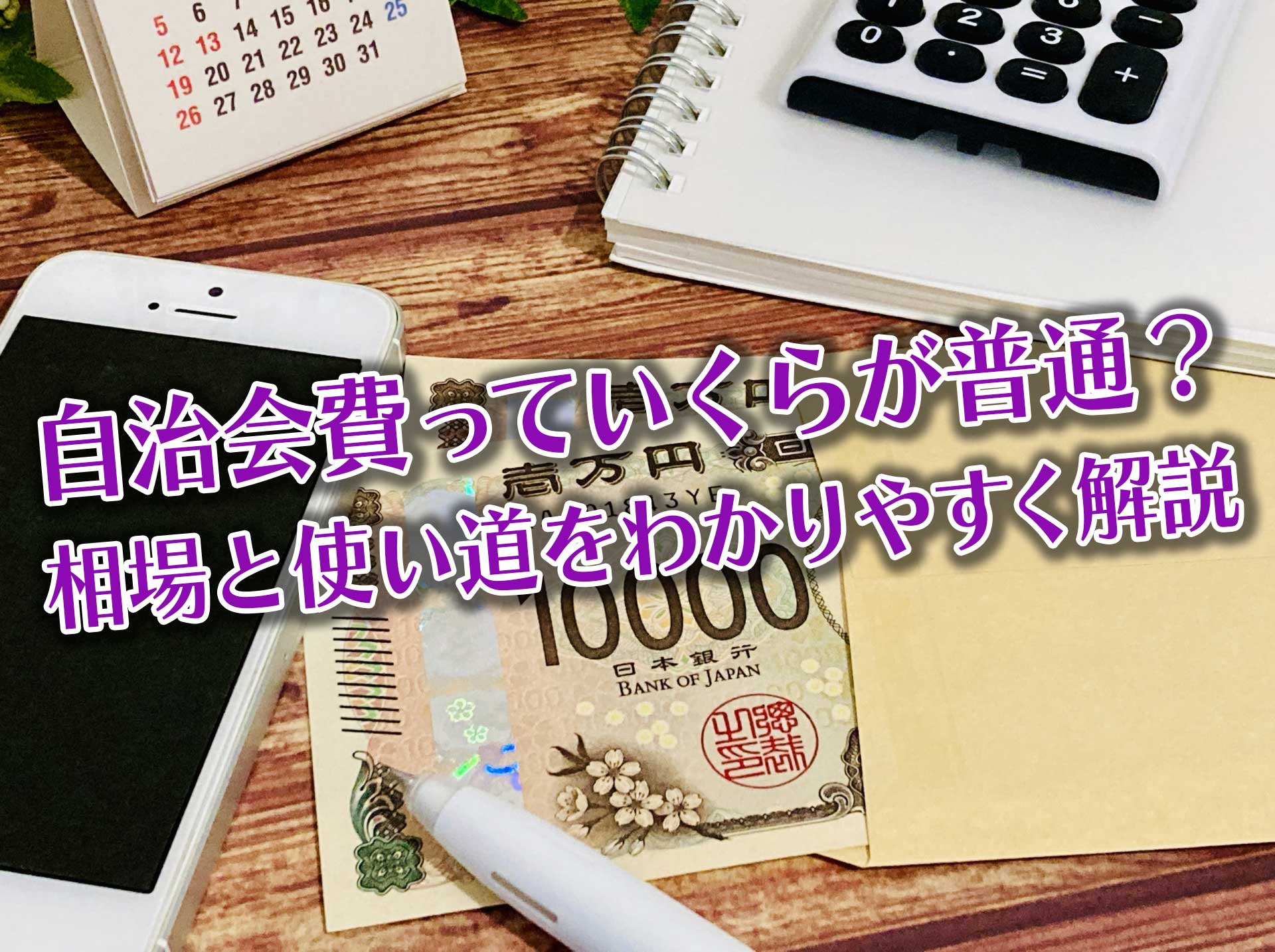2021年に新しく生まれ変わった豊橋市斎場
私たちの自治会に隣接して建てられている豊橋市の斎場は、2021年に新しい施設として生まれ変わりました。斎場というと、一般的には「縁起が悪い」「できれば近づきたくない」といったイメージを抱かれる方も少なくありません。確かに、人の死に直結する施設であり、忌避感や心理的な距離を感じるのも自然な反応でしょう。
けれど、私にとってこの斎場は、そうした印象とは少し違います。というのも、この場所は子どもの頃からずっと身近にあり、特別な「異質さ」を感じたことがなかったからです。むしろ当時の斎場のアスファルト舗装された広い駐車場は、キャッチボールやローラースケート、ラジコン遊びの格好の場所でした。野山くらいしか遊ぶ場所の少なかったあの頃、ここは地域の子どもたちにとって貴重な「整備された空間」だったのです。
もちろん、施設の本来の用途や意味を理解するようになってからは、相応の敬意と節度を持って接するようになりましたが、「斎場=嫌われる施設」という固定観念にはどうしても違和感があります。そうした体験を持つ地域住民の一人として、斎場の再整備におけるPFI事業の導入や、その後の運営のあり方には未だに疑問を感じています。
PFIという手法は、民間の資金やノウハウを活用して公共施設を整備・運営する新しい枠組みです。そのメリットや課題は一概には語れませんが、斎場のように地域に根ざした公共施設であるからこそ、その効果や影響を実感として捉え直す必要があると感じています。