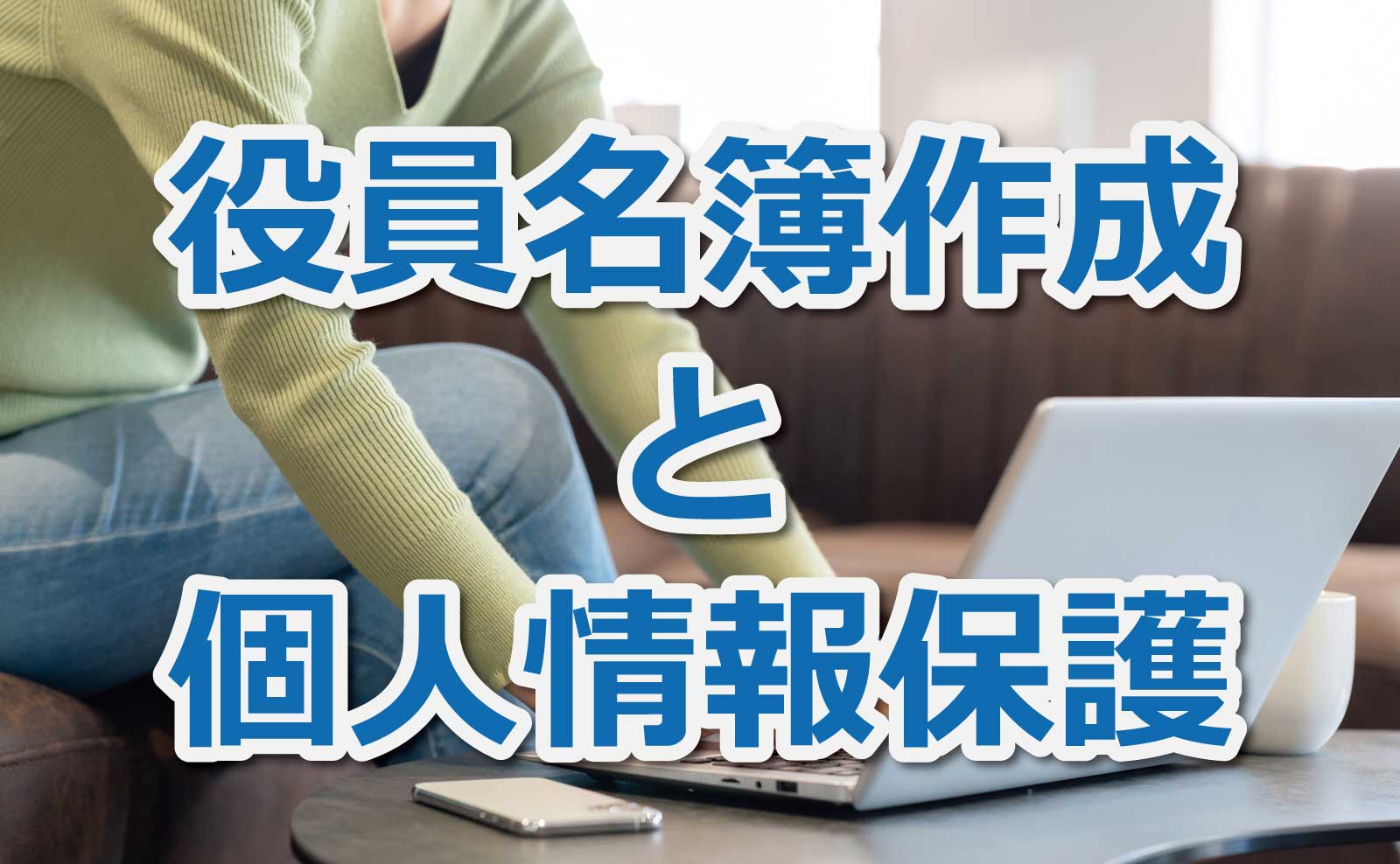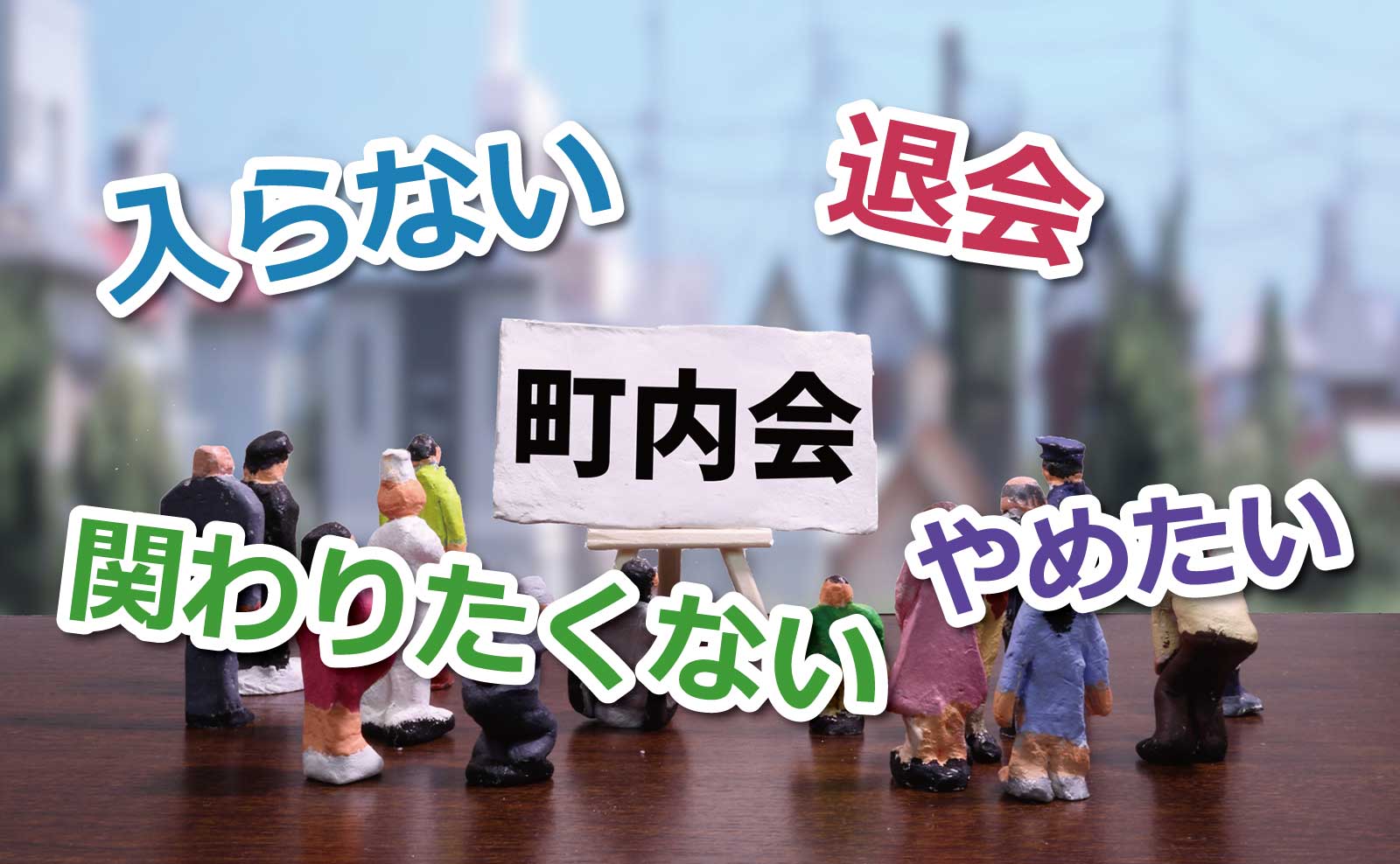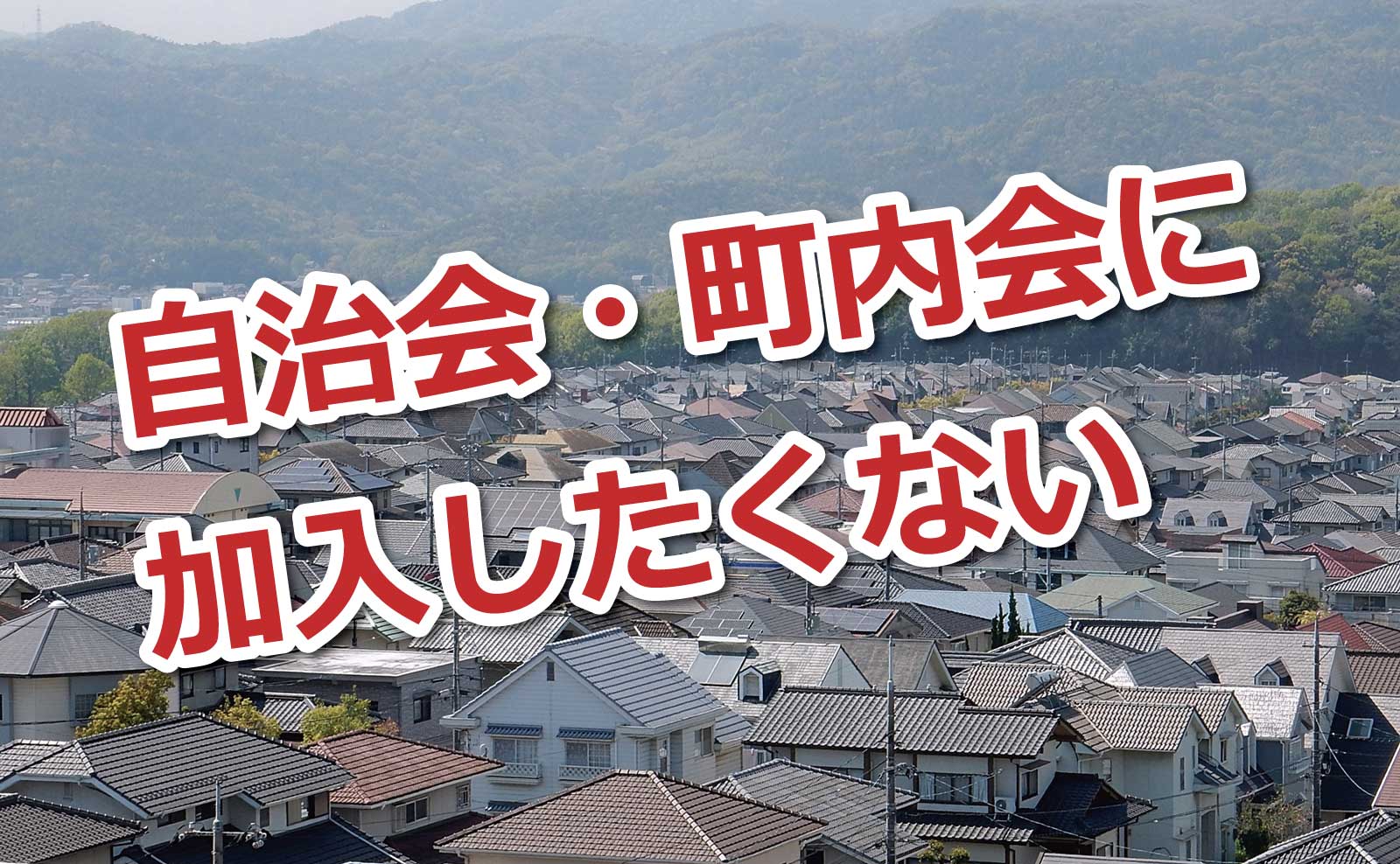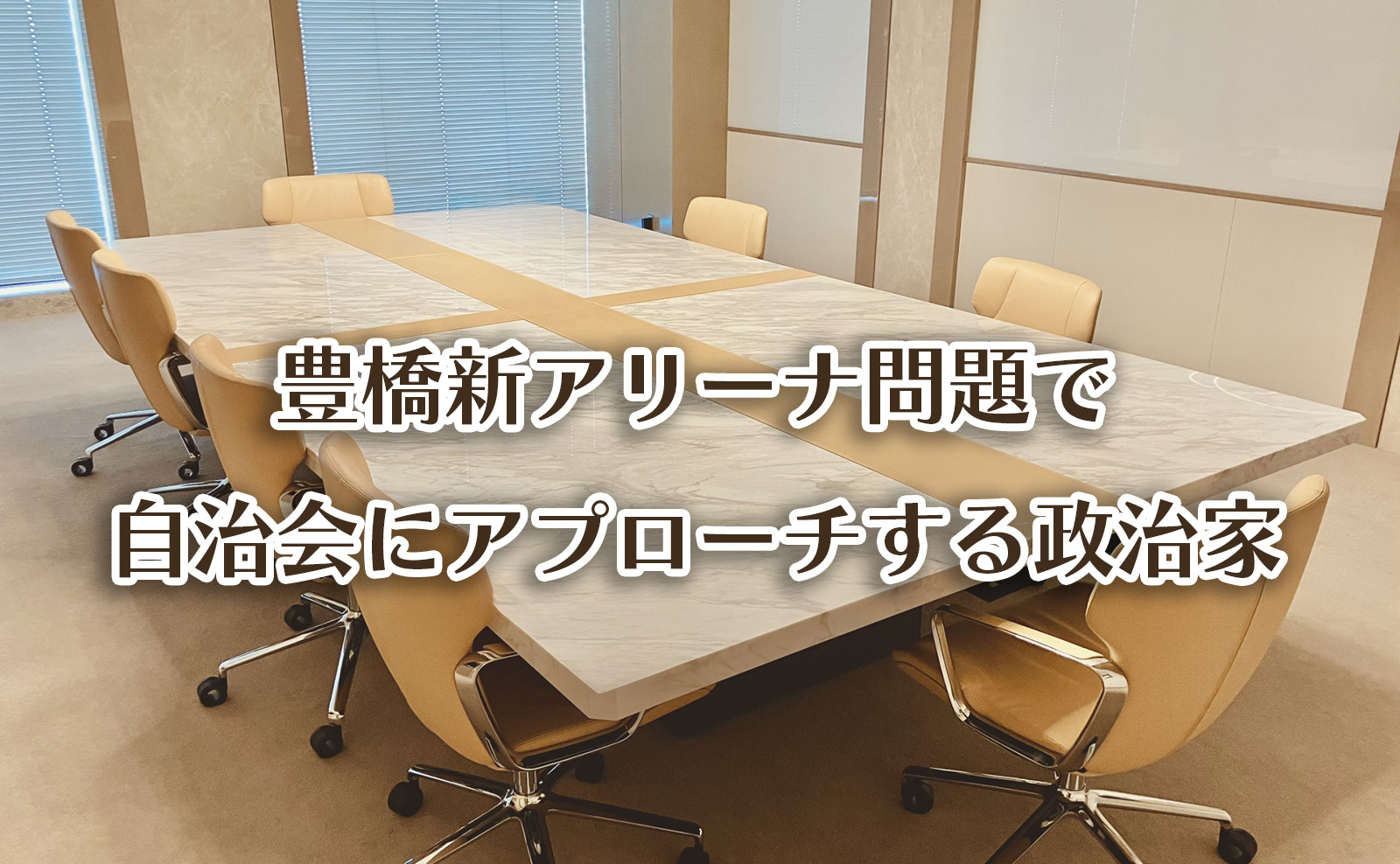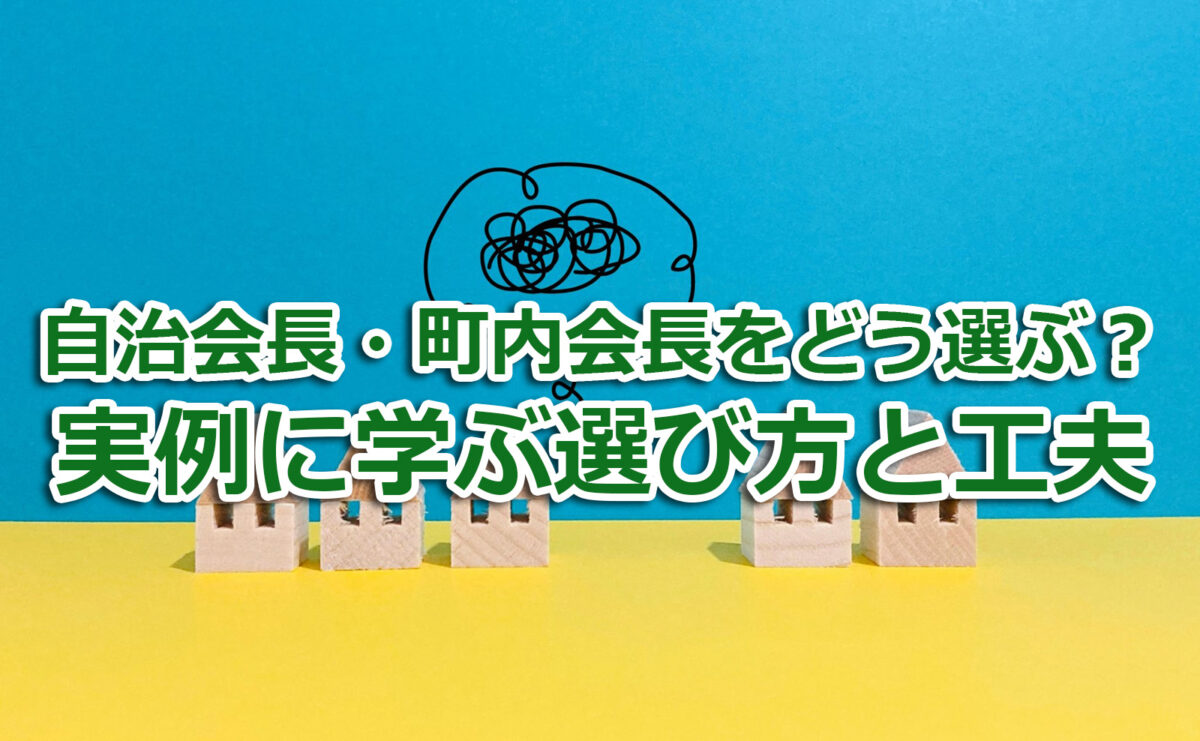
自治会や町内会の活動を支える中心的な役割が「会長」です。地域の行事、防災や防犯の取り組み、行政との窓口など、多岐にわたる仕事を担うため、地域にとっては欠かせない存在です。しかし、この重要な役割を「誰が務めるのか」を決める段階で、多くの地域が悩みを抱えています。というのも、会長の仕事量は決して軽くなく、責任も大きいため、「ぜひやりたい」と手を挙げる人が少ないのが現実だからです。
そのため、会長選びは「順番だから仕方ない」「断りにくいから受けざるを得ない」といった消極的な理由で決まるケースが少なくありません。公平さを保つために輪番制を採用している地域も多いですが、家庭や仕事の事情を無視して一方的に割り当てられると、本人や家族にとって大きな負担になります。中には、話し合いが深夜まで続いたり、押し切られるような形で承諾したりと、選出の場自体が住民にとってストレスになってしまうこともあります。
私自身も過去に2年間、自治会長を務めた経験があります。その中で、会長という立場の責任の重さや仕事の煩雑さを実感すると同時に、「どうすればもっと公平で、無理のない仕組みが作れるのか」という課題を強く感じました。今回は、その経験を踏まえて、自治会長・町内会長の選び方の現実と、少しでも負担やトラブルを減らすための工夫について紹介していきます。