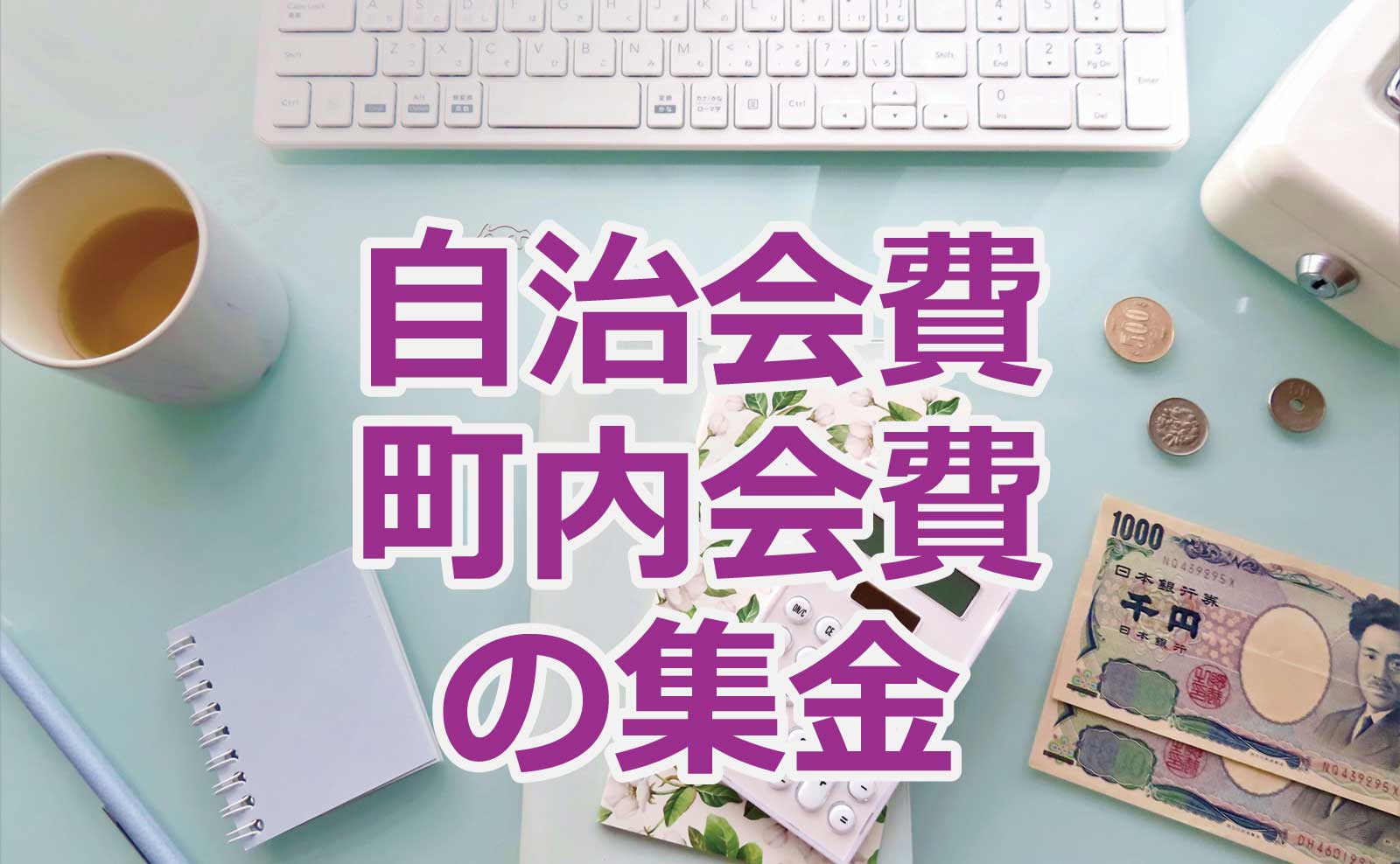はじめに
自治会長・町内会長という役職は、地域を支える大切な存在です。住民にとって最も身近なリーダーであり、行政からの情報を伝えたり、地域の安全を守る活動を推進したりと、多岐にわたる役割を担っています。しかし実際には「どんな仕事をするのか分からない」「負担が大きくて不安」という声も少なくありません。特に、初めて引き受ける方にとっては業務内容が見えにくく、戸惑いやプレッシャーを感じる場面が多いでしょう。また、地域によって役割の範囲や活動の規模が異なるため、「うちの町内会では何をすればいいのか」と迷うケースもあります。
こうした不安や疑問を解消するためには、自治会長・町内会長の仕事や役割を体系的に理解することが欠かせません。本記事では、基本的な役割から具体的な仕事内容、年間の流れ、そして実際に起こりやすいトラブルとその対策までを網羅的に解説します。単なる「義務」としてではなく、地域に暮らす人々をつなぐ「調整役」「共創のリーダー」としての視点を持つことが大切です。この記事を通じて、これから役職を担う方が安心してスタートできるように、また現役の会長がより効率的に活動できるように役立つヒントを提供していきます。