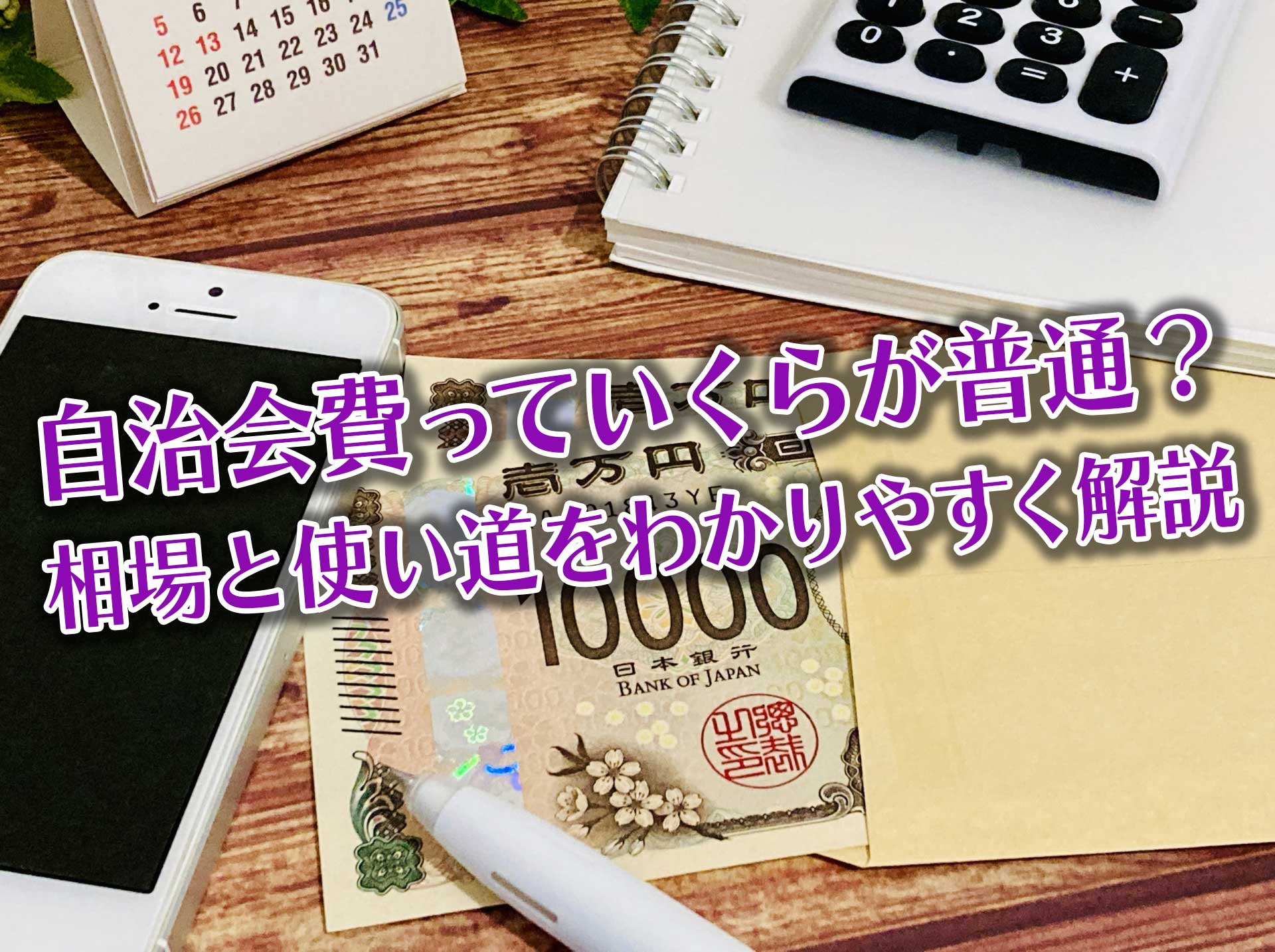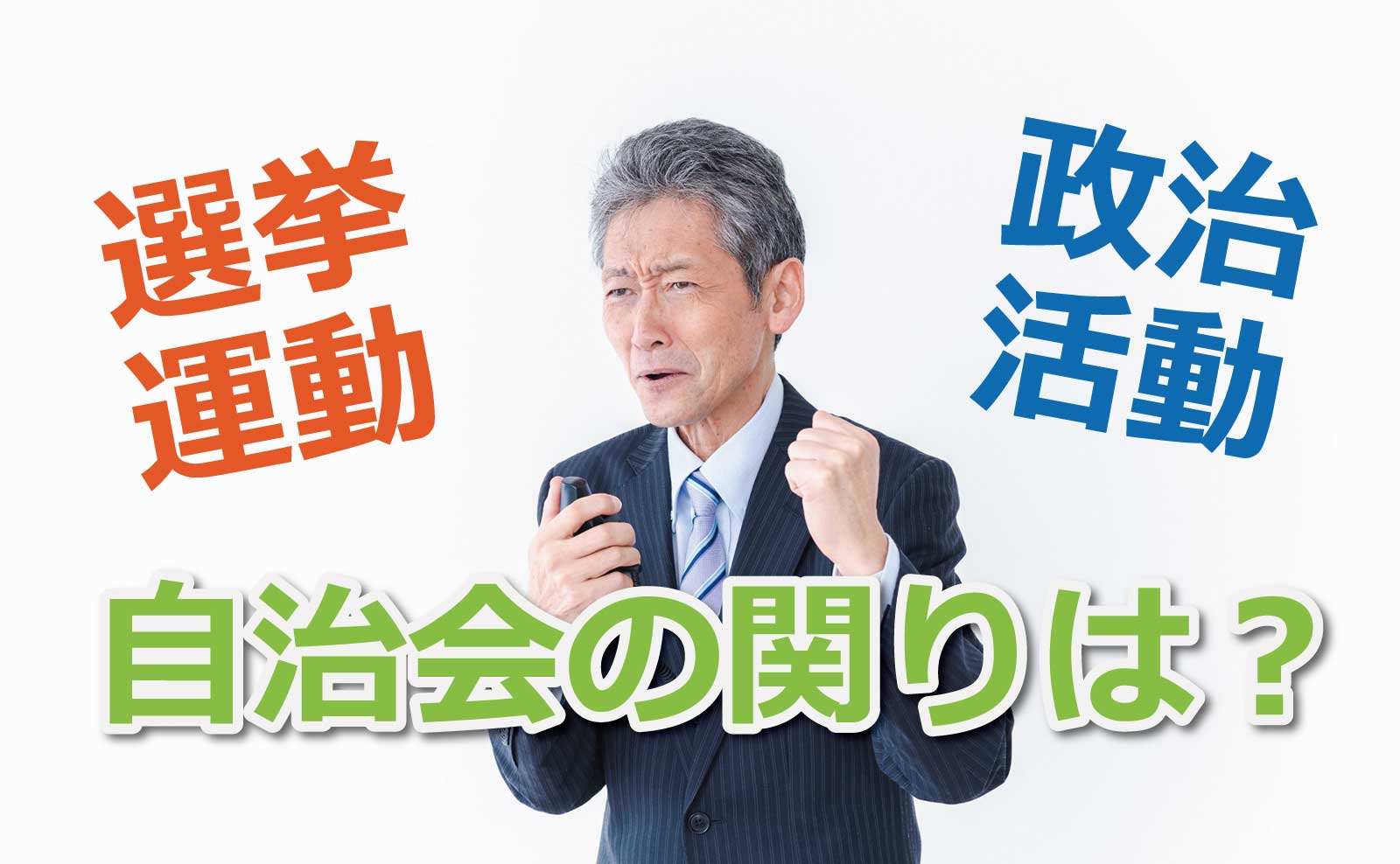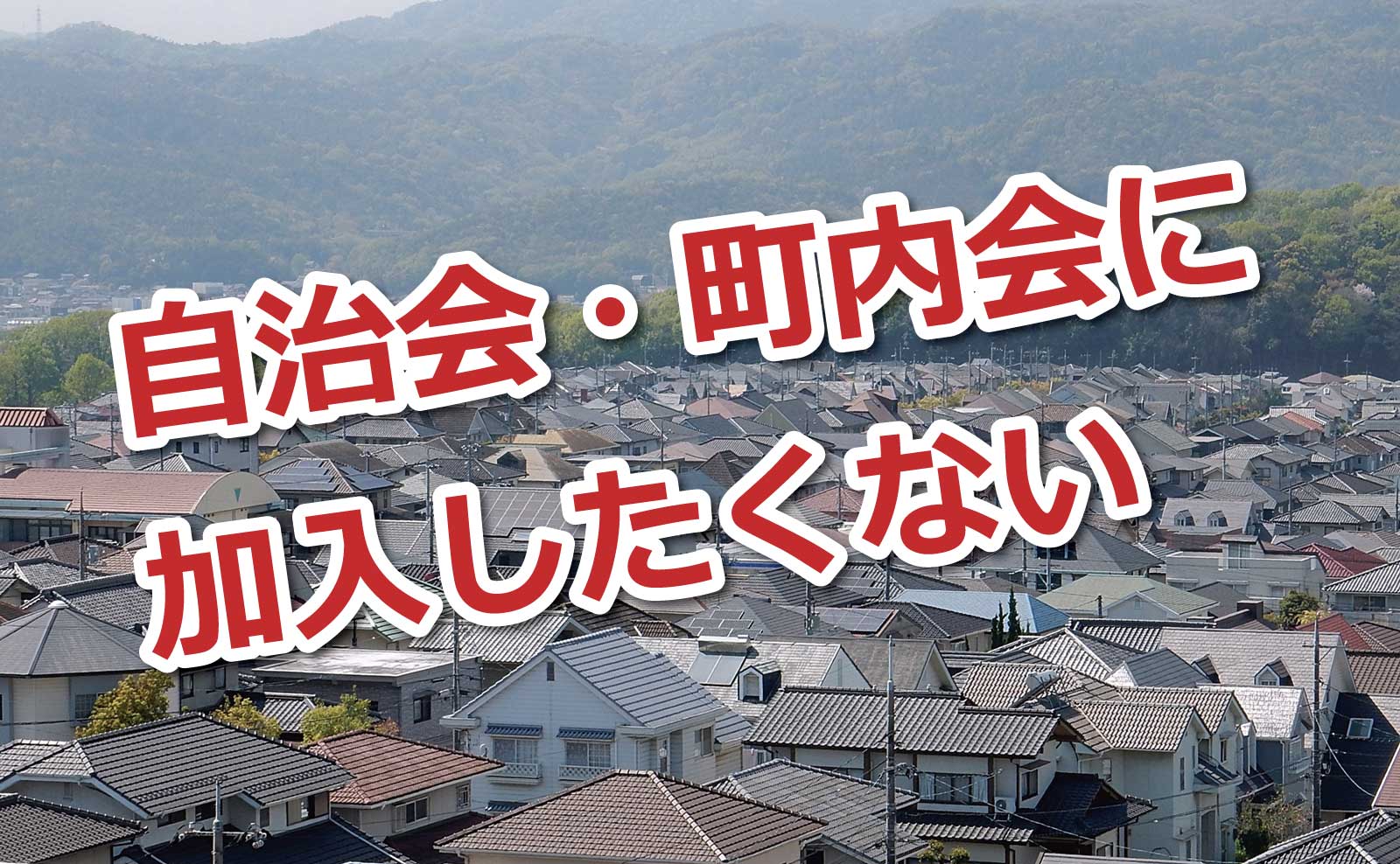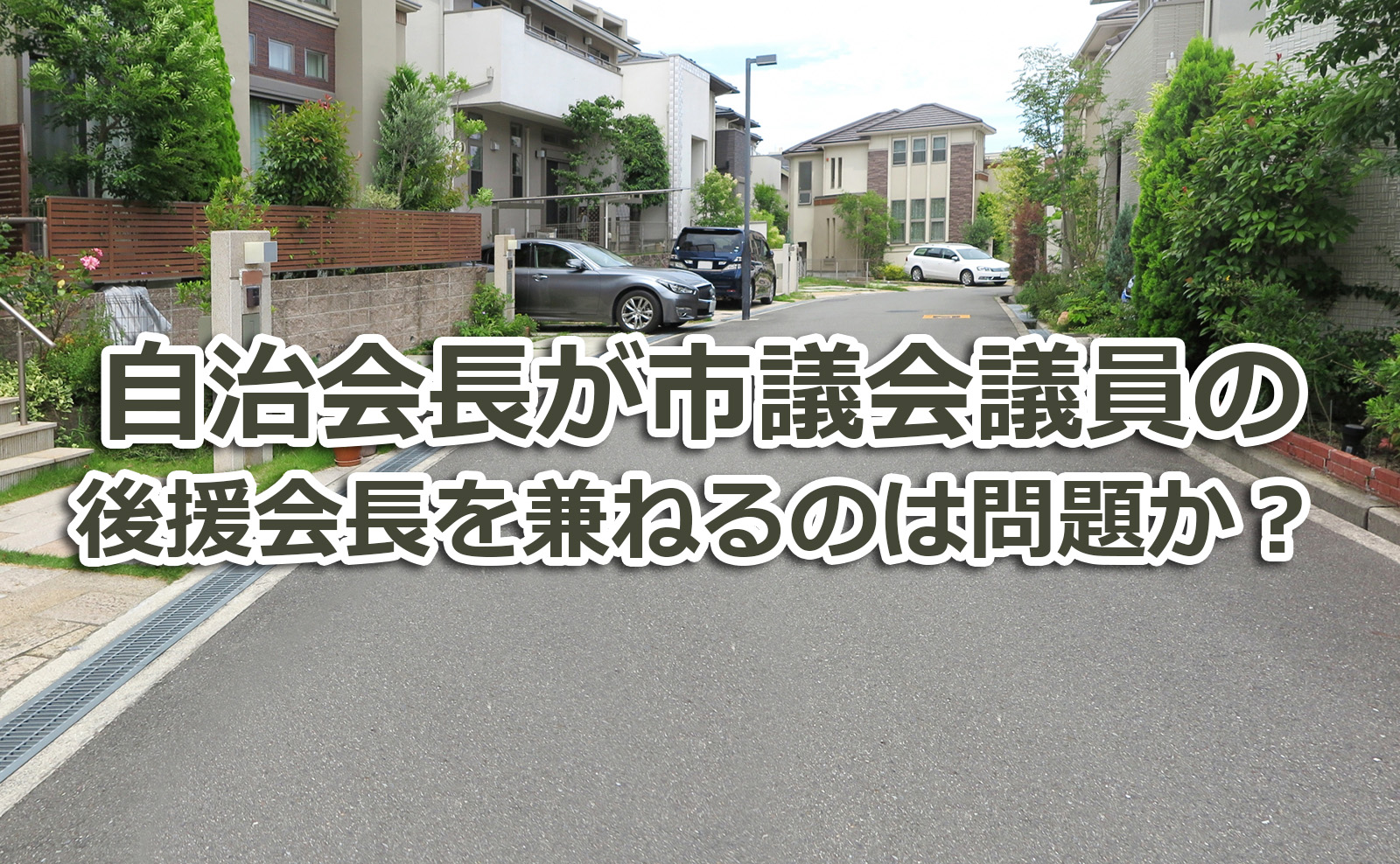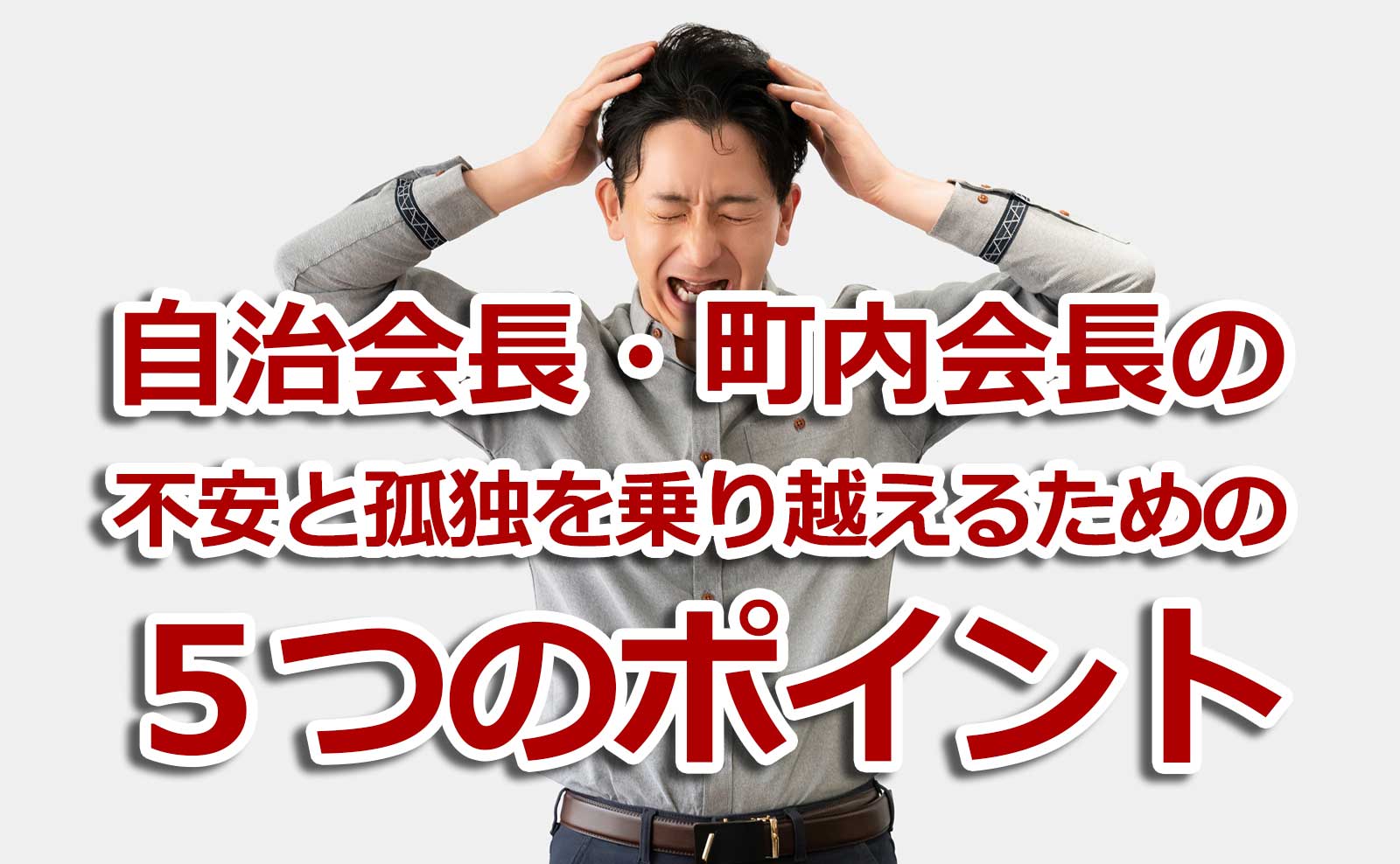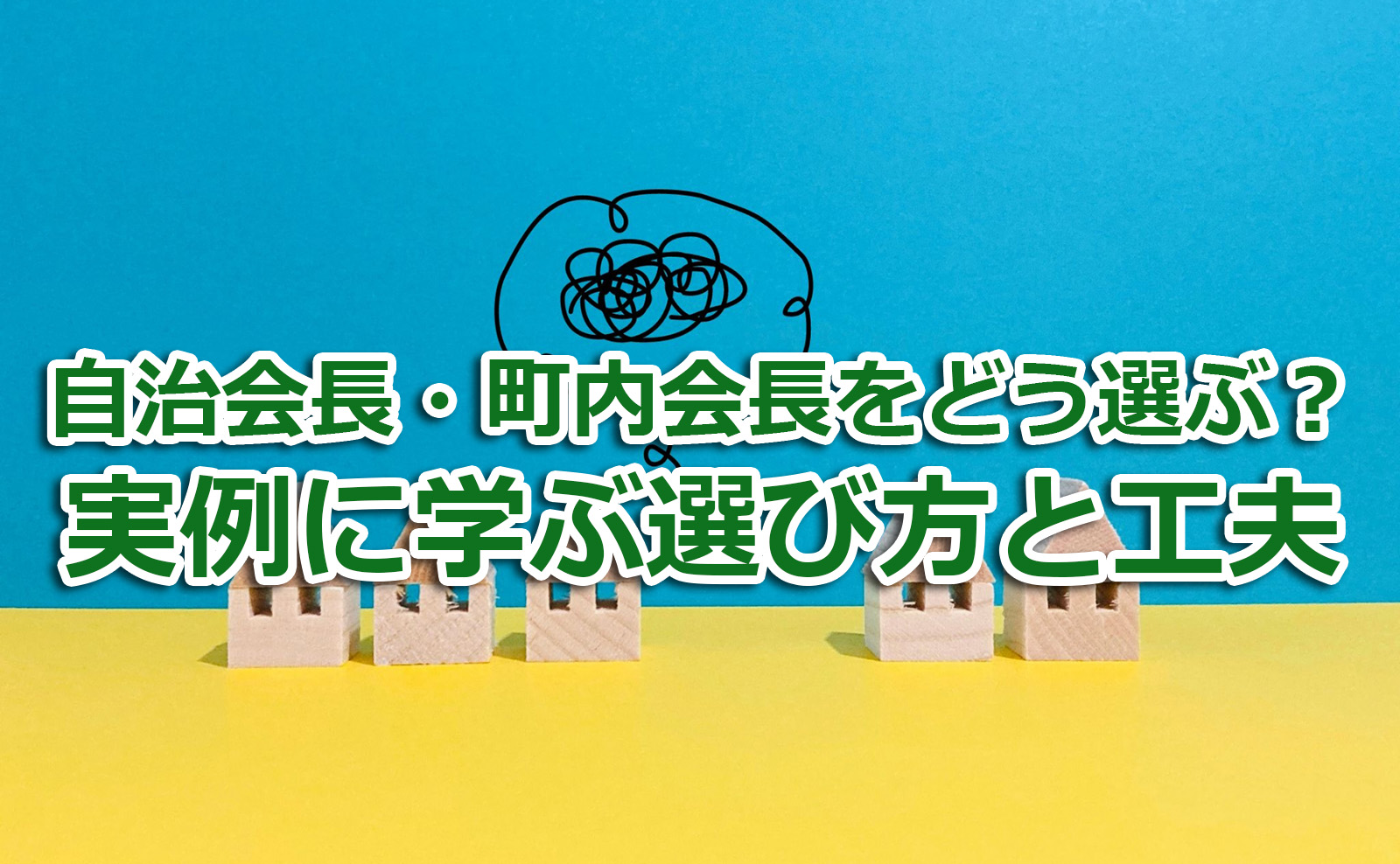近年、街中から公共のごみ箱が減少する一方で、ポイ捨てや散乱ごみの問題が各地で深刻化しています。安全対策や維持管理費用を理由に撤去が進んだ背景がありますが、その結果として、地域住民や自治会が日常的にごみ問題に直面せざるを得ない状況が生まれています。
奈良公園では「シカの誤食問題」が象徴的です。ごみ箱を撤去して40年近く「ごみは持ち帰る」方針を貫いてきましたが、観光客増加とともにポイ捨てが目立ち、死後にプラスチックごみが見つかるシカも多いと報告されています。こうした現実を前に、2024年にはついにスマートごみ箱が試験導入されました。これは、理想と現実のはざまで苦悩する自治体の姿を示しています。
一方、豊橋市発祥の「530運動」は、「自分のごみは自分で持ち帰る」というシンプルで普遍的な精神を広げ、市民一体で街を美しく保つ文化を築いてきました。清掃活動の実践だけでなく、ごみを減らす啓発活動へと発展し、今も続いています。この運動は、地域社会におけるモラルや責任意識を育む象徴的な取り組みです。
しかし現場を預かる自治会にとって、ごみ問題は理念だけでは解決できません。集会所や公園のごみ箱をどうするのか、イベント後の清掃を誰が担うのか、家庭ごみの持ち込みをどう防ぐのか。負担は結局「誰がするのか」という問いに集約されます。行政か、住民か、事業者か。それとも費用を分担する新たな仕組みを模索すべきか。
公共空間のごみ問題は、自治会にとって「地域をどう守り、どう持続させるか」という根幹の課題です。きれいな街を維持するために、今こそ自治会が中心となって議論し、行政や市民、企業との連携の在り方を考える必要があるのではないでしょうか。