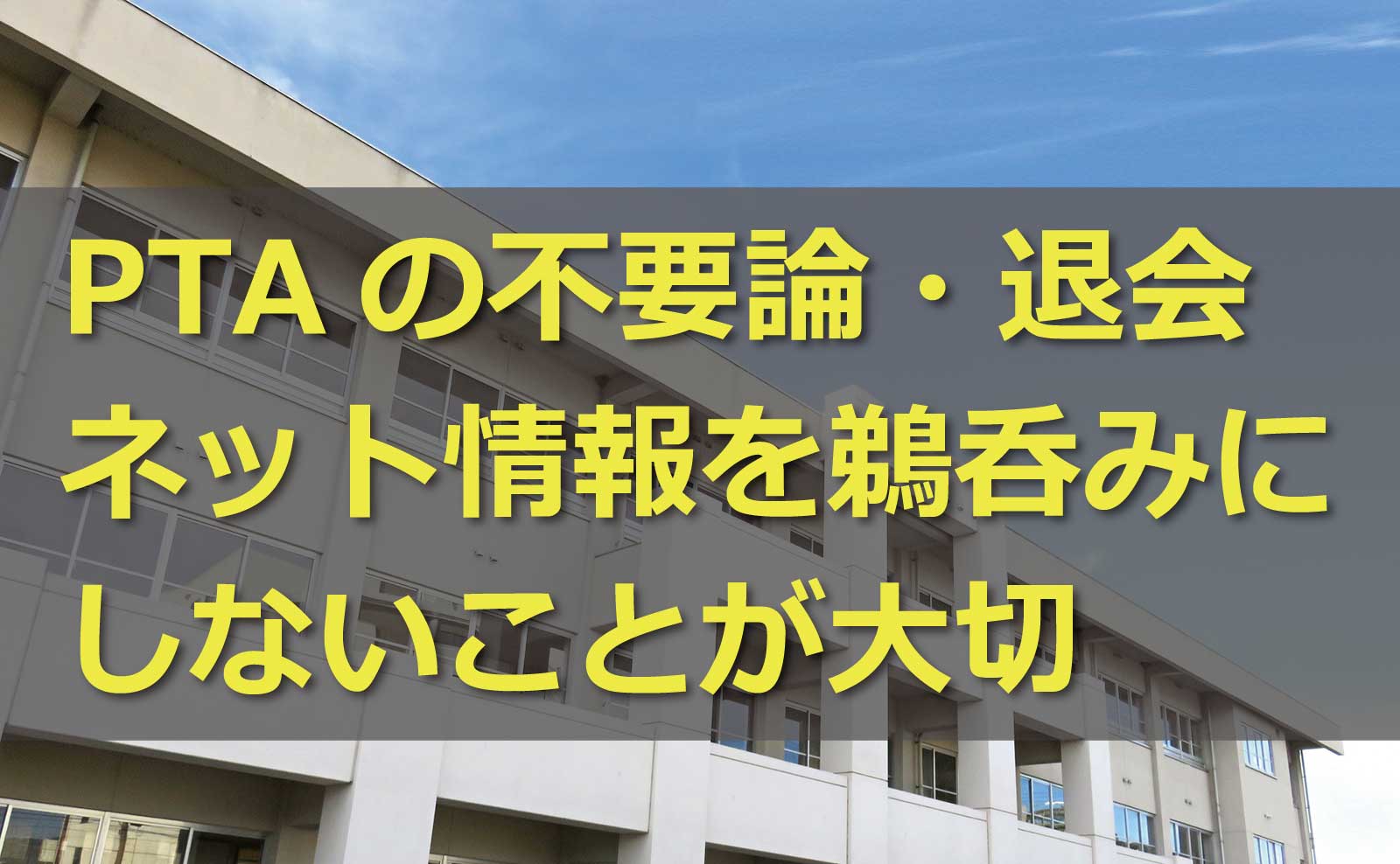はじめに
新年度ですね。今週は全国各地の小中学校で入学式が行われました。晴れて入学式を迎えられたお子さんを前に親御さんにはあるお悩みがあるのではないでしょうか?
それは「PTA」の問題です。
毎年のように新年度にはこのPTAの問題が新聞記事などで取り上げられます。記事では大抵「自動入会」の問題とか「委員の強制」などといった問題について実際の保護者の意見を取材しつつまとめられています。

そしてこのPTAの問題は自治会や町内会の問題と共通する部分があります。自治会や町内会も地域に差はあれどその地域に引っ越してくると「自治会に加入しませんか?」と勧誘に来ます。きっぱり断ればいいのですがこれからのご近所づきあいを思えば断れなくて加入してしまうという方が多いのが現実です。
そして何年かすると「組長」「班長」「委員」などの役が回ってきます。
僕自身の話をすれば長男、長女が小中学生の時にPTA役員を7年務めそのうち2年はPTA会長を務めました。僕が「自営業であること」「シンパパで学校行事にはできるだけ出席していたため目立ってしまったこと」「断れない性格だったこと」からPTA役員を務めることとなってしまいました。そしてやはり同様に自治会長もお願いされて断り切れず2年間務めました。
僕もこれまでに、PTAの役員を7年、うち会長を2年、さらに自治会長も2年務めてきました。だからこそ分かるのですが、「PTAも自治会も、決して無意味な存在ではない」と思っています。子どもたちのため、地域の安全のため、誰かが動かなければ成り立たない活動が、そこには確かにあります。
しかし一方で、「自動的に入会させられる」「役員が強制的に回ってくる」という仕組みには、やはり大きな問題があるとも感じています。任意団体であるはずなのに、辞退しづらい空気や暗黙の了解のもと、半ば強制的に関わらされる。それは果たして健全な参加と言えるのでしょうか?
しかも今は、共働き世帯が当たり前になり、子育てや介護、仕事に追われて時間に余裕のない人が多い時代です。「誰もが同じように関われる」という前提自体が、もう時代に合っていないのではないか。そんな疑問を、現場にいて何度も感じてきました。
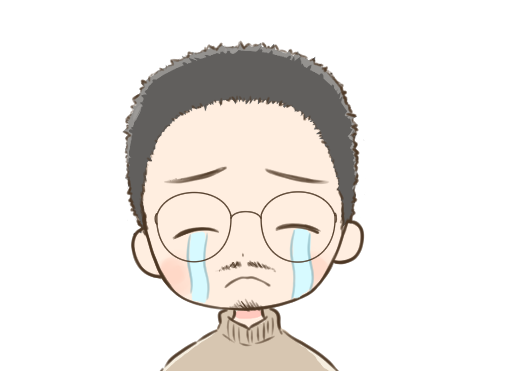 サイト管理人
サイト管理人こうした仕組みのままで本当にいいのか? もしこのまま何も変えなければ、PTAや自治会の担い手はますます減り、機能不全に陥ってしまうかもしれません。
「じゃあ、どうしたらいいの?」という問いに、僕自身の経験を交えて考えてみたいと思います。
PTAや自治会、町内会の入会の問題点
PTAや自治会・町内会は、本来「任意団体」です。つまり、加入するかどうかは個人の自由であり、強制されるものではありません。しかし現実には、「入学したら自動的にPTA会員」「引っ越してきたら自治会に入って当然」という空気が根強く残っており、多くの人が疑問や違和感を抱きながらも「なんとなく」加入しています。この自動入会の前提が、組織に対する不信感を生んでいる原因のひとつです。
さらに問題なのは、入会を断ったり退会したりすることの難しさです。実際に「やめたい」と申し出ようとしても、「空気を乱す人」「地域に協力しない人」と見られてしまうのではないかと不安になり、言い出せない人が大勢います。結果として、「本当は参加したくないけど、言えないから続けている」という構図ができあがり、活動へのモチベーションも低くなってしまいます。
また、会員になることで会費を支払ったり、名簿に個人情報を登録したり、行事への参加を求められたりと、思った以上に負担が生じることもあります。プライバシーの観点から見ても、名簿管理やLINEグループでのやり取りに抵抗を感じる人は少なくありません。本来は「地域や学校を良くしたい」という想いで成り立つべき組織が、「やらされ感」や不信を招く存在になってしまうのは、非常にもったいないことです。
役員や委員が「回ってくる」ことの問題
PTAや自治会では、役員や委員の担当が「順番で回ってくる」ことが一般的です。しかし、多くの人が本音では「できればやりたくない」と感じています。それでも毎年、誰かが引き受けざるを得ない状況が続いています。その背景には、「誰かがやらなければ活動が止まってしまう」というプレッシャーや、「やらない人ばかりでは不公平」という意識があるのかもしれません。
実際に役員や委員を引き受けてみると、その負担の大きさに驚かされます。資料の作成、会議への出席、イベントの準備など、平日の夜や休日に時間を取られることも多く、仕事や家庭との両立が難しいと感じる人も少なくありません。特に共働き家庭やシングル世帯にとっては、ただの「地域貢献」では済まされない現実的な負担です。
その結果、「やった人だけが苦労する」「何もしない人が得をしている」という不公平感が生まれてしまいます。本来、地域や学校のために行うはずの活動が、苦痛や不満の種になってしまうのは本末転倒です。この強制的に回ってくる仕組みこそが、組織の持続可能性を脅かす原因になっているのではないでしょうか。負担の分散や選択肢のある関わり方が求められています。


それでもPTAや自治会、町内会が必要だと思う理由
近年、地域のつながりはどんどん希薄になりつつあります。顔を知らないご近所さん、子どもたちだけで遊ぶことへの不安、助け合いのない空気、そうした時代だからこそ、PTAや自治会のような組織の存在は、むしろこれからの社会に必要だと感じています。特に子どもを取り巻く環境は、地域全体で見守る仕組みがなければ安全を保つのが難しくなっているのが現実です。
また、地震や台風などの自然災害が頻発する日本において、地域内の助け合いや情報共有、防災体制の構築は重要です。自治会の防災訓練や安否確認体制、PTAによる登下校見守り活動などは、いざという時に大きな力になります。こうした活動は、普段は目立ちにくいですが、有事の際に“やっておいてよかった”と思えるものです。
私自身も、役員を経験して「大変だったけど、やってよかった」と思える瞬間が何度もありました。運動会の準備で汗を流した時、地域の清掃活動で子どもと一緒に動いた時、感謝の言葉をもらった時、人と人との距離がぐっと縮まり、「地域って悪くないな」と実感しました。強制でなく、関わる中で得られるものの価値を、もっと多くの人に知ってほしいと感じています。
ではどうしたらいいのか?
まず取り組むべきは、「自動入会」という仕組みを見直すことです。PTAも自治会も、任意団体である以上、参加の自由と選択を前提とすべきです。ただし、単に「自由ですよ」と言うだけでは人は集まりません。何のために存在し、どんな役割があるのかを丁寧に伝える工夫が求められます。強制でなく納得して参加する人を増やすことが、持続可能な組織運営への第一歩です。
そのうえで、役員や委員のなり手不足には報酬や謝礼の導入、作業の分担やマニュアル化による簡略化も有効です。また、PTAと自治会がそれぞれで行っているような防犯パトロールや見守り、行事の準備などは、実は重複している部分も少なくありません。こうした活動を連携・統合し、地域ぐるみで子どもと暮らしを守る仕組みとして、PTAと自治会をハイブリッド化する発想も今後の選択肢になるのではないでしょうか。
さらに、回覧板や連絡帳、出欠確認などは、LINEやアプリなどのデジタルツールを導入することで、大きく負担を減らすことができます。役割の割り振りも、定年後で時間に余裕のある世代と、子育て真っ最中の世代とで柔軟に分担すれば、それぞれの無理のない関わり方が可能になります。これからの地域活動は、「誰もが平等にやる」から、「できる人が、できる時に、できる範囲で」に変えていく必要があるのかもしれません。
これからのPTA、自治会、町内会の在り方
PTAや自治会を「もういらない」「なくしてしまえ」という声があるのも理解できます。ですが、私自身の経験を通じて感じるのは、それらの組織が担ってきた役割には、まだまだ大きな価値があるということです。問題なのは、そのあり方です。今、私たちが向き合うべきなのは、「やめるか残すか」ではなく、「どう変えていくか」ではないでしょうか。
あなたの地域では、どんな課題がありますか? 今のPTAや自治会に、参加しづらさや負担の重さを感じている人はいませんか? もしかしたら、あなたの気づきが、変化の第一歩になるかもしれません。「誰かがやってくれるだろう」と待つのではなく、自分自身がその“誰か”になる勇気こそ、地域をより良くするために必要なのだと思います。



そして今こそ、新しい形の地域活動をけん引してくれる人材が求められています。従来のやり方にとらわれず、デジタルや外注も活用しながら、時代に合った柔軟な運営を模索できる人。その先頭に立つのは、何も特別なスキルや肩書を持った人ではありません。地域を思う気持ちと、「なんとかしたい」という想いがあれば十分です。次の時代のPTA・自治会を、共につくっていきませんか?