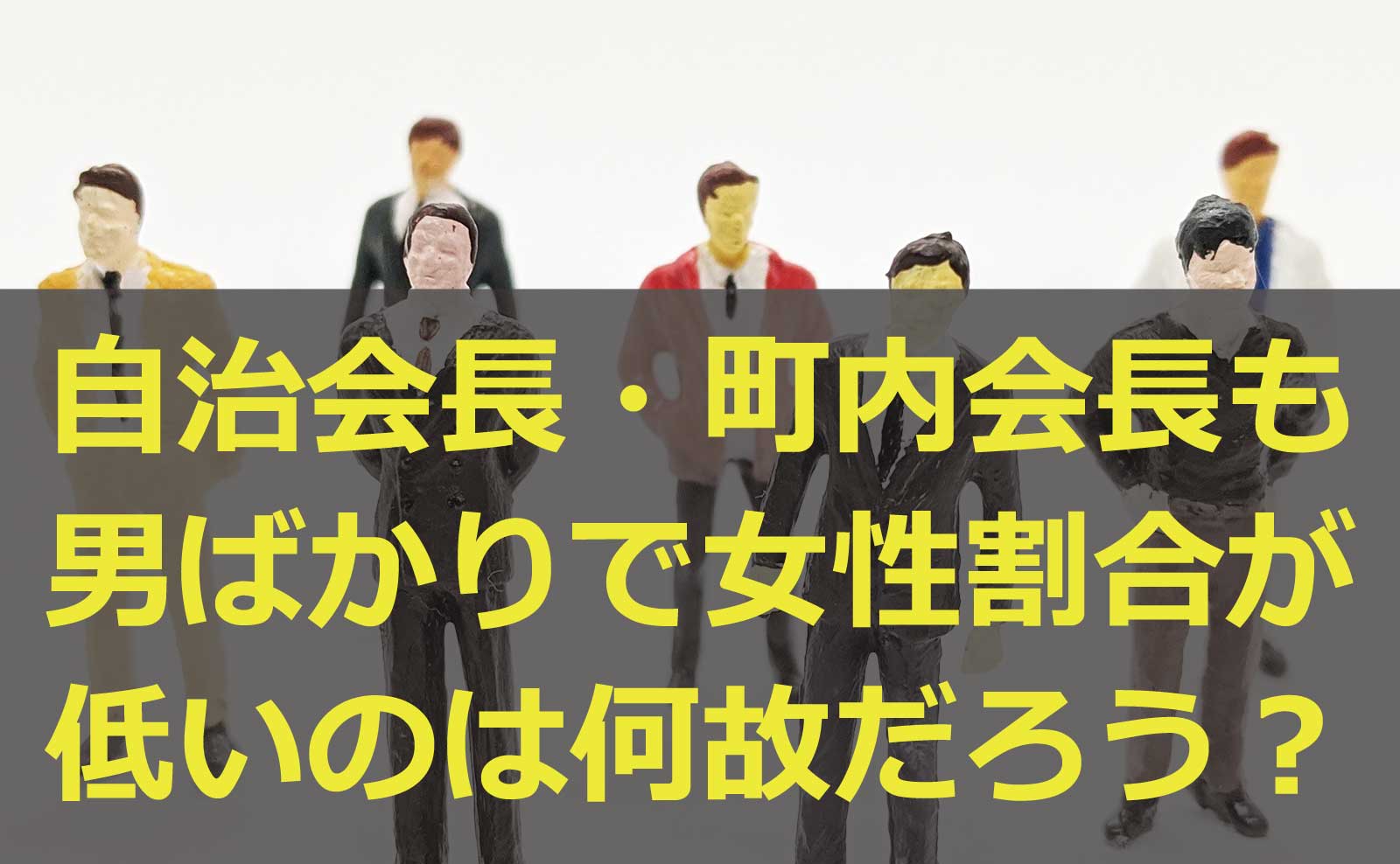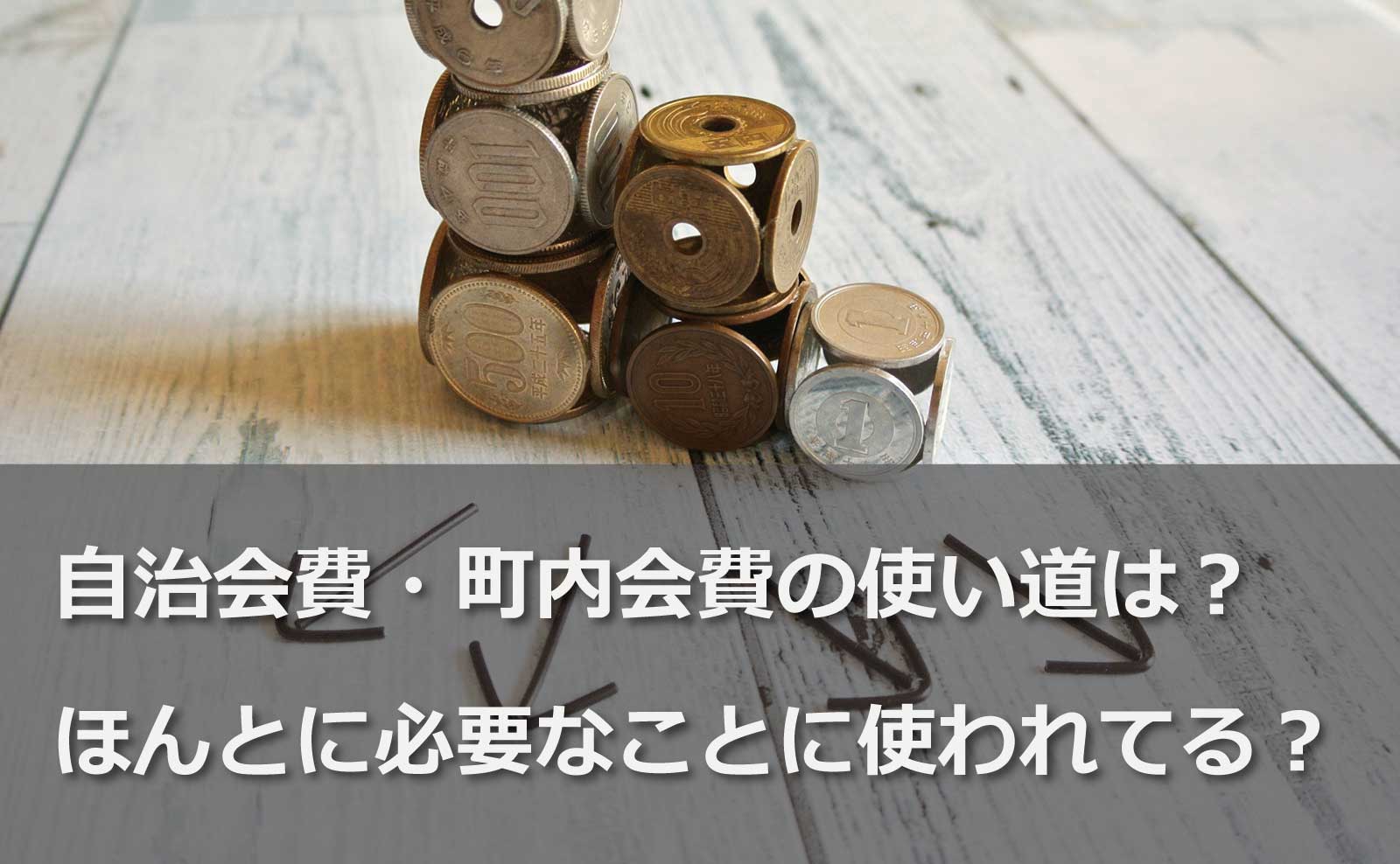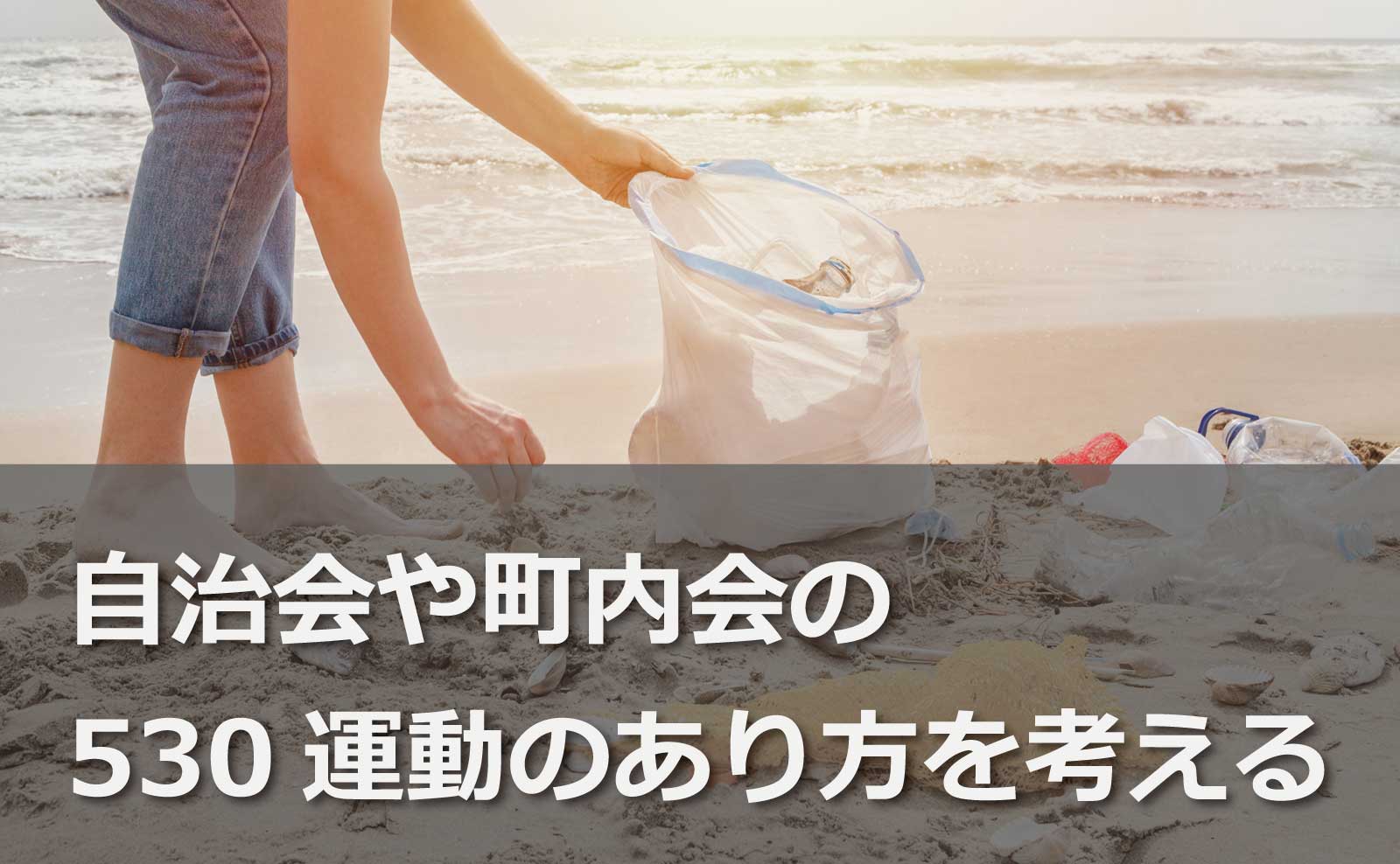新年度、突然の役目に戸惑うあなたへ

えっ、自分が自治会長!?
新年度、そんなふうに困惑している方も多いのではないでしょうか。かく言う私も、まさに「頼まれてしまった側」でした。
2021年の年末、当時の自治会長と「住みよいまちづくりの会」の会長が、突然我が家を訪ねてきました。そして開口一番、「来年度、自治会長を引き受けてもらえないか」とお願いされたのです。翌年度僕は組長が回ってくる年だったのですが、僕が所属しているのは第3ブロック。本来であれば、翌年度の自治会長は第4ブロックから選出されるはずでした。順番としては「うちじゃない」はずだったのです。ですが、なり手が見つからず、「何とかお願いできないか」と頭を下げられました。
加えて、当時は新型コロナウイルスの影響で、地域の活動が3年ほど停滞していた時期。前年度の活動もほとんど行われておらず、引き継ぎ資料や実務的な情報もまったく整っていませんでした。それでも「誰かがやらなければ」と腹をくくり、私は2022年4月から自治会長を務めることにしました。
当初は1年間のつもりでしたが、いざ動き出すと、活動の仕組みや役割分担など、見直さなければならないことが山積みであることに気づきます。結果的に、もう1年延長し、2024年3月までの2年間、自治会長を続けることになりました。
今思えば、最初の頃は「何をすればいいのかわからない」「自分にできるのか」と不安でいっぱいでした。でも、試行錯誤しながらもなんとか1年、そして2年とやり切ることができました。



そんな僕がその2年間で感じたこと、学んだこと、そして「こうしておけばラクになる」という実践的なヒントをまとめています。これから1年間、自治会長・町内会長を務めることになったあなたが、少しでも気楽な気持ちで取り組めるように、背中を押せたら嬉しいです。
まず押さえておきたい基本姿勢・心構え
自治会長になったばかりの頃は、「何をどうすればいいのか分からない」「とにかく全部きちんとやらなきゃ」と気が張ってしまうものです。でも、はっきり言います。完璧を目指す必要はありません。7割で十分です。
地域の活動は、正解が決まっているものばかりではありませんし、全員が満足する結果を出すのも難しいのが現実です。むしろ「完璧を目指しすぎて自分が疲れてしまう」ほうが問題です。ある程度の割り切りや適当さも必要なんです。やってみて「これでいいのかな」と思うくらいがちょうどいい、ということを私は2年間で実感しました。
次に大事なのは、一人で抱え込まないこと。自治会長になると、どうしても「自分が全部やらなきゃ」という気持ちになりますが、それでは持ちません。相談できる相手を見つけて、意見を聞いたり、場合によっては仕事を丸投げすることも必要です。副会長や班長、過去の役員経験者など、周囲には頼れる人が必ずいます。「助けて」と声を出せるのは弱さではなく、自治会運営に必要な力です。
そして、自分の生活や仕事を何より優先してください。自治会の仕事は大切ですが、あくまでボランティアです。日々の暮らしや本業に支障が出るほど頑張ってしまうと、心身がもちません。「今日は疲れてるから会議資料は明日でいいや」「今週は無理だから、行事は誰かに任せよう」くらいの気持ちでいいんです。
さらに、よく耳にする「去年こうだったから」「昔からこう決まってる」という言葉。これも大事ですが、「前例に縛られすぎない」柔軟さも必要です。状況は年々変わっていきますし、コロナ禍を経た今は特に、以前のやり方がそのまま通用しないことも多いです。必要がないことは思い切って削る、形を変える、オンラインやデジタルツールを使って効率化する—そうした判断ができるのは、今のあなたならではの役割です。
自治会というと「堅苦しい」「面倒くさい」というイメージがつきまといがちですが、実は地域のために頑張る人が、ゆるやかにつながる場でもあります。気負いすぎず、無理しすぎず、自分なりのやり方で取り組めば、きっと周りもそれを受け入れてくれます。肩の力を抜いて、深呼吸。まずは、できることから一歩ずつ始めていきましょう。
- 完璧を目指さず7割でOK
- 一人で抱え込まず、頼ることも大切
- 自分の生活・仕事を優先して無理しない
- 前例にとらわれず柔軟に考える
- 地域は“ゆるやかにつながる場”と考え、気楽に取り組もう
年間スケジュールをざっくり把握するだけでラクになる
自治会長になって最初にやっておきたいのが、年間スケジュールの全体像を把握することです。細かいことまでは分からなくても構いません。春には総会、夏には夏祭りや環境美化活動、秋には防災訓練や敬老会、冬は歳末警戒や会計報告など、地域によっておおよその「恒例行事」があります。それをざっくりとでも把握しておくだけで、心の準備ができ、いざというときに慌てずに済みます。
おすすめなのは、カレンダーやスケジュール帳に行事を書き込んでおくことです。私の場合は、Googleカレンダーに行事を登録し、通知が来るように設定していました。そうすることで、「来月のイベント、そろそろ準備しなきゃ」と先回りして動けるようになります。とにかく後手に回らないことが、精神的な余裕につながります。
さらに大事なのが、「今年はやらなくてもいい行事」がないかを見極めることです。すべてを前年通りにやる必要はありません。そもそもその行事に参加者が少ない、準備が大変な割に反応が薄い、開催する意味があいまい—そんな行事は、思い切って中止や縮小、もしくは簡素化する判断もアリです。
自治会の行事は「やらなければいけない」ものではなく、「地域のためになるからやる」もの。必要なものと、そうでないものを分けて考えることができると、負担はぐっと減ります。そしてその判断ができるのは、今の自治会長であるあなただけです。
全体を俯瞰し、先を見て動くこと。それだけで、日々のストレスが大きく減ります。まずは一度、前年度の資料を参考にしながら、ざっくりと1年の流れを把握してみてください。それが「なんとかなる自治会運営」への第一歩です。
- 年間行事をざっくり把握し心の準備を
- カレンダーに予定を書き先手を打つ
- 不要な行事は思い切って見直す勇気も大切
会議・打ち合わせをうまく回すコツ
自治会や町内会に会議はつきものです。会議をいかにスムーズに行うことができるかがスムーズな自治会運営のカギとも言えます。
会議は短く、議題を絞って
自治会の会議は、長くなればなるほど参加者の集中力が切れ、建設的な意見も出にくくなります。議題は多くても3つ程度に絞り、資料も簡潔に。必要以上に説明を加えず、要点だけを伝えるようにするとスムーズです。会議の目的は「話すこと」より「決めること」。短時間で終わる会議ほど評価されます。
議事録はテンプレ活用でOK
会議後の議事録作成は地味に大変ですが、形式にこだわる必要はありません。役所や前年度の議事録を参考に、自分用のテンプレートを作っておくと効率的です。日時・出席者・議題・決定事項の4点があれば十分。メールやLINEで共有するだけでも、立派な記録になります。気負わずシンプルにまとめましょう。
「沈黙」に耐える~発言を無理に引き出さなくていい
会議中、意見を聞いても誰も発言しない場面があります。でも、沈黙が悪いわけではありません。無理に「何か意見ありませんか?」と促すより、「ではそのように進めます」とまとめた方がスムーズです。発言が少ないのは「異論がない証拠」と考えてOK。沈黙に耐えるのも会議運営の大事な技術です。
文句を言う人ほど手伝わない…と割り切る
会議では何かと不満や文句を言う人が現れがちですが、そういう人ほど実際の作業は手伝ってくれません。真面目に取り合うと疲れるだけなので、「はいはい」と聞き流すくらいの気持ちでOK。建設的な意見だけ拾い、否定ではなく“スルー”する姿勢が自分を守ります。割り切ることで気が楽になりますよ。
苦情・トラブル対応はこう乗り切れ!
自治会長をしていると、近隣トラブルや苦情の相談を受けることがあります。でも、そこで大切なのは「聞くだけ聞く」「すぐには答えない」という姿勢です。相手は誰かに話を聞いてもらうだけで気が済むことも多く、無理に解決しようとする必要はありません。
また、すぐに動かなくてもいいケースがほとんどです。焦って対応すると、逆に話がこじれることもあります。判断に迷ったときは、役所や他の役員に相談し、決して一人で背負わないこと。自分ひとりでどうにかしようとせず、「共有」と「相談」を意識することが大切です。
さらに、やりとりはメールやLINEなど記録に残る方法で行うのが安心です。万一トラブルが大きくなっても、記録が残っていれば冷静に対応できます。苦情対応は「抱え込まない」「即断しない」「記録を残す」が基本。これだけでグッとラクになります。
仲間づくりは運営のカギ
自治会長の仕事を円滑に進めるためには、**「仲間づくり」**が何よりも大切です。すべてを一人で抱え込むのは無理があります。だからこそ、副会長や書記、班長などの役員を“味方”につけることが、自治会運営の成否を大きく左右します。
人によって得意なことやできる範囲は違います。細かい作業が得意な人もいれば、人とのつながりを大切にしている人、昔から地域の事情に詳しい人もいます。そうした人たちの力を借りることで、自治会の活動はぐっと楽になります。
また、自治会活動は世代を超えた交流ができる貴重な場でもあります。普段は話す機会のないご近所の高齢者や若い世代の方と関わることで、新しい視点や知恵が得られたり、自分の地域をより深く知るきっかけにもなります。「自治会って案外面白いかも」と思える瞬間がきっとあるはずです。
そして、忘れてはいけないのが「ありがとう」の一言。小さなことでも「助かりました」「ありがとうございます」と伝えるだけで、相手の気持ちは大きく変わります。感謝の気持ちを言葉にすることで、自然と協力関係が築かれていきます。
自治会運営は、一人でやるものではなく、みんなで少しずつ支え合って成り立つものです。仲間を信じ、任せ、感謝する。このシンプルな流れを大切にすれば、無理なく1年を乗り切ることができます。
さいごに:やってみて分かった「やってよかった」と思える瞬間
自治会長なんて、できればやりたくない。そう思っていた自分が、終わってみると「やってよかったな」と思える瞬間が、いくつもありました。
まず一番大きかったのは、地域の人に顔を覚えられることです。行事や会合の場で少しずつ声をかけられるようになり、通りすがりに挨拶される回数が増えました。これまで「近所だけど知らない人」だった方々と、自然に関係が築けるようになったのは、自治会長としての何よりの財産です。
また、誰かに「ありがとう」と言われた瞬間は、本当に報われる気持ちになります。掃除や配布物の手配、ちょっとした行事の段取りなど、自分では「たいしたことじゃない」と思っていたことにも、感謝の言葉をもらえる。たった一言でも、その重みは大きく、次の一歩を踏み出す勇気になります。
そして何より、あんなに不安でいっぱいだった自分が、1年なり2年なり、役目を果たしたという事実は、どこか誇らしい気持ちにさせてくれます。何も分からずに始めたのに、最後には「なんとかやれた」と思える。その経験は、これから先の人生でもきっと自信になります。
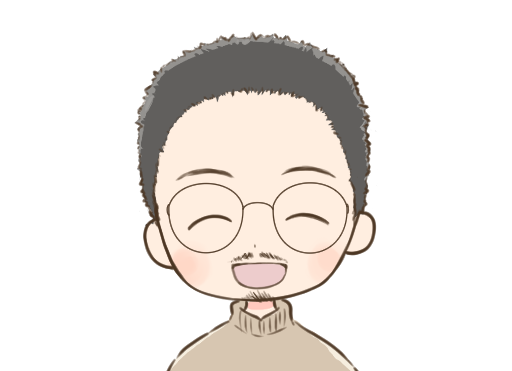
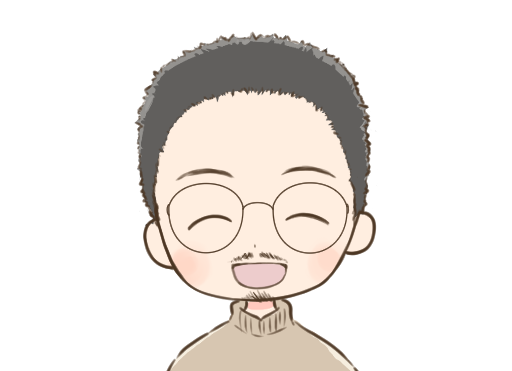
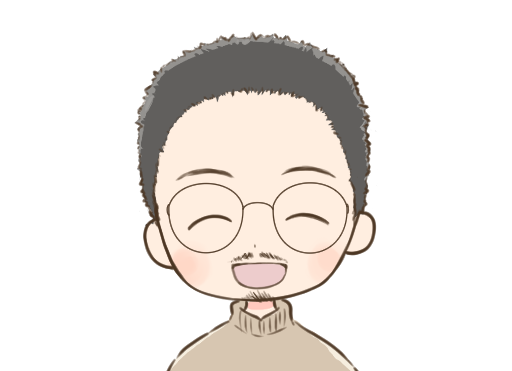
自治会長は、面倒なことも多いけれど、それ以上に得るものもある役目です。だからこそ、「やってよかった」と思える瞬間が、きっとあなたにも訪れるはずです。焦らず、無理せず、自分のペースで、1年間を歩んでくださいね。