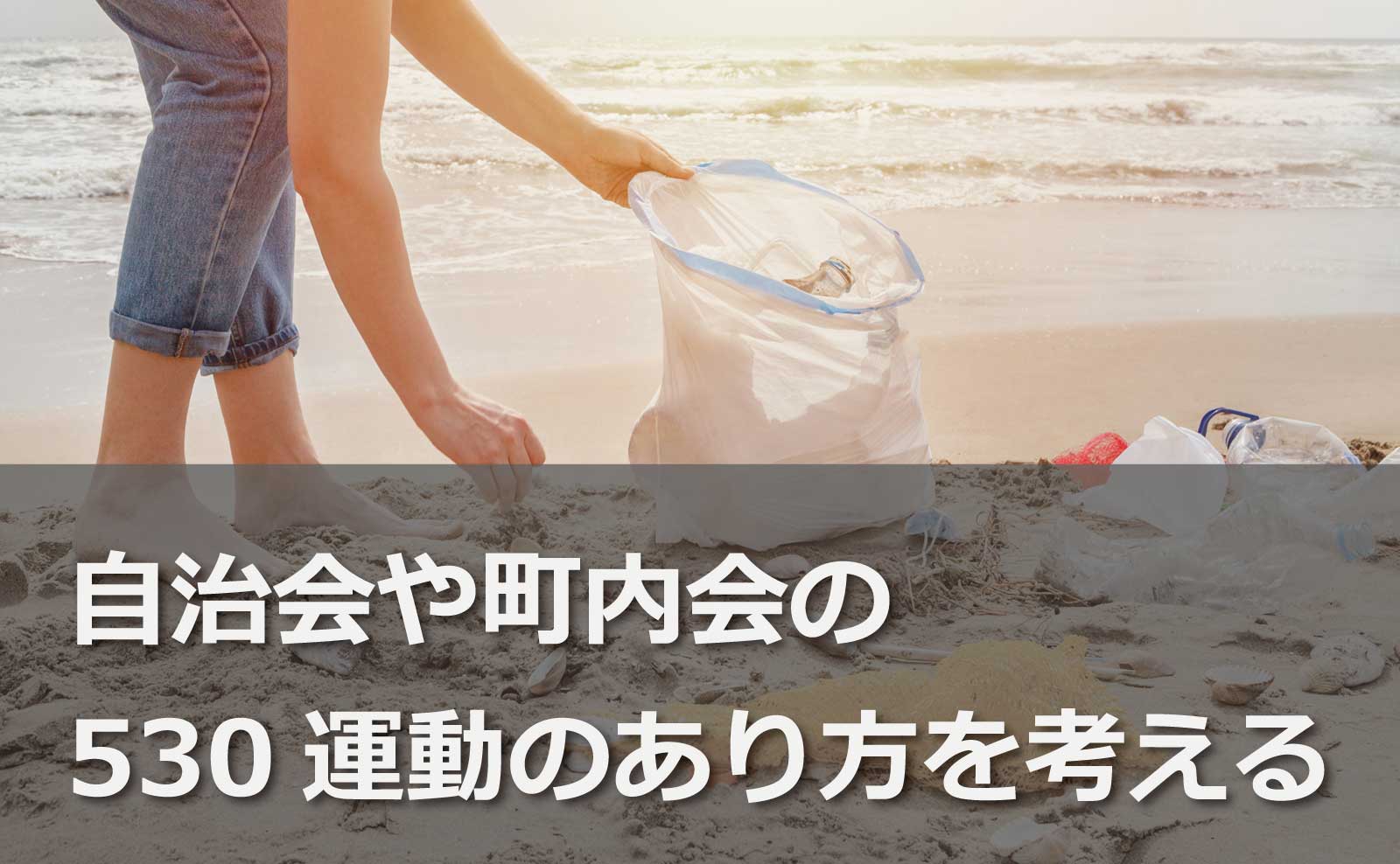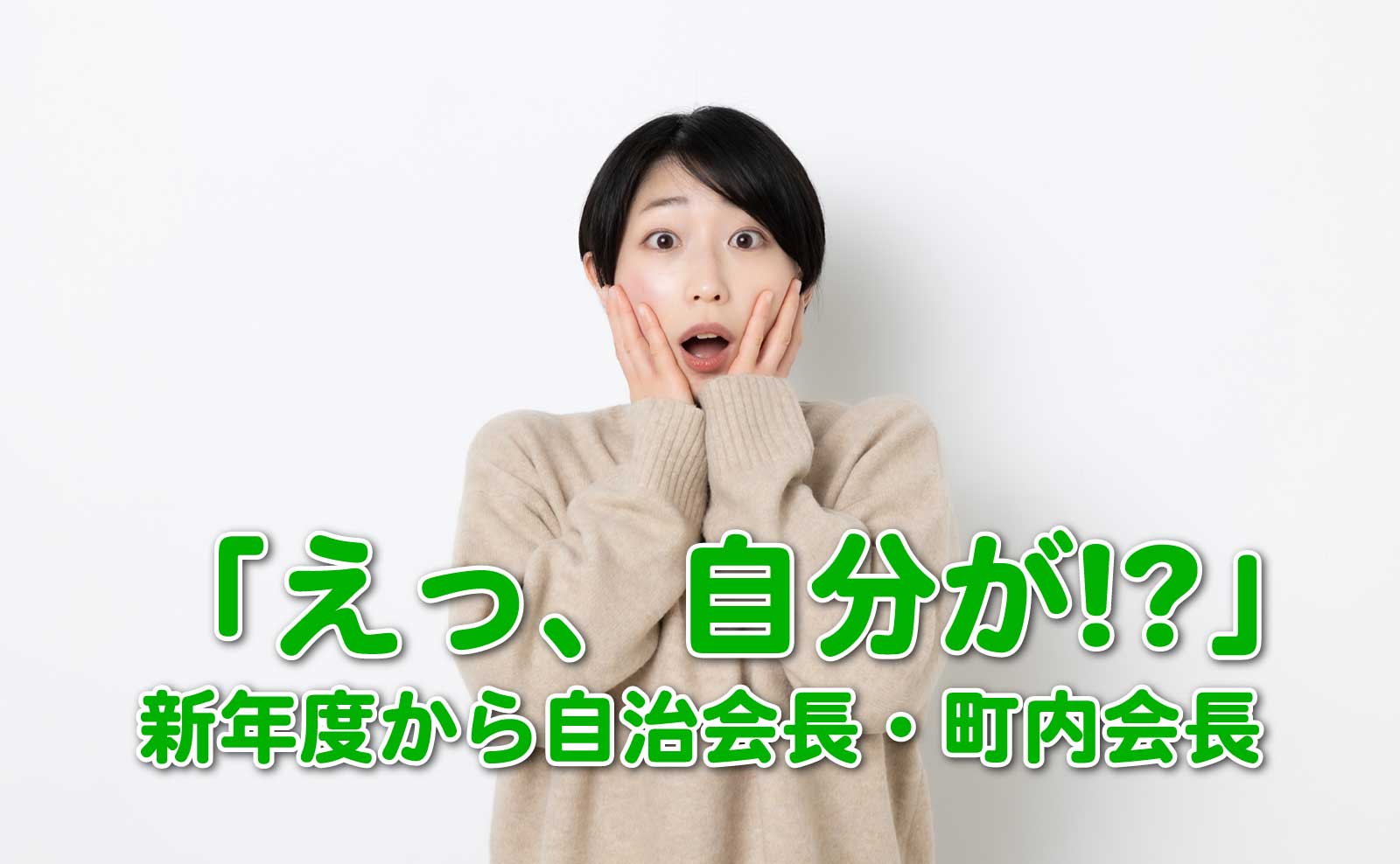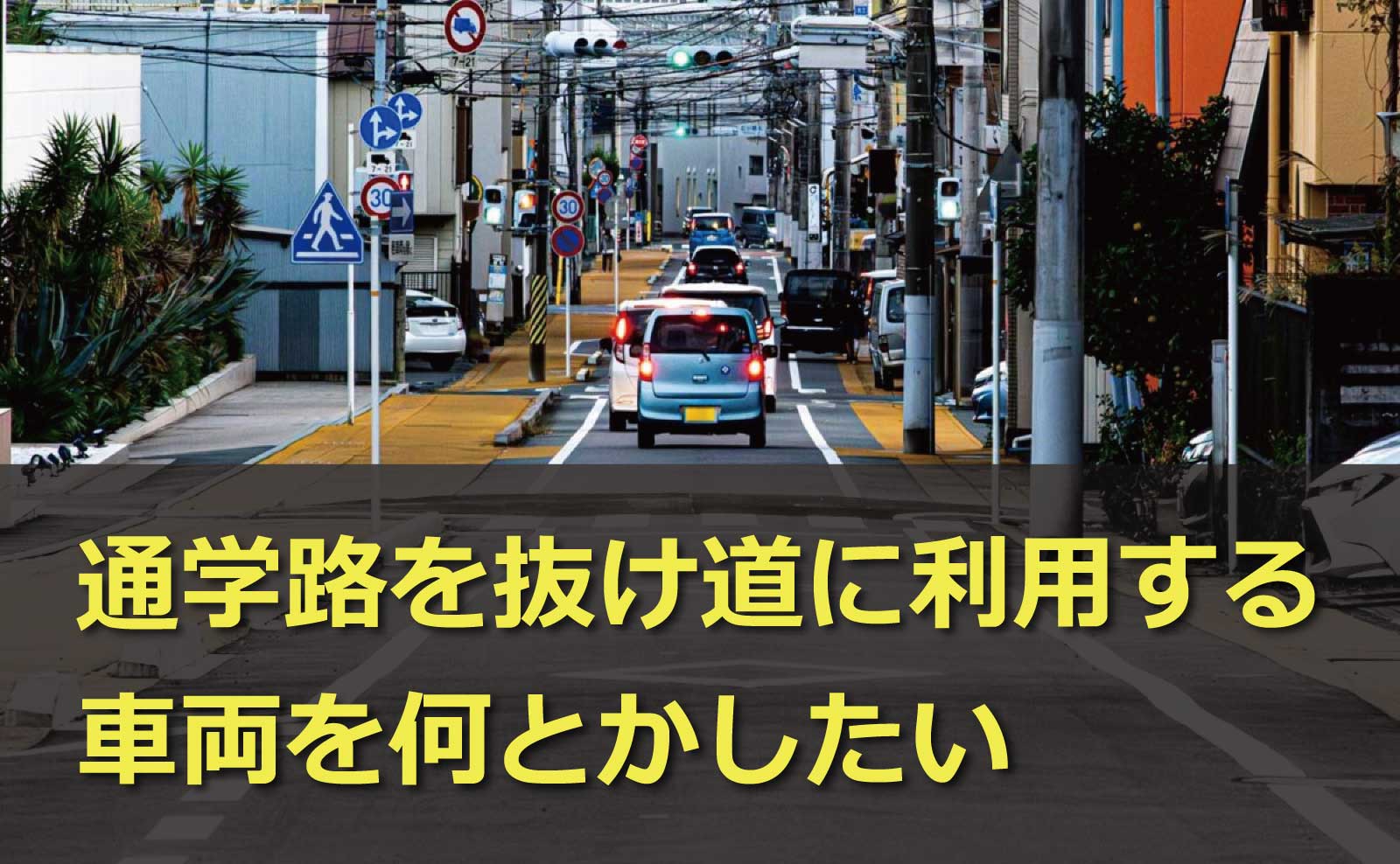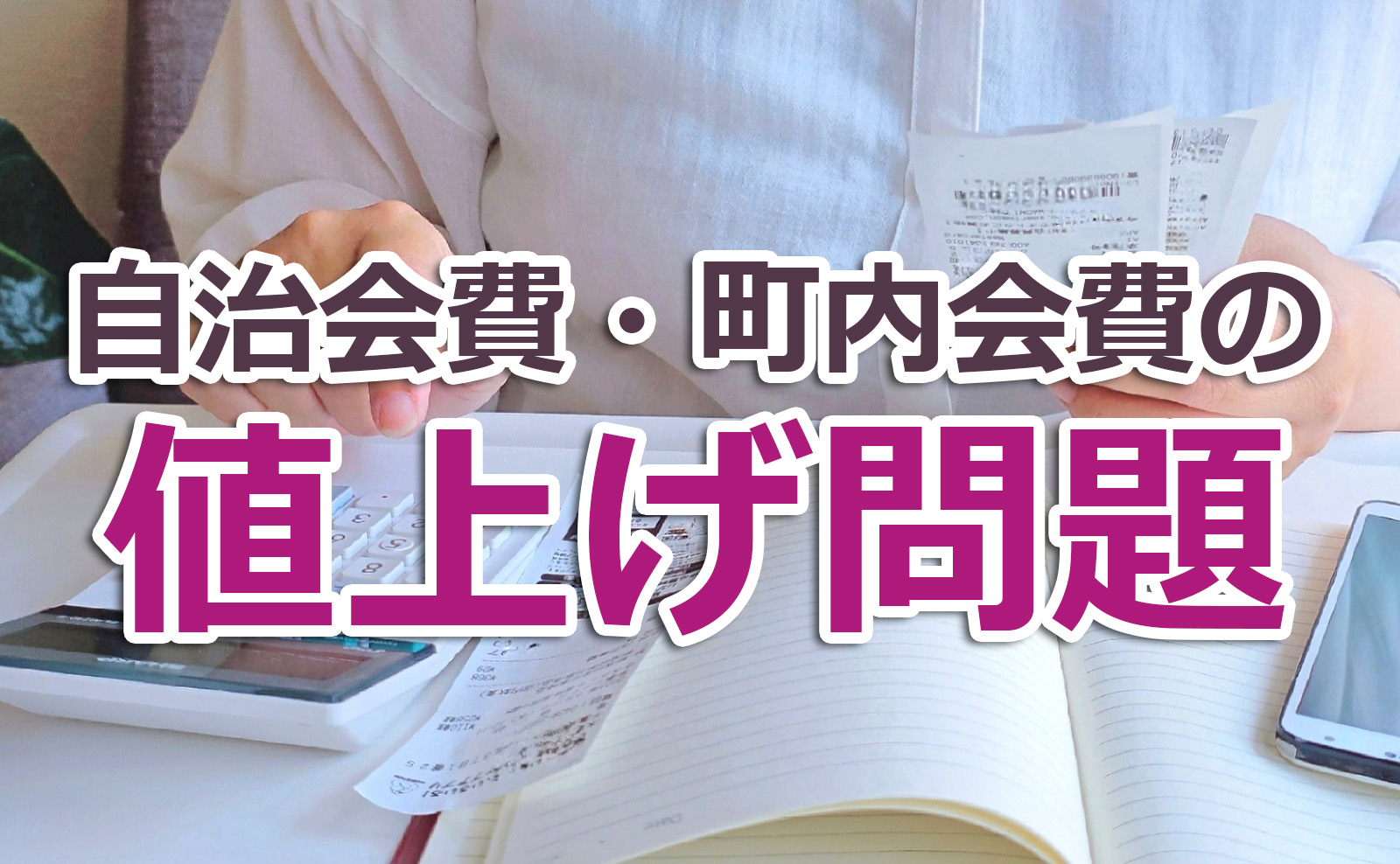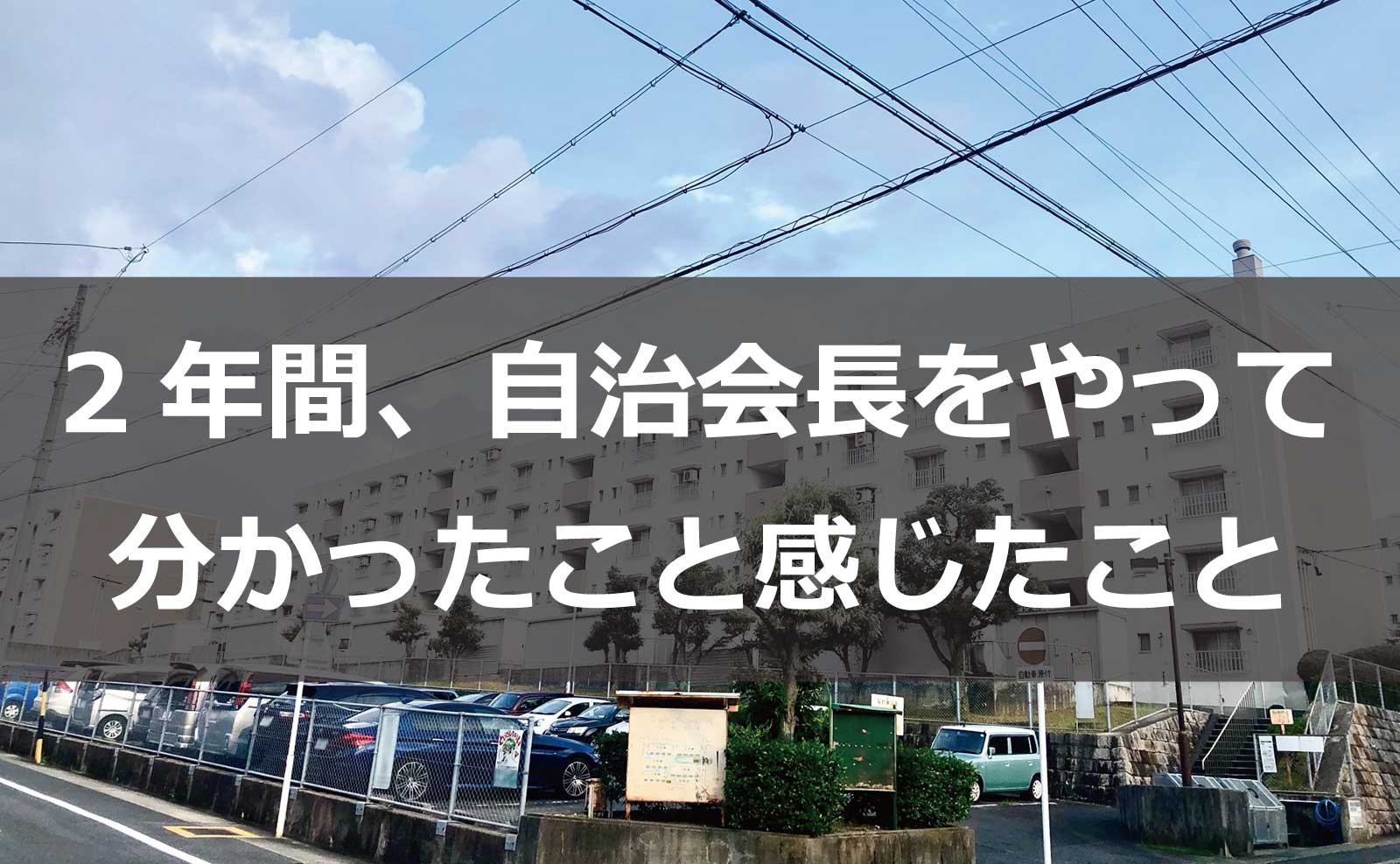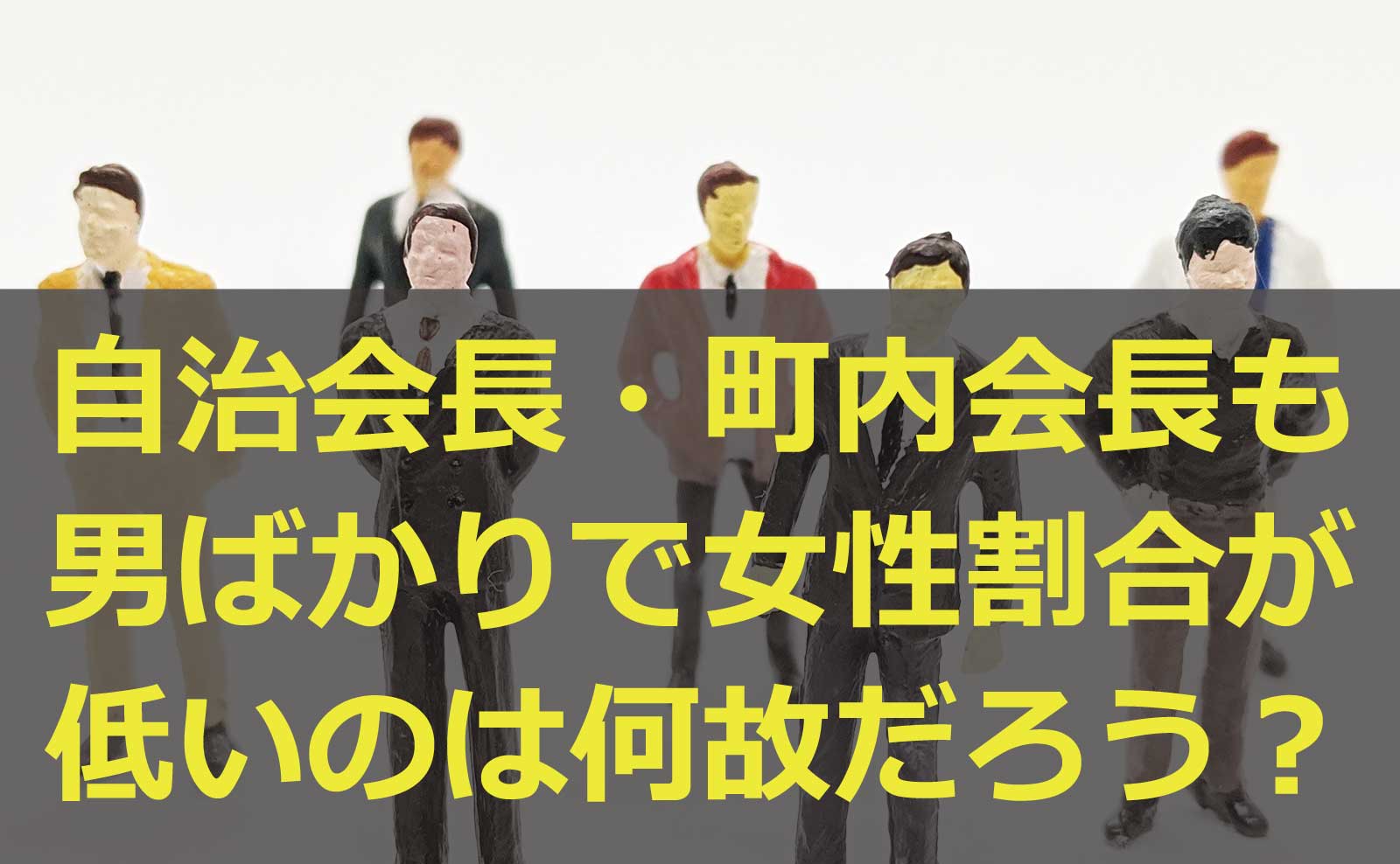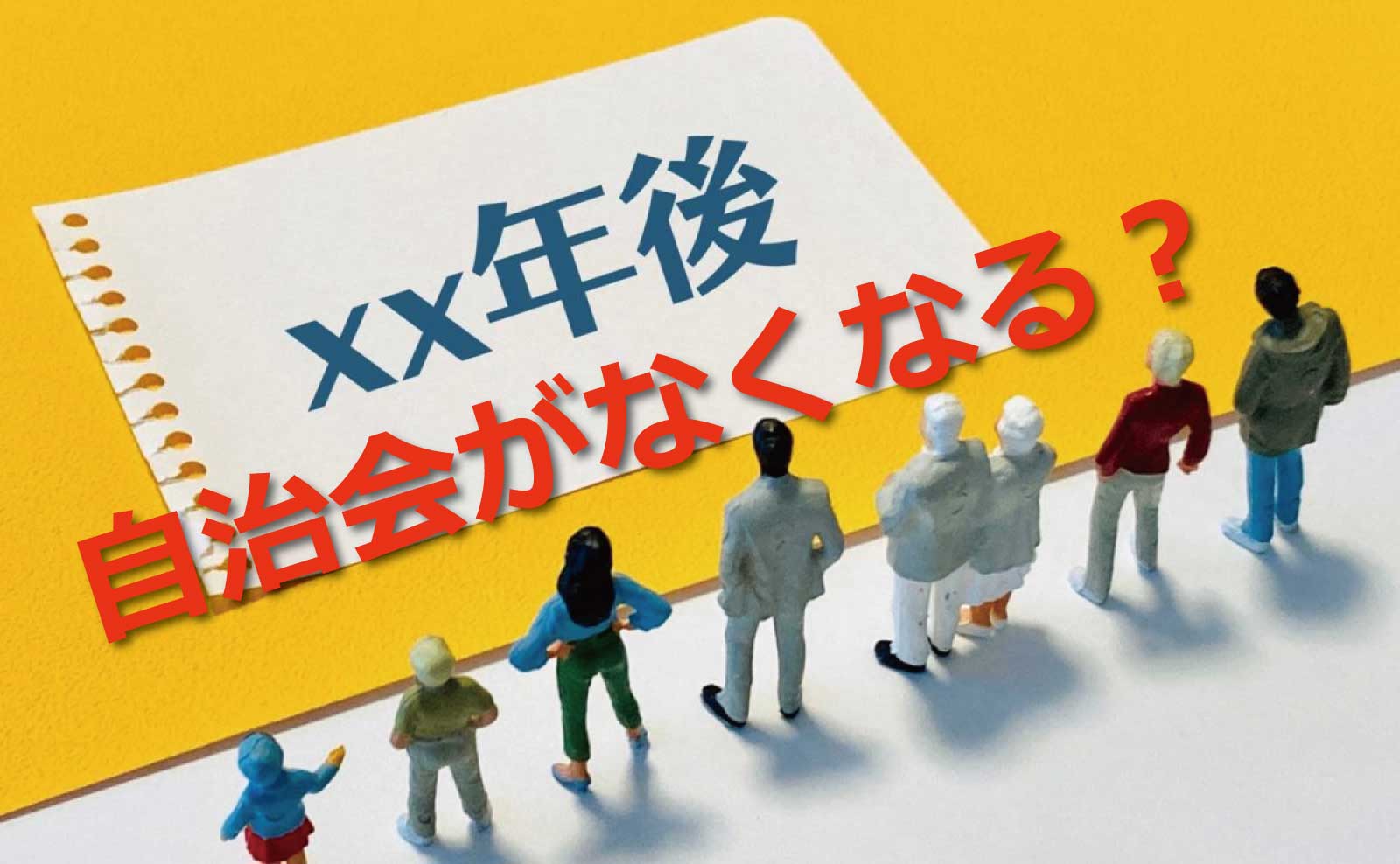はじめに
「自治会と町内会はどう違うの?」引っ越しや地域活動への参加を考えるとき、誰もが一度は疑問に思うテーマです。名前が違う以上、仕組みや役割も違うのではないか、と考える人も少なくありません。しかし結論から言えば、総務省の定義によると「自治会」も「町内会」も、さらには「町会」「部落会」「区会」「区」といった呼称も、すべて「地縁によって形成された団体」として同じ枠組みに含まれています。つまり法的な位置づけや団体としての性格はほぼ共通であり、呼び名が違うからといって役割が大きく異なるわけではないのです。
では、なぜ名称が複数存在しているのでしょうか。その背景には、地域の歴史や文化、そして行政区分の違いがあります。都市部では「町会」と呼ばれることが多く、地方では「自治会」という呼び方が一般的です。また、かつての集落単位を引き継いだ「部落会」や「区会」といった呼称も今なお残っています。さらに、同じ市内でも「町内会」と「自治会」が並立しているケースもあり、地域によっては役割分担をしているところもあります。
こうした違いは、地域ごとの成り立ちや慣習を反映したものに過ぎません。日常的な活動内容、防犯や防災、清掃活動、地域イベント、行政との連携などはどの呼称の団体でも共通しています。つまり、「自治会と町内会はどちらが上か、どちらが正式か」といった議論はあまり意味がなく、大切なのはその地域でどう機能しているか、という点に尽きるのです。今回は、この「呼称の違い」と「共通点」を整理しながら、現代的な課題やICT活用の観点も交えてわかりやすく解説していきます。