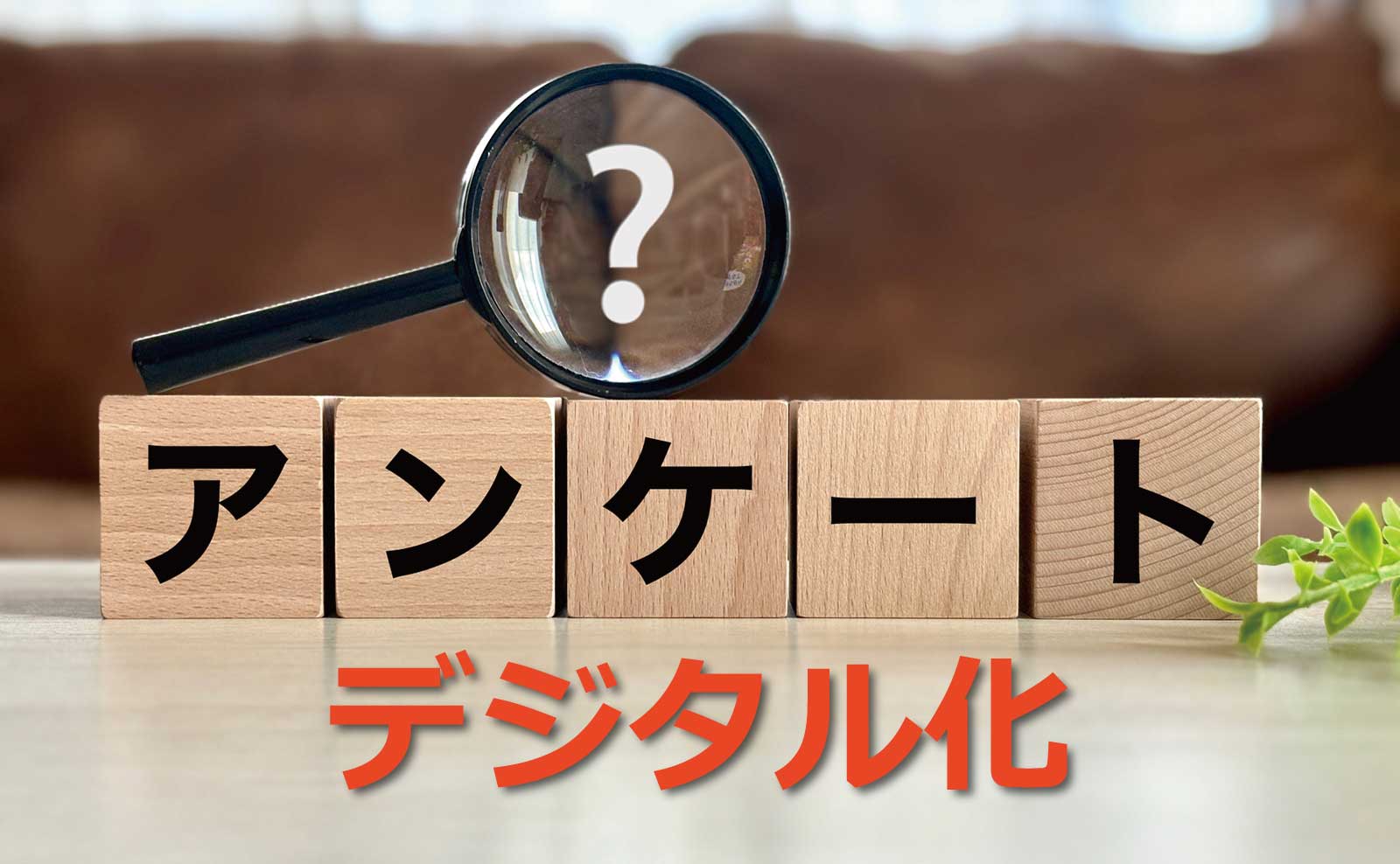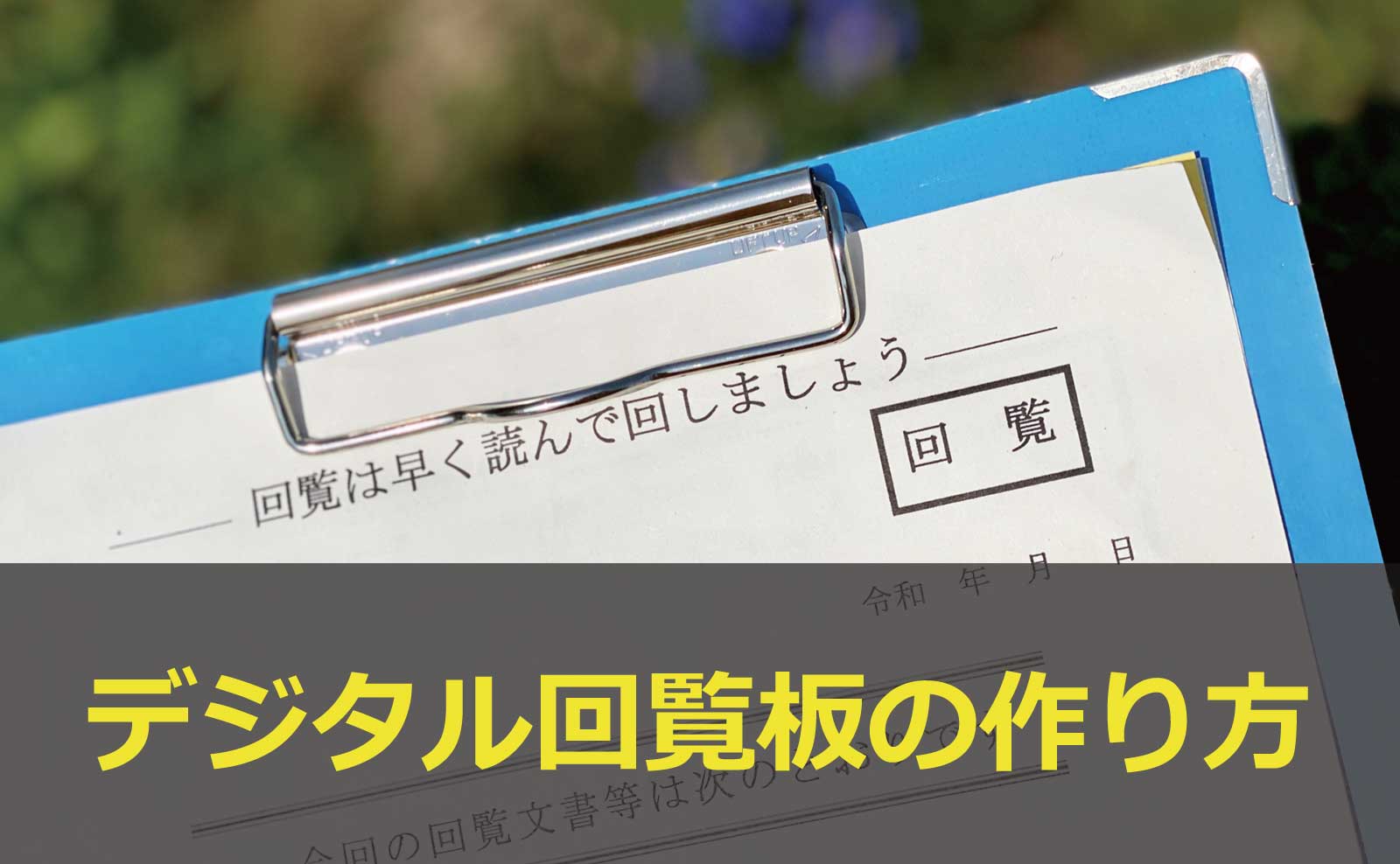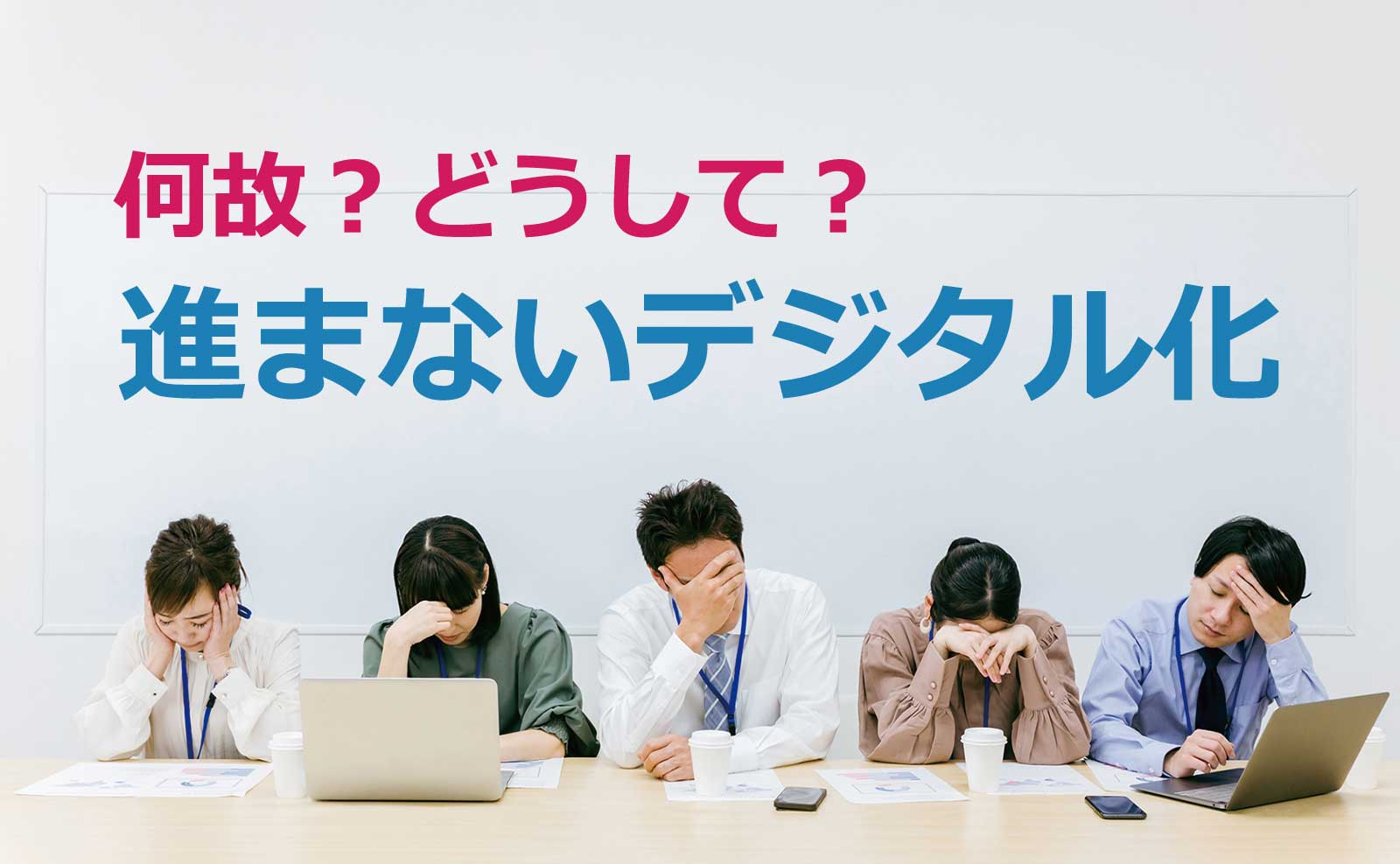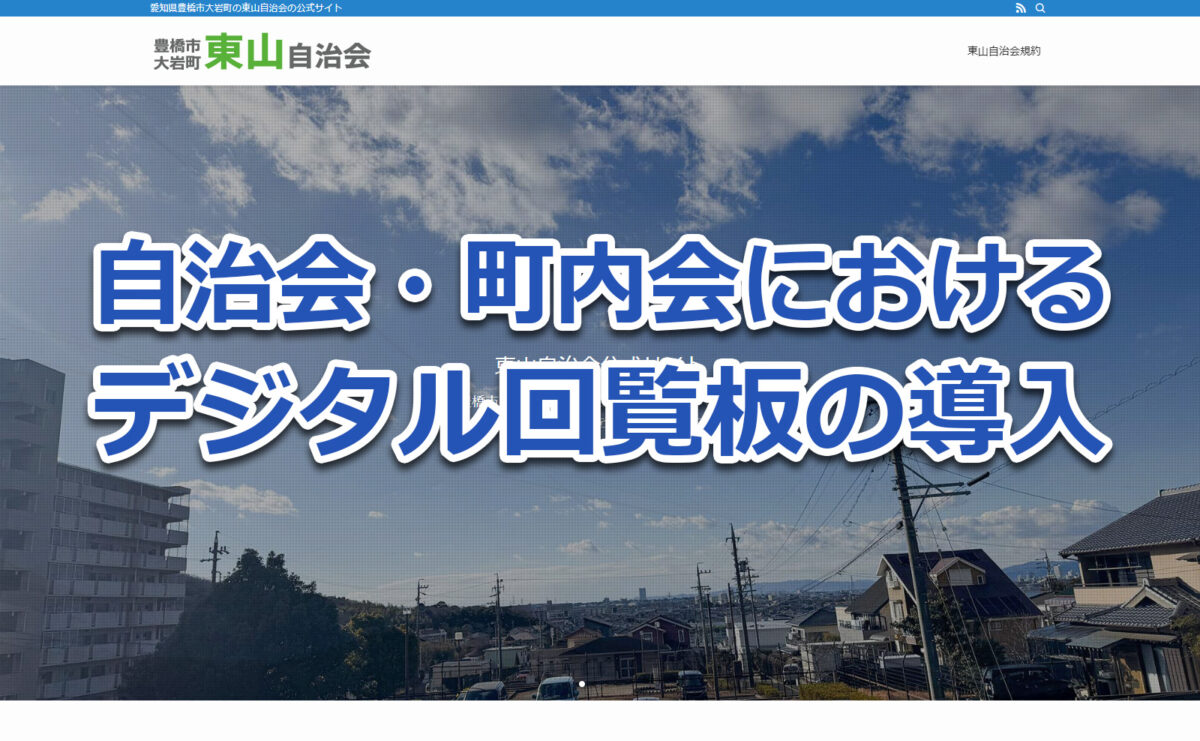
はじめに
自治会や町内会にとって「回覧板」は、長年にわたり地域住民へ情報を届ける基本的な伝達手段として活用されてきました。行政からのお知らせや防犯・防災に関する案内、地域行事や清掃活動の告知など、多くの情報が回覧板を通じて共有され、地域の暮らしを支えてきたといえます。しかし、紙の回覧板にはいくつかの課題が存在します。例えば、回す順番が滞ると全体に届くのが遅れることがありますし、忙しい家庭では「見るのを忘れた」「押印し忘れた」といったトラブルも少なくありません。また、集合住宅や共働き世帯の増加により、そもそも回覧板を受け取るタイミングが難しい家庭も増えており、情報の伝達効率に疑問が持たれる場面も見られます。
一方で、社会全体ではデジタル化が急速に進んでいます。行政手続きや買い物、銀行取引までスマートフォンやパソコンで完結できる時代において、自治会活動も例外ではありません。最近では、紙の回覧板を補完する形で「デジタル回覧板」を導入する動きが全国各地で広がっています。自治体が専用システムを推奨したり、LINEや専用アプリを使った情報共有が進められたりと、さまざまな試みが行われています。ICTを活用することで、住民にとっては「いつでもどこでも確認できる」「見逃しが減る」という利便性が高まり、役員や班長にとっても負担軽減や効率化につながります。こうした流れは、少子高齢化や人手不足に直面する地域活動において、持続可能な仕組みづくりの一歩といえるでしょう。