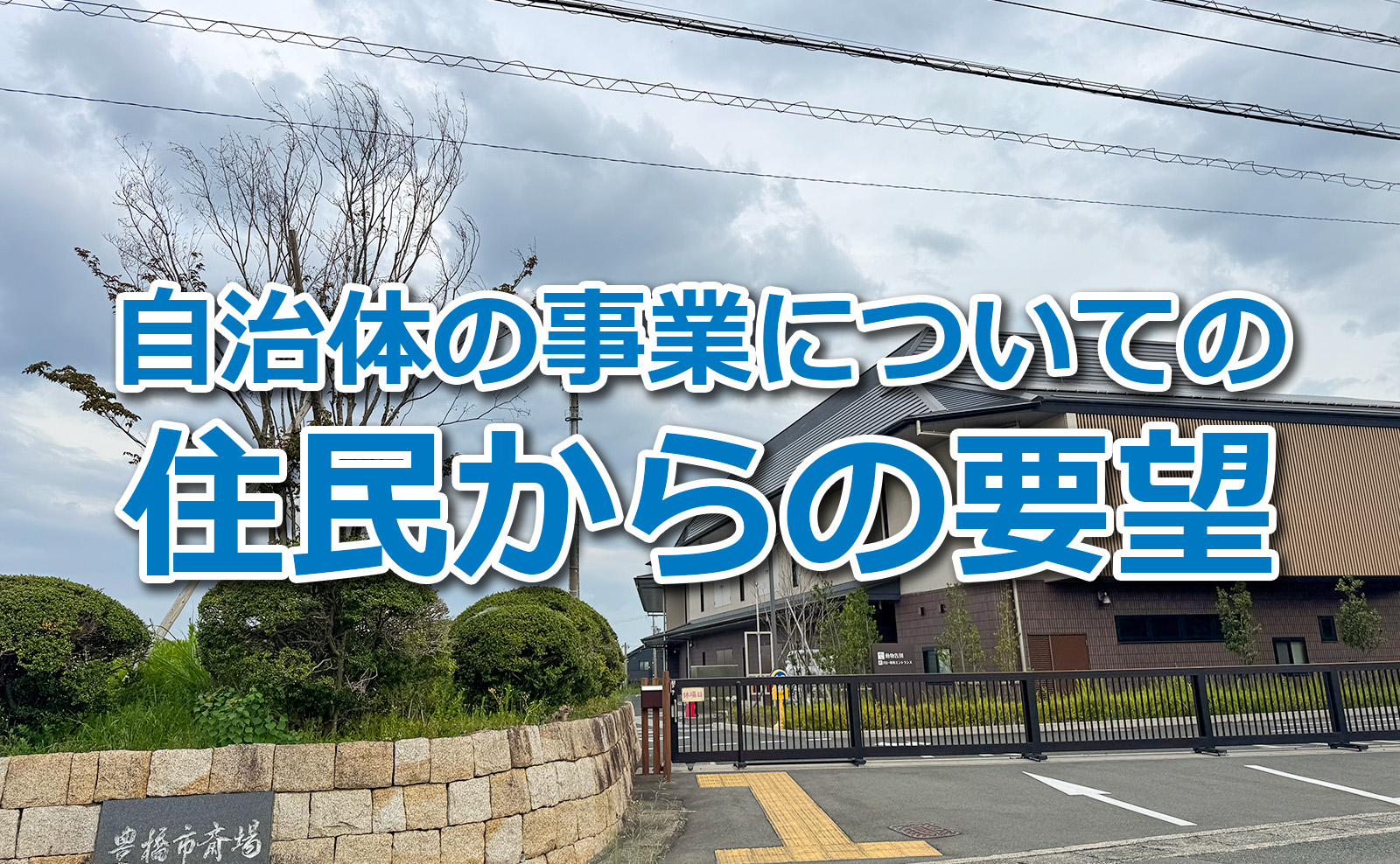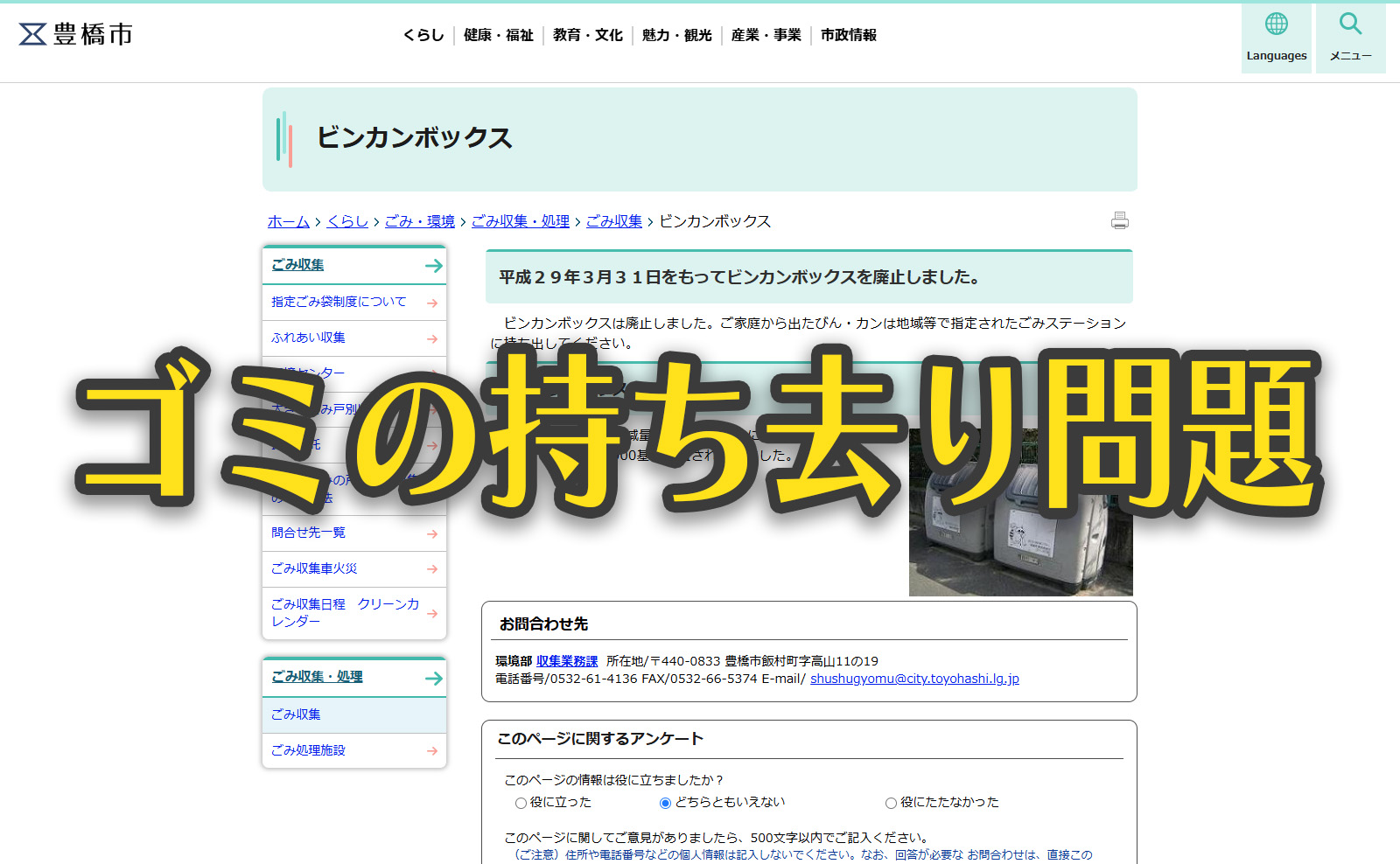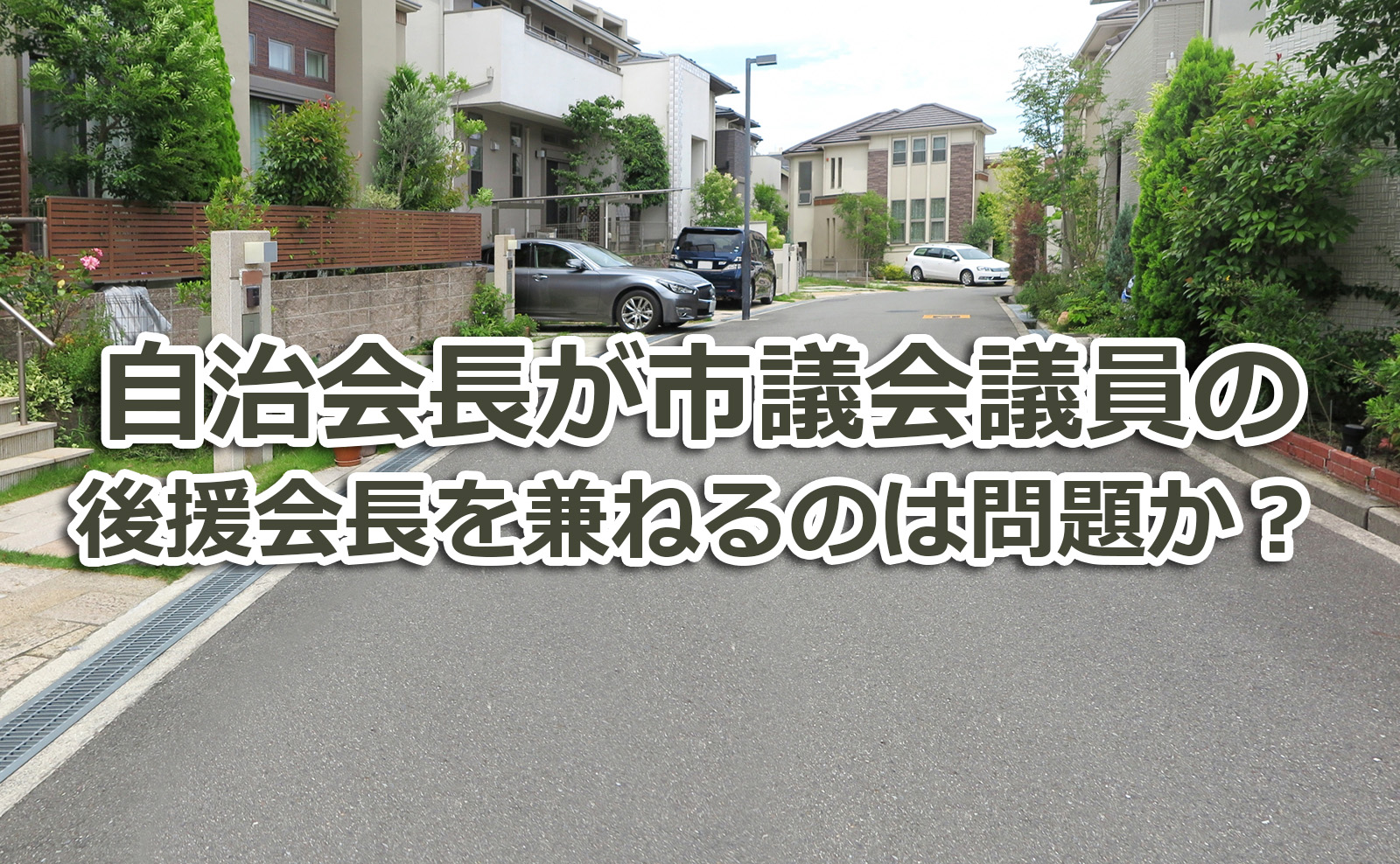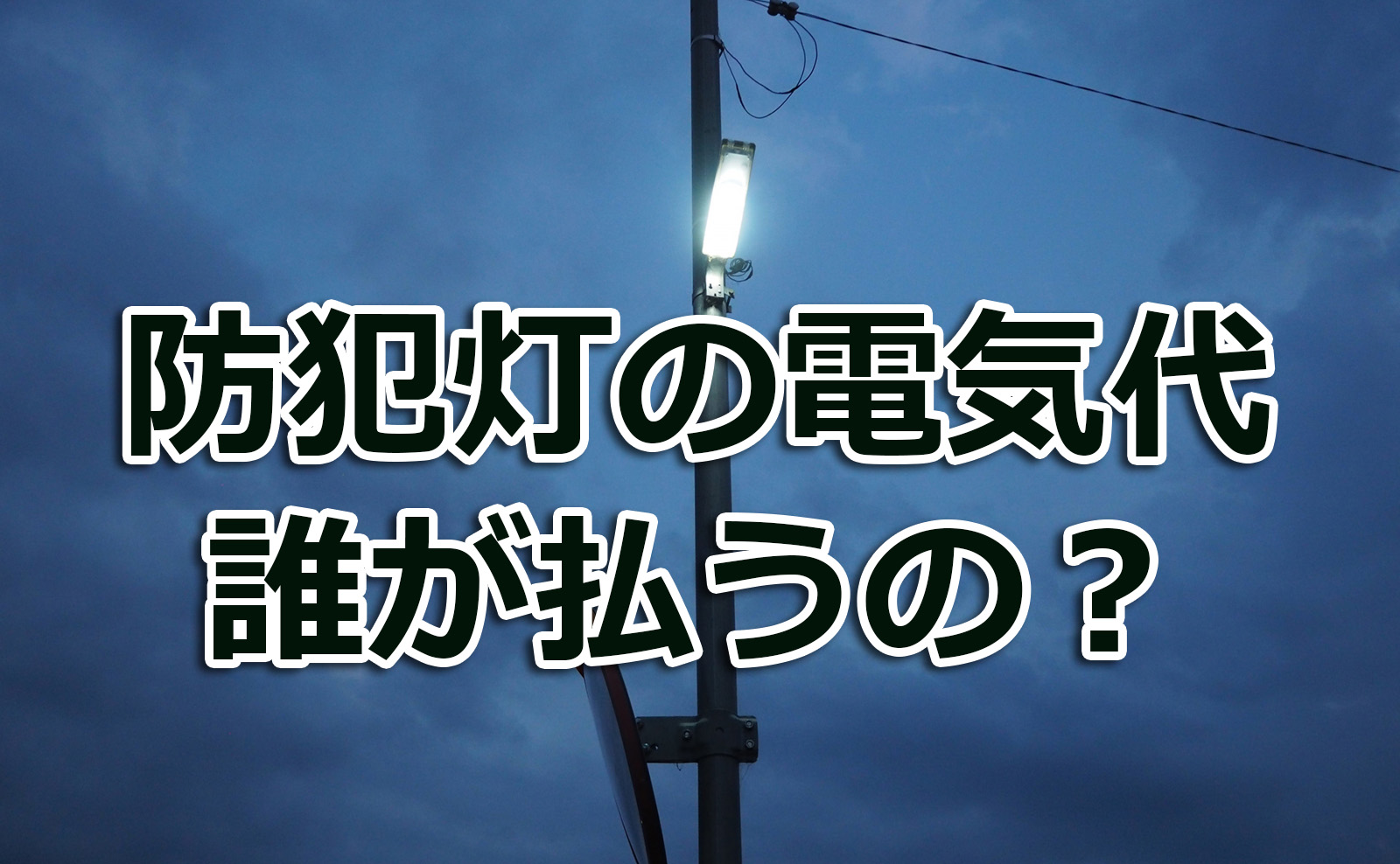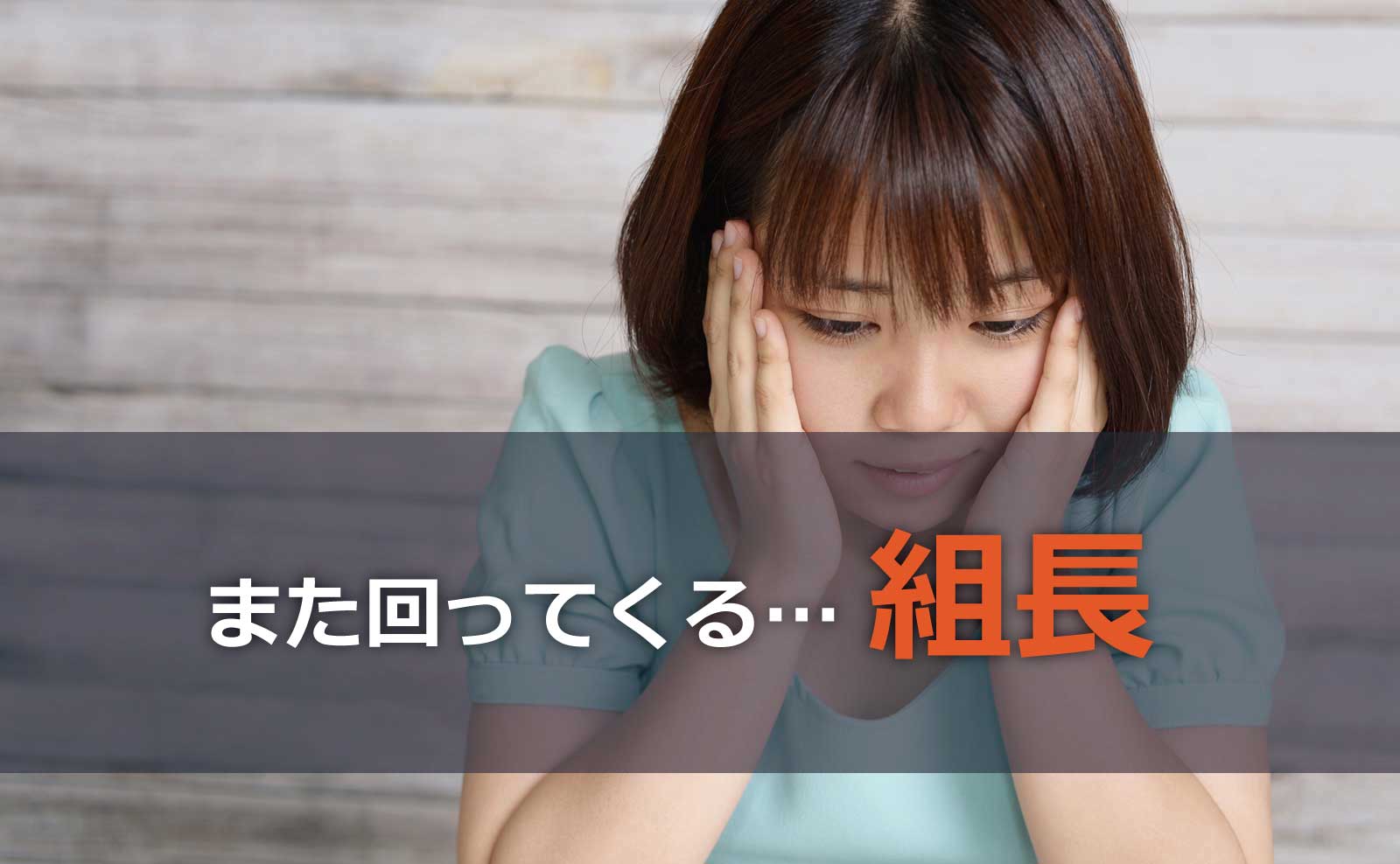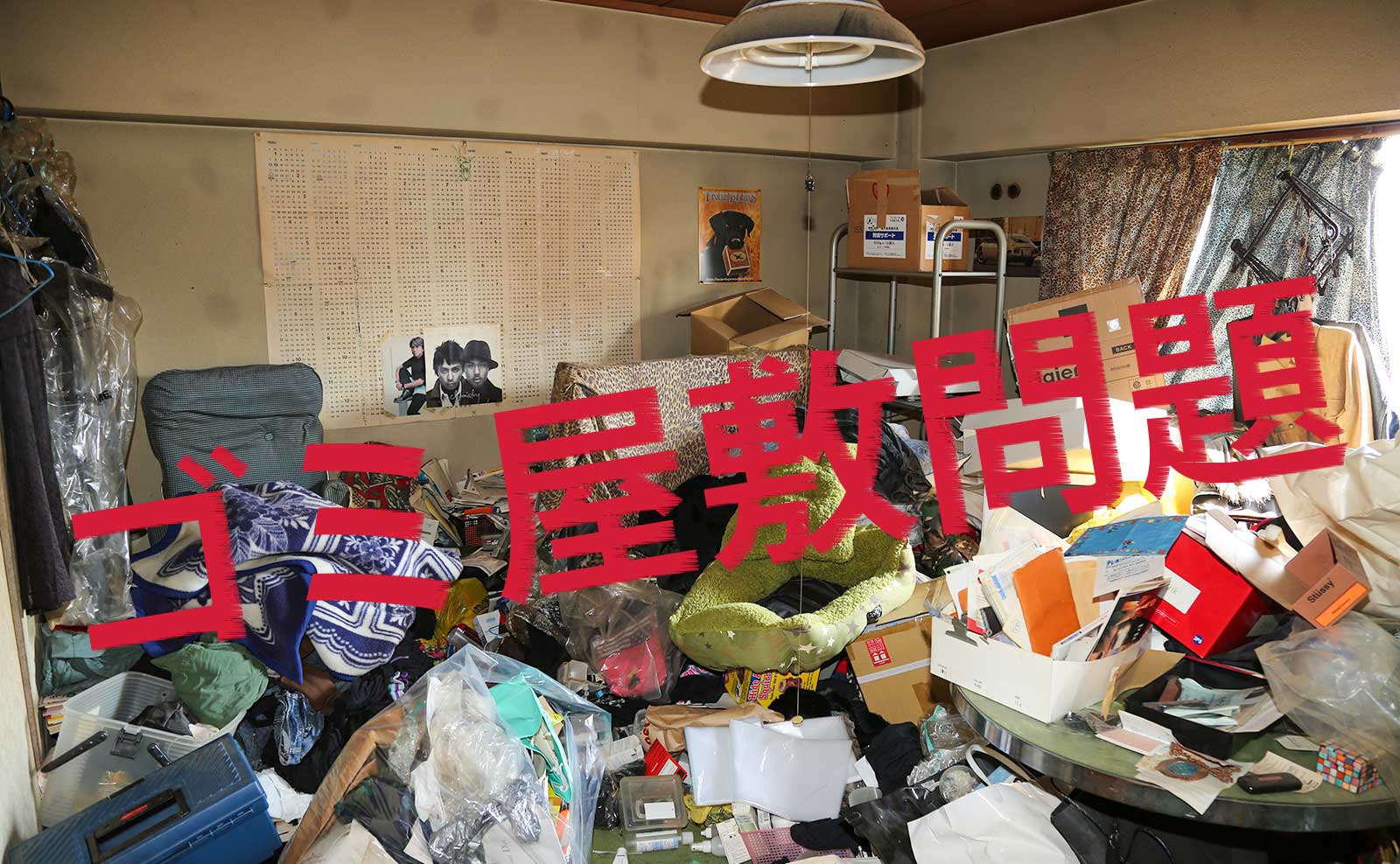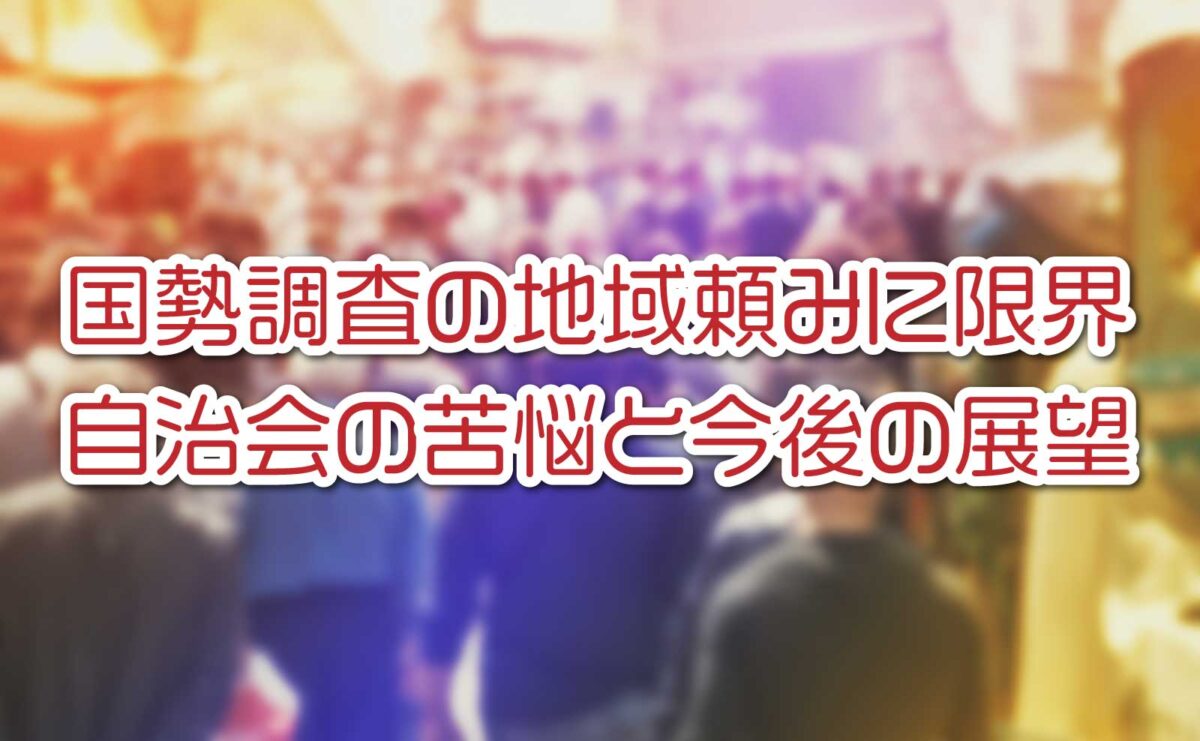
5年に一度の「国勢調査」、今年もその季節がやってきました。日本に住むすべての人と世帯を対象に行われる、国が主導する大切な調査です。人口や世帯構成、就業状況など、さまざまな統計の基礎となるこの調査は、行政サービスや地域政策を考えるうえでなくてはならないもの。だからこそ、調査がきちんと行われることが、とても大切なのです。
でも、今回もまた、調査を担う「調査員」の確保に全国の自治体が頭を悩ませています。調査員は、住民のもとに調査票を届けたり、回収したり、場合によっては再訪したりと、なかなか大変な役目。報酬はあるとはいえ、誰でも気軽にできる仕事ではありません。地域のことをよく知っている人にお願いしたいという理由で、自治会に「調査員を推薦してください」と依頼が来るのが通例ですが、これがなかなかの重荷になっているようです。
実際に、現場の自治会では
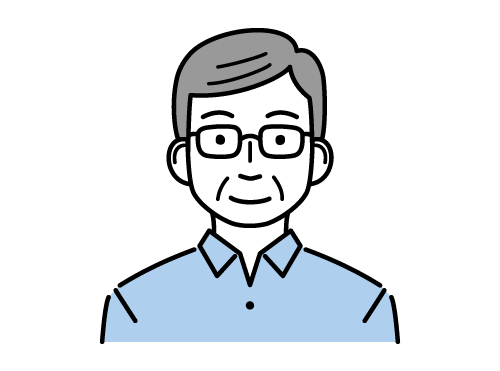 自治会長
自治会長誰に頼んでも忙しくて断られる



そもそも自治会がやるべき仕事なの?
という声がちらほら。調査員を引き受けてくれる人が集まらず、自治会長が頭を下げて回るケースも少なくありません。国の大切な調査が、地域の「顔の見える関係性」と「なんとかなる精神」に頼っている現実。時代が変わってきた今、このやり方にも見直しの時期が来ているのかもしれません。
現場の声:福井市・上野本町自治会の例
福井新聞のウェブ版に以下のような記事が掲載されました。冒頭の部分を引用します。
5年に1度の国勢調査が今秋、全国一斉に行われる。福井県内でも市町が調査票の配布・回収などに当たる調査員の確保を進めているが、福井市内の自治会長から「調査員を推薦するよう連絡があったが集まらない」との訴えが、福井新聞の「ふくい特報班」(ふく特)に届いた。自治会の負担を減らそうと調査員の公募に力を入れる市町も増えているが、確保には苦心。地域の担い手確保自体が課題となっている中で「人頼みの調査は限界にきているのでは」との声も上がる
加入世帯だけで660軒を超える福井市森田地区の上野本町自治会。今年初めて自治会長になった北嶋孝夫さん(67)は3月下旬、地区の自治会連合会の会合で、調査員6人を推薦するよう求められた。自治会役員らに相談したところ「仕事があるので厳しい」「そもそも自治会が担うべき内容ではないのでは」などと難色を示された。
顔なじみの調査員経験者や元役員らに頭を下げ、なんとか3人に引き受けてもらえたが、自身を加えてもまだ2人足りない。「世の中どこも人手不足なのでなかなか集まらない。調査方法の限界に来ているのでは」と嘆く。
この記事の内容をもとに国勢調査の在り方、自治会や町内会とのかかわりの在り方について考えてみたいと思います。
「調査員を6人出してください」と突然の依頼
春の終わりが見えてきた3月下旬、福井市の森田地区にある上野本町自治会で、ひとつの依頼が舞い込んできました。「今年の国勢調査で、あなたの自治会から6人の調査員を推薦してください」。市からの依頼は、自治会連合会を通じて各町内へと伝えられます。これが初めて自治会長を務める北嶋孝夫さん(67)にとって、想像以上に重たい宿題になったのです。
初めての役目に戸惑いながらも、何とかしなければと声をかけて回りますが、なかなか話は進みません。「そもそも調査員の仕事って、こんなに集めにくいものなのか…」と、初陣を飾るには少し荷が重いスタートでした。



簡単に『推薦して』と言われますが、現実にはそう簡単じゃないんです
「それって本当に自治会の仕事なの?」
推薦に向けて、北嶋さんはまず自治会の役員たちに相談しました。しかし返ってきたのは、思っていた以上に厳しい反応でした。「平日は仕事があって無理」「自分たちが担うべき役割とは違うんじゃないか」。自治会とはいえ、住民のボランティアで成り立つ組織。国の業務を肩代わりするような任務に、戸惑いや不満の声も出てきます。
さらに、役員世代の多くも現役で働いているため、時間的な余裕もありません。「善意」で回っていた仕組みが、今の社会構造ではもう回らない。それを突きつけられる瞬間でもありました。



地域のことはできるだけ協力したいけど、これは本当にうちの仕事なんですかね…
頭を下げて、頼み込んで、それでも足りない
それでも北嶋さんは諦めませんでした。かつて調査員を務めた経験者、以前役員だった人、顔見知りの近所の方…心当たりのある人に一人ひとり声をかけ、頭を下げてお願いをしました。その結果、なんとか3人が「やってみようか」と応じてくれました。
とはいえ、目標の6人にはまだ届きません。北嶋さん自身も調査員を引き受けることで「あと2人」まで迫りましたが、最後の一押しが難しい。頼れる人は限られ、これ以上お願いするのは気が引ける…そんな葛藤が募ります。



調査員が足りないのは理解してます。でも、こちらも人が余っているわけじゃないんです
「人手不足」と「役割の曖昧さ」に揺れる現場
調査員を集める苦労の裏には、「人手不足」と「役割のあいまいさ」という、2つの大きな壁があります。地域に協力的な人が減っていることに加え、国勢調査のような“国の仕事”をなぜ自治会が請け負うのか、というモヤモヤも残ります。
自治会の仕事とは一体どこまでが「地域のため」で、どこからが「行政の委託」なのか。その線引きがはっきりしないまま、人づてにお願いが続く現状に限界が見えつつあります。調査員を集められないのは、自治会の責任ではなく、制度の構造にこそ課題があるのではないでしょうか。



地域だからお願いって言われても、もう頼れる人が本当にいないんです
国勢調査を行うにあたって制度の構造的な問題
「地域を知る人」に頼る、という理屈
国勢調査の実施にあたり、各自治体が調査員の確保を自治会に依頼する理由は明確です。それは「その地域の事情をよく知る人のほうがスムーズに調査が進む」という考え方に基づいています。町内の地理、住民の顔ぶれ、生活リズムなど、地元に精通している人材が調査を行えば、効率よく信頼関係を築けるという期待があるのです。
実際、地域内で顔見知りの関係性があれば、調査票の配布や回収も円滑になる可能性はあります。問題が起きたときにも柔軟な対応ができるとして、こうした「地域密着型」の人材が重宝されてきました。結果、推薦依頼は今もなお、各地区の自治会へと向けられているのです。
しかし、その地域がすでに疲弊している
ところが、この前提には大きなほころびが出始めています。そもそも自治会そのものが、深刻な人手不足と高齢化に直面しているのです。役員のなり手がいない、若い世代が加入しない、運営は一部の高齢メンバーに偏っている…そんな現実の中で、「調査員の確保」まで任されるのは過重な負担です。
さらに、地域内での「顔が利く人」が減ってきているのも問題です。昔のように、町内の誰がどこに住んでいて、どんな人柄なのかを自然に把握しているご近所付き合いの文化は薄れつつあります。自治会が頼れる「地域のネットワーク」は、もう以前のようには機能していないのです。
気軽にできる仕事ではない、という現実
調査員には報酬が支払われるとはいえ、その仕事内容は決して「簡単で軽い仕事」とはいえません。配布・回収だけでなく、期限までに回答が得られなかった場合には督促訪問を行ったり、近隣住民への聞き取りを求められることもあります。
こうした業務は、心理的な負担も伴います。世帯によっては応対を拒まれるケースもあり、クレームやトラブルに発展する可能性もゼロではありません。「お金が出るんだから頼めばいい」という単純な構図では済まないのです。誰かに勧めるには、それなりの覚悟と信頼関係が必要とされます。
制度が「地域に頼りすぎている」ことへの問い直し
現在の国勢調査の仕組みは、「地域の力で成り立つ」ことが前提となっています。しかし、その「地域力」が持続不可能になりつつある今、制度そのものの見直しが求められているのではないでしょうか。行政と住民のあいだで責任の境界が曖昧なまま、昔ながらのやり方を続けていては、現場の混乱や負担は増すばかりです。
- 自治体が自治会に調査員の推薦を依頼するのは「地域を知る人材」が望ましいという前提から
- しかし自治会自体が高齢化と担い手不足で対応困難になっている
- 調査員の業務内容は心理的負担も大きく、気軽に引き受けられる仕事ではない
- 現制度は「地域の善意」に頼りすぎており、制度的な再設計が必要とされている
国勢調査における自治体の対応とその効果
公募という新しい試み、しかし…
自治会に依存し続けることへの限界が見え始めた今、福井県内のいくつかの自治体では、調査員の「公募」に力を入れはじめています。たとえば敦賀市では、約350人の調査員を必要とする中で、前回調査時に初めて公募を試みました。しかし、1か月間の募集期間にもかかわらず、集まった人数は「ゼロ」。自治会ルート以外からの確保は思うように進みませんでした。
この反省を踏まえ、今回の国勢調査では公募開始を前倒し、2か月半に期間を延長。より早期に広報活動を行うことで、少しでも応募の可能性を高めようとしています。チラシ、ホームページ、広報紙、SNS――あらゆる手段を使って呼びかけを行っている状況です。
「誰でもできる」仕事を伝える努力
越前市も同様に公募開始時期を1か月前倒しし、市の広報紙や公式サイトで積極的に呼びかけています。特徴的なのはそのアピール方法。「100世帯で4万6千円」「誰でも簡単にできるお仕事です」といった具体的な金額とともに、「スキマ時間のあるシニア層、パート主婦層、大学生に向いています」とターゲットを明確にしたPR文句を使っている点です。
鯖江市も、公募と並行して過去に調査員を務めた市民への声かけを進め、経験者の再任を目指しています。新規の応募が少ない中、すでに仕事内容を理解している人材を中心に確保するのは、現実的な策といえるでしょう。
それでも「集まらない」現実
工夫を凝らしても、なお調査員の確保は厳しいままです。働く高齢者の増加、地域活動への参加意欲の低下、対面業務への不安感――背景には複数の要因が絡み合っています。特に、自治体がいくら「簡単な仕事」と伝えても、現場では「断られたときの気まずさ」「聞き取りのプレッシャー」「トラブルのリスク」など、心理的ハードルの高さが応募をためらわせていると考えられます。
自治体としても、もう自治会任せにはできないという危機感は強まっています。しかし、公募一本に切り替えるには説得力と成功事例がまだ不足しており、「移行期」のもどかしさが各地でにじんでいます。
- 敦賀市・鯖江市・越前市などで公募制度を強化し、開始時期や広報方法を工夫
- 金額や対象層を具体的に示し、応募しやすいイメージづくりに努めている
- 経験者への再依頼も現実的な対策として進行中
- それでも応募数は伸び悩み、「簡単な仕事」として受け止められていない実情
- 自治会任せからの脱却を図りつつも、制度的な過渡期にあることが課題
今後の展望:国勢調査のICT化・地域支援の可能性
紙の配布から“デジタル案内”への転換を
国勢調査はすでにオンライン回答に対応しており、前回(2020年)の調査では、全国で約53%がインターネットで回答を済ませました。これは都市部に限らず、地方でも一定の普及が見られたことを意味します。それならば、調査員の役割も「紙を配って回収する」から、「オンライン回答への案内・サポート」へと軸足を移していくことができるはずです。
たとえば、高齢者世帯には、スマートフォンの操作方法やQRコードの読み取り方を簡単にレクチャーする支援をする。あるいは、パソコンやタブレットの貸し出し、地域でのICT教室との連携など、オンライン回答を“自分ごと”にできる環境を整えることも一つの方法です。
担い手は自治会以外にもいる
調査員=自治会が担うべき、という固定観念から脱却すれば、もっと多様な担い手が見えてきます。たとえば、地域のNPO団体やシルバー人材センター、大学の地域連携プロジェクトなど。特に大学生は、柔軟な時間を持つ若年層であり、報酬と社会経験の両面から参加意欲を引き出すことが可能です。
また、子育てがひと段落した主婦層や、地元に貢献したいと考えるシニア世代にもアプローチする余地があります。自治体は、従来の「推薦ルート」に加えて、こうした“潜在的な担い手”を意識した仕組みづくりを進めるべき時期に来ているのです。
制度を再設計する視点を
「地域の信頼感がある人でなければ調査できない」「顔見知りの方が安心」という意見も確かに根強くあります。しかし、その前提自体が変化している今、制度そのものを時代に合わせて見直す必要があります。たとえば、デジタルでの本人確認や、郵送調査の精度向上、サポートコールセンターの強化など、行政の側が“人に頼らない仕組み”を本気で整備すれば、調査の負担は大きく減るはずです。
「地域にお願いする」のではなく、「地域とともにつくる」調査体制。ICTと人のサポートをうまく掛け合わせることで、地域社会の負担軽減と、正確な調査結果の両立を目指す時代に入りつつあります。
- オンライン回答を前提にした、調査員の役割の再定義が必要
- ICT支援や地域のデジタル教室と連携した「案内役」としての活用
- NPO・大学・シニア人材など、自治会以外の担い手への広がりを視野に
- アナログな「紙文化」から、ICTとのハイブリッド体制への移行を
- 地域と協力しながらも、制度側の抜本的見直しが不可欠
国勢調査のあり方を、地域任せから未来志向へ
今回の国勢調査をめぐる自治会の現場からは、「人が集まらない」「もう限界だ」という切実な声が聞こえてきました。地域を支える仕組みとして長年機能してきた自治会ですが、その人手は今や限られ、善意や関係性だけではどうにもならない状況に直面しています。そんな中で、国の重要な業務を“当然のように”地域に依頼し続ける構造は、見直されるべき時期に来ているのではないでしょうか。
これからの国勢調査には、「人に頼る」前提から、「しくみで支える」発想への転換が必要です。オンライン回答の普及、ICT支援の充実、多様な人材の登用…これらを組み合わせて、地域の負担を分散しながらも、調査の正確性を保つ方法を模索するべきです。
そして何より、制度を運営する行政自身が、「地域が何とかしてくれるだろう」という姿勢を改め、自ら前に出て調整・広報・支援を行っていくことが問われています。地域とともに歩む調査体制の構築こそが、次の5年、10年につながる持続可能な国勢調査の形になるはずです。



元自治会長として、今回の問題は他人事ではありませんでした。「また頼まれるかも」「断りにくい」そんな空気の中で、地域の誰かが黙って負担を背負っているのが現実です。国勢調査は大切な取り組みですが、その運営方法も時代とともに見直す必要があります。「地域の力」に甘えすぎない制度へ。このテーマが、仕組みと支え合いの両方を考えるきっかけになればと思います。