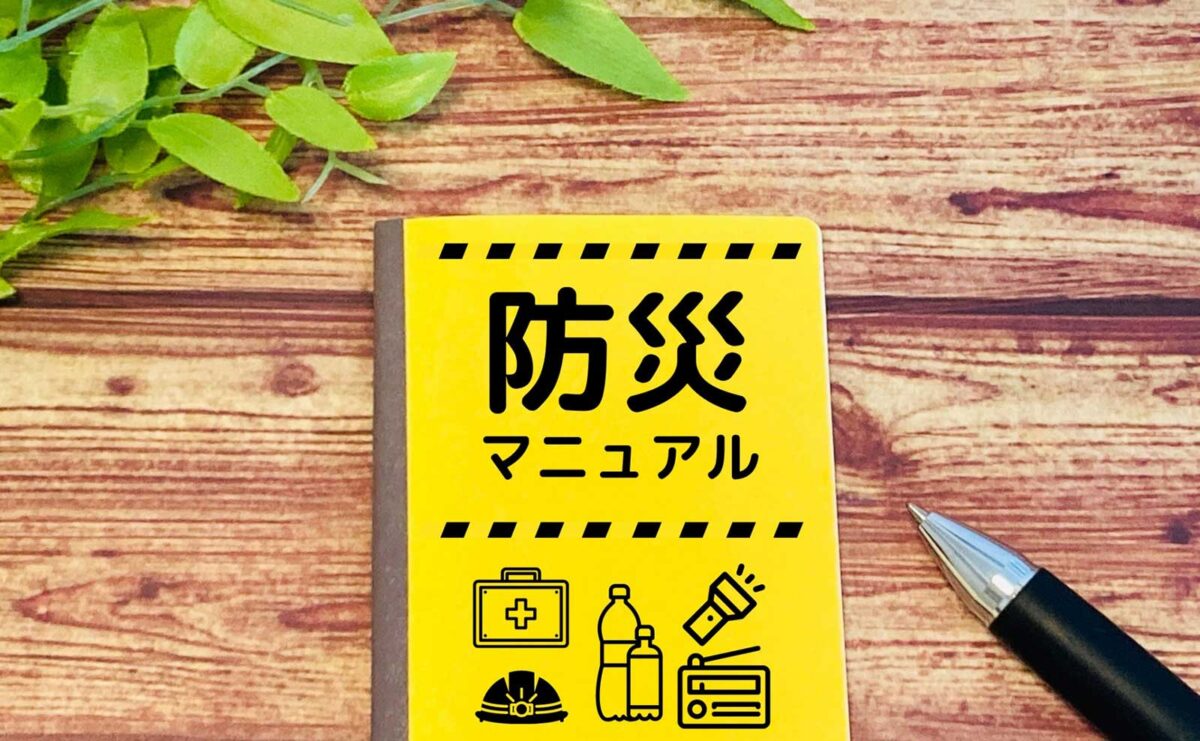
自治会や町内会で防災訓練や避難訓練を行うところも多いでしょう。コロナ禍で一時休止していたところも昨今の地震や水害などが多発していることもあり、また感染拡大時だからと言って災害は待ってはくれないことから積極的に訓練を行う自治体も出てきているようです。
防災訓練・避難訓練の内容
さて、そんな防災訓練、避難訓練ですがどのようなことを行いますか?よく行われている訓練内容をまとめてみましょう。
初期消火訓練
初期消火訓練は火災発生時に初期消火を迅速に行う方法を学ぶことが目的です。地震などの災害時には各所で火災が発生することも考えられます。消防車がすぐに消火に駆けつけてくれるような状況ではないと考えられます。日頃から自治会や町内会で消火器の使い方、消火栓の操作方法、バケツリレーなどの訓練をしておく必要があるでしょう。
消火器の使用方法についての訓練
- 消火器の構造や種類(粉末、二酸化炭素、泡など)基本的な使用方法について理解する。
- 消防署、消防団などの協力で実際に消火器を使って火を消すデモンストレーションを行う。
- 参加者が実際に消火器を操作し、使い方を体験する。水を詰めた水消火器での操作体験なども効果的。
- 自治会、町内会内の街頭消火器の設置場所の確認。
バケツリレーの訓練
- バケツリレーの基本的な方法や役割分担について理解する。
- バケツに水を入れて、実際にリレー形式で火を消すデモンストレーションや参加者による体験を行う。
消火栓の操作方法
- 自治会、町内会内の消火栓の位置や使用方法について理解する。
- 消防署や消防団の協力の元、消火栓を実際に開け、水を出してホースを使って火を消すデモンストレーションや操作体験をする。
初期消火訓練は消火器や消火栓の場所の確認が大切なのはもちろんですが、それ以上に実際にそれらを使ってみることが大切です。消防署や消防団の協力が得られると実際の火に向かって消火器を使ってみたりとより効果的な訓練が出来ます。
避難訓練
自治会の防災訓練で行われる避難訓練には、地震発生時や水害などの自然災害が発生したときに地域住民が安全に避難するための具体的な方法とその効果を検証できます。また訓練を重ねることで様々な問題点も浮き彫りになってきてより安全な避難が出来るようになるでしょう。
- 避難経路の確認 各家庭や地域全体の避難経路を確認します。避難経路図を作成し、住民に配布します。
- 避難場所の確認 地域の指定避難場所を確認し、全員がその場所を知っていることを確認します。
- 役割分担 各家庭やグループ内で役割を分担し、避難時に誰がどのように行動するかを決めます。
- 集合と説明 訓練の目的と流れについて説明します。避難経路や避難場所、役割分担について再確認します。
- シミュレーション開始 具体的な災害シナリオ(地震、火災など)を設定し、そのシナリオに基づいて訓練を開始します。
- 避難行動の実施 住民が実際に避難経路を通って指定避難場所に避難します。途中で障害物や危険箇所を設定し、現実的なシナリオを再現します。
- 避難場所での集合 指定避難場所に全員が集合し、点呼を行います。ここで避難の確認や反省点の共有を行います。
- 振り返りと評価 訓練終了後、避難行動の振り返りを行い、良かった点や改善点を共有します。次回の訓練に向けた課題を確認します。
自治会や町内会で行う避難訓練を通じて、災害時における安全意識が高まり、住民全体の防災意識が向上します。実際の避難経路を確認し、避難行動を体験することで、災害時に迅速かつ的確に行動できるようになります。また訓練を通じて、避難経路の問題点や改善点を発見し、必要な対策を講じることができます。そして住民同士や自治会、行政、消防などとの連携を強化し、災害時に円滑な情報共有と協力ができるようになります。
避難訓練は、地域全体の防災力を向上させるために非常に重要です。定期的に訓練を行い、常に最新の情報や方法を取り入れることで、より効果的な防災対策が可能となります。
救護訓練
自治会の防災訓練で行う救護に関する訓練には、災害時に迅速かつ適切に負傷者や具合の悪い人を救護するための具体的なスキルを学ぶ活動が含まれます。怪我をした人や具合の悪い人を迅速に救護する方法を学んだり応急手当の方法(止血、心肺蘇生法、応急処置)、AEDの使い方について学ぶことが多いです。
心肺蘇生法の訓練
心肺停止時の基本的な対応方法を学びます。消防署や消防団の協力でマネキンを使って心肺蘇生法の手順を学んで実際に参加者が体験します。
AEDの使い方
自動体外式除細動器(AED)の操作方法を学びます。町内のどこに設置されているかを確認したりAEDの実物を使って、操作手順を説明します。また参加者も実際にAEDを使った訓練を行います。
応急手当の基本
圧迫止血や包帯の巻き方を学んだり骨折時の応急処置方法を学びます(副木の使い方など)。その他やけどの応急処置方法(冷却や覆い方)を学びます。
搬送訓練
負傷者を安全に搬送する方法を学びます。担架の使い方や簡易担架の作り方を学び、実際に担架を使って搬送訓練を行います。
防災資機材の確認
自治会や町内会で保有している防災資機材の操作方法を理解し、整備状況を確認します。防災倉庫の点検、備蓄品の確認、発電機や無線機の使い方の練習を行います。
情報伝達訓練
災害時の情報を迅速かつ正確に伝達する方法を学びます。無線通信の訓練、非常時連絡網の確認、地域内での情報共有方法の確認を行います。
自治会や町内会の防災訓練の限界
自治会や町内会の防災訓練というと大体以上のような内容で行われることが多いと思います。どれも大切で実際自然災害などが発生したときに役立つ訓練ばかりです。自治会が行う防災訓練は地域の防災意識を高め、災害時の対応力を向上させるために重要ですが、いくつかの限界も存在します。
例えば、住民全員が訓練に参加することは難しく、一部の人だけが参加することが多いです。高齢者や体の不自由な人、仕事などで忙しい人は参加が難しいことがあり、訓練の参加率が低くなる傾向があります。また、訓練の内容が基本的なものに限られまた、マンネリ化してくる傾向にあります。そして実際の災害時に発生するさまざまな状況に対応するための実践的な訓練が不足している場合があります。
例えば、夜間や悪天候時の避難訓練は行われないことが多いです。さらに、自治会や町内会には限られた資材や機材しかなく、十分な設備や資機材を揃えることが難しいこともあります。専門的な知識や技術を持つ指導者が不足していることも課題です。そして、防災訓練は年に一度や数回しか行われないことが多く、訓練の間隔が長いために住民の意識が薄れがちです。
防災訓練の回数や内容を進化させる
これらの限界を補完するために、いくつかの対策が考えられます。まず、訓練の日程を複数回設定し、参加しやすい環境を整えることが重要です。例えば、平日夜間や週末など多様な時間帯で訓練を実施することで、幅広い住民の参加を促すことができます。また、高齢者や障害者、仕事で忙しい人々に配慮した参加方法を考えることも必要です。方法はどのように行うのかは検討の必要もありますが、オンライン訓練も一つの方法として考えてよいのかもしれません。ただ訓練の回数を増やすことは運営者側の負担ともなりますので難しいところです。
訓練内容を多様化することも効果的です。実際の災害シナリオを想定した実践的な訓練を行うことで、住民は現実的な状況に対応するスキルを身につけることができます。例えば、夜間避難訓練や雨天時の避難訓練を行うことで、様々な状況に対応する力を養うことができます。加えて、行政や企業、NPOと連携して専門的な知識や技術を持つ指導者を招き、訓練の質を高めることも重要です。防災設備や資機材の充実を図り、訓練で実際に使用する機会を増やすことで、住民は実践的なスキルを身につけることができます。
定期的な訓練と意識啓発も重要です。防災訓練を定期的に行い、住民の防災意識を常に高めておくことが必要です。訓練だけでなく、防災に関する情報提供や啓発活動を継続的に行うことで、日常的に防災意識を持つことができます。さらに、近隣の自治会や町内会と連携し、広域的な防災ネットワークを構築することも効果的です。防災訓練や情報交換を通じて、地域全体の防災力を強化することができます。
また、各家庭や個人が自分自身の防災対策を講じるように促すことも重要です。防災バッグの準備や家庭内の避難計画の策定など、個別の防災対策を進めることで、地域全体の安全性が向上します。特に高齢者や障害者など、災害時に支援が必要な人々に対しては、日常的な見守りや支援体制を強化することが求められます。
これらの対策を通じて、自治会や町内会の防災訓練の限界を補完し、災害時により安心できる環境を整えることができます。地域全体が一丸となって防災意識を高め、実践的な対策を講じることが重要です。



