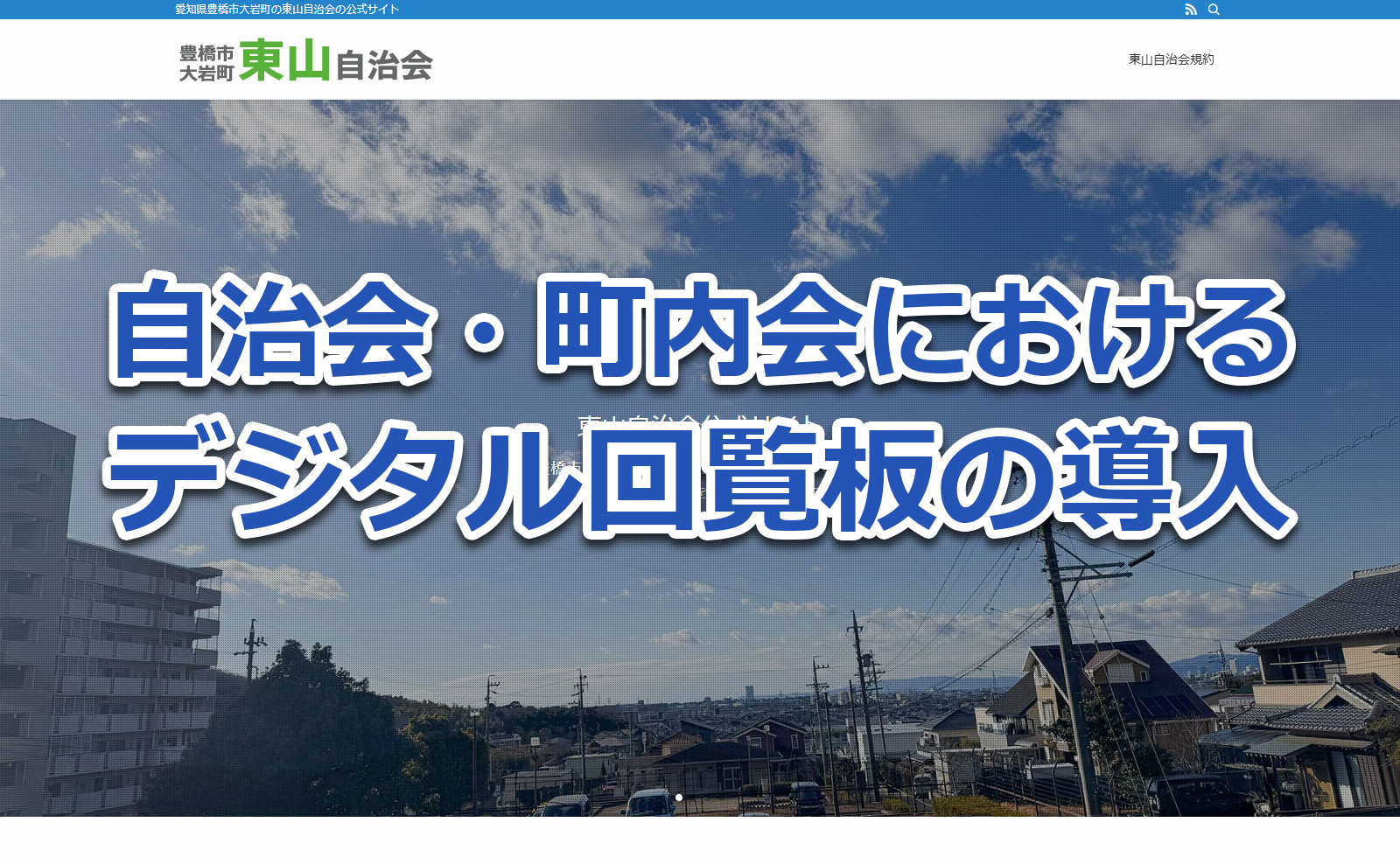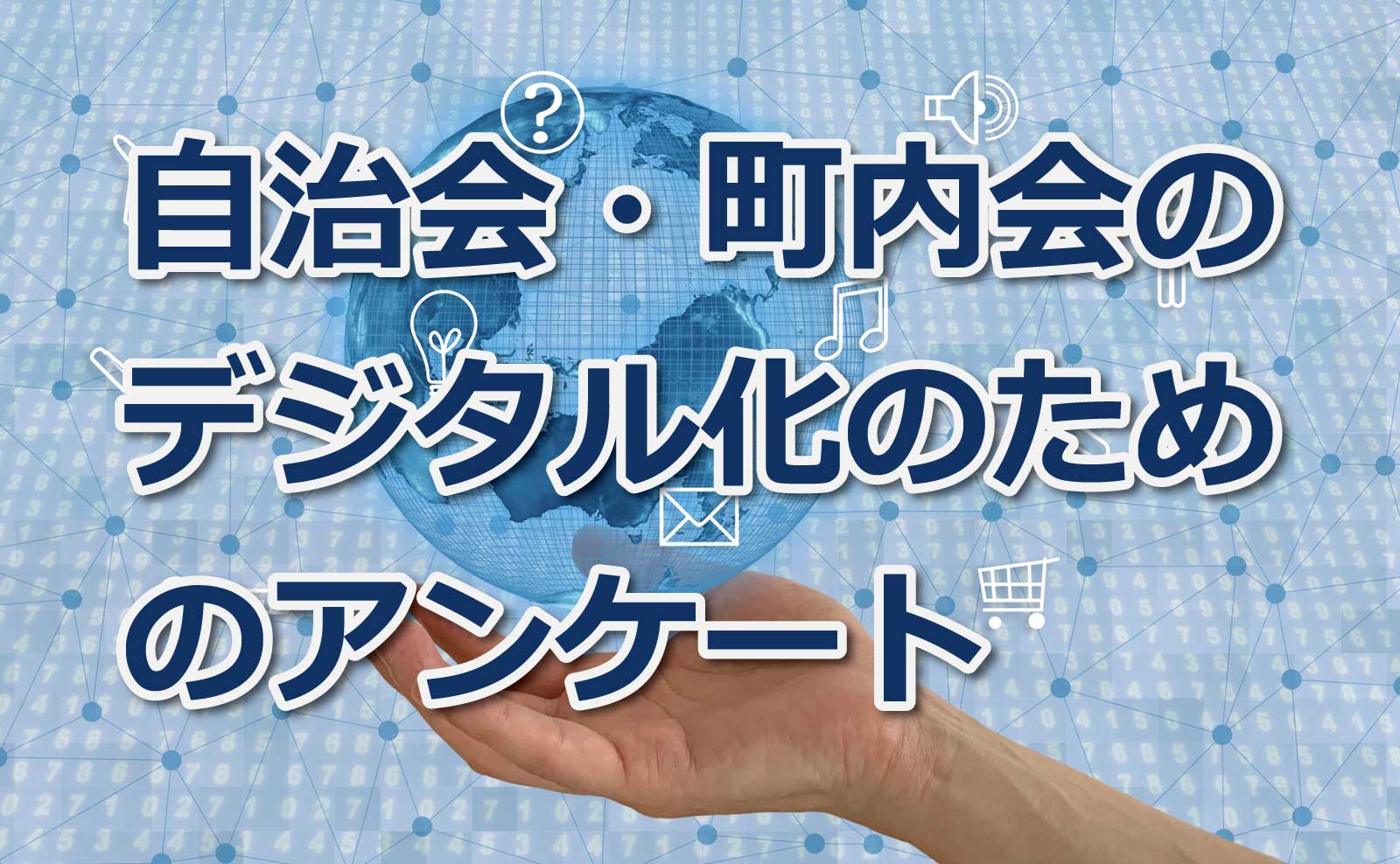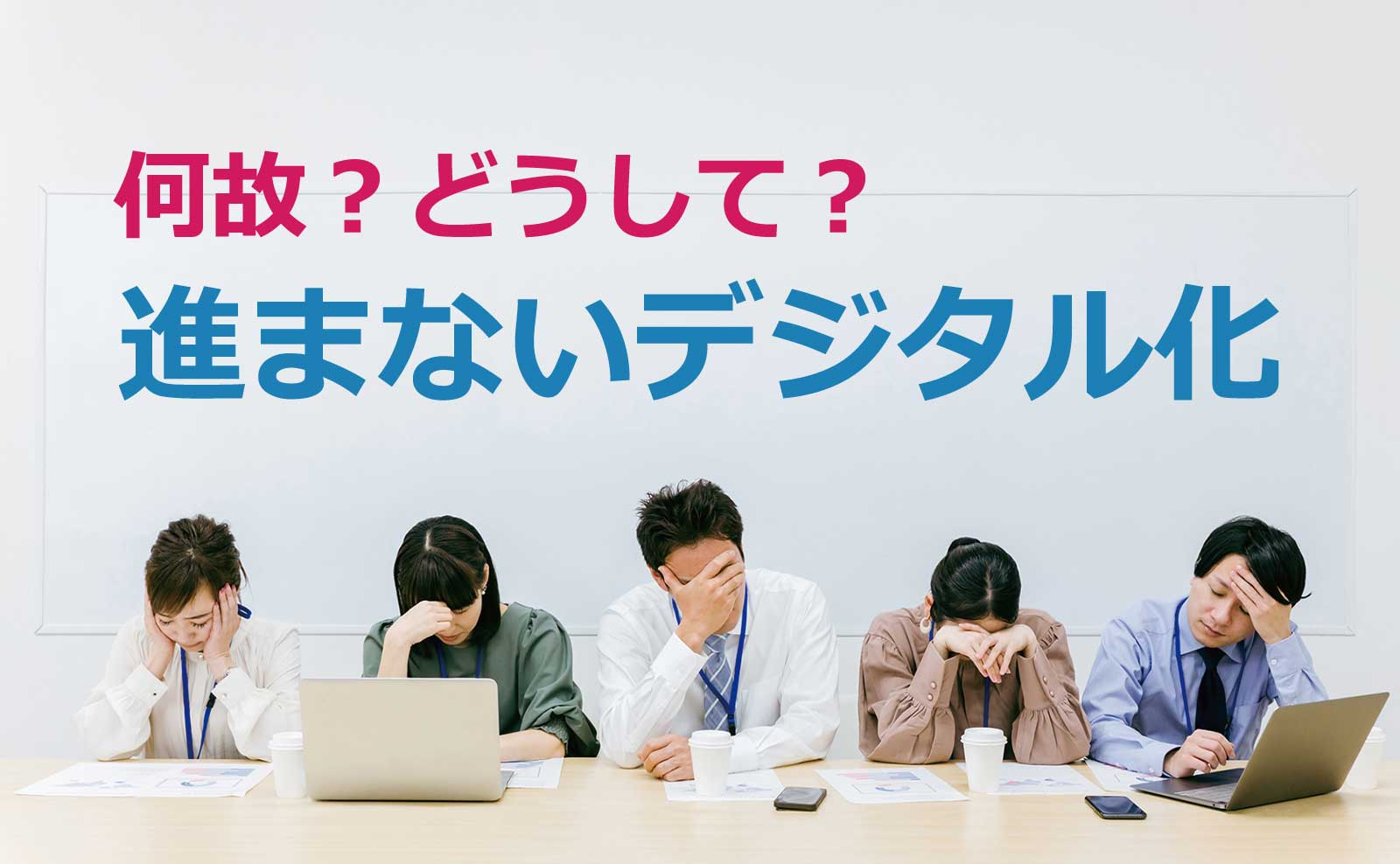2024年4月に報じられた朝日新聞デジタルの記事では、町内会運営の担い手不足や高齢化、加入率の低下という全国的課題に直面している長野県松本市の取り組みが紹介されました。市は町内会を所管する職員を増員し、役員会の開催方法の見直しやイベントの再構成、さらに紙回覧板のデジタル化推進など、町会の持続可能な形を市民とともに模索しています。特に注目されるのは、デジタル化の導入とあわせて、現役世代や外国人、女性など多様な市民が参加しやすくなる仕組みを行政自らが伴走型で支援しようとしている点です。
町内会は、防災、福祉、ごみステーションの管理、地域祭りといった住民の生活に密接した機能を担っていますが、その基盤が崩れつつあります。これまでの「地域の当たり前」が通用しなくなり、役員の負担が高齢者に偏る構造が限界に達しつつある中で、松本市のような自治体による現実的な運営改革支援とICTの活用は、他の地域にも大きな示唆を与えるものです。町内会におけるデジタル活用は単なるツール導入ではなく、地域の「つながりの再設計」としての意味合いを持ち始めています。
本コラムでは、松本市の事例を出発点に、「町内会×ICT活用」の意義と可能性、そして地域住民の誰もが関われる仕組みづくりを、自治体・住民・行政の三者の視点で考察していきます。読者の皆さんには、「デジタル化で町内会は何が変わるのか?」「ICTは住民のつながりを希薄にするのか、それとも新しくするのか?」という問いを頭の片隅に置きながら、これからの地域づくりを一緒に考えていただければと思います。
以下に朝日新聞の記事から引用します。すべての記事を読むのは有料です。
町内会の会合に市職員も参加へ 運営の効率化図り、なり手不足解消を
町内会役員のなり手不足や会員の高齢化、加入率の低下は全国的な課題で、長野県松本市も同様の悩みを抱えている。そこで市は今年度から、市役所内に担当職員を増員し、各町内会の運営方法などを改革する手助けをする。町内会運営の効率化を一緒に考えることで、働き盛りの現役世代や女性、外国人の参加を促し、意見を反映しやすくする狙いがある。
松本市では町内会などの自治組織は「町会」と呼ばれ、市内に485ある。市によると、1989年度の加入率は94.3%、平成の大合併で4村と合併した2005年度は85.6%だったのに対し、24年度は74.1%と年々低下している。
https://digital.asahi.com/articles/AST4T36SVT4TUOOB004M.html
全国共通の課題としての自治会・町内会の疲弊
加入率の低下、役員の高齢化、担い手不足
かつては住民のほぼ全員が自然と加入していた町内会も、今やその加入率は全国的に低下傾向にあります。総務省の調査によれば、都市部を中心に加入率が7割を切る地域も珍しくありません。その背景には、「町内会は任意加入である」という認識の広がりや、若年層が引っ越してきても地域に関わる機会が少ないという構造的問題があります。加えて、役員の担い手も固定化しており、定年後の高齢者が中心となることで、負担が集中する一方、新たな担い手が現れにくい状況が続いています。このような状態は「地域のつながり」そのものを危うくし、災害時や高齢者支援といった地域防災・福祉の機能の脆弱化にもつながりかねません。
都市部・準都市部で進む地域共同体の希薄化
マンションやアパートの増加、転入者の流動化が進む都市部では、住民同士が顔を合わせる機会が少なくなり、地域共同体の希薄化が進んでいます。かつてのように玄関先でのあいさつや井戸端会議を通じた情報交換の文化が失われつつあり、住民同士の関係性が「地縁」から「無縁」へと移行しています。その結果、町内会が地域の結束や安全を担保する機能を持っていた時代の仕組みでは、現代の都市生活にはなじまなくなっているのが実情です。新興住宅地やタワーマンションの住民にとっては、そもそも町内会の存在や活動目的を知らない場合もあり、地域活動への「関心」以前に「接点」が生まれないという深刻な課題を抱えています。
旧来型の役割分担とライフスタイルのミスマッチ
町内会の活動は、防災訓練、清掃活動、祭りの運営、回覧板の配布など多岐にわたりますが、その多くは平日の日中や休日に時間が割かれることが一般的です。こうしたスケジュールは、共働き世帯や子育て世代にとっては大きな負担となり、「手伝いたくても手伝えない」というジレンマを生みます。また、役職の引き受けも「前年の副会長が翌年は会長」といった順繰り制が多く、個人の都合や能力を考慮しづらい非柔軟な構造となっているのも現実です。こうした旧来の形式が現代の多様なライフスタイルと乖離することで、若年層が地域活動に参加しにくくなり、結果として世代交代が進まないという悪循環を引き起こしています。
 サイト管理人
サイト管理人町内会の形が時代に合わなくなってきている今こそ、「人が減ったからやれない」のではなく、「人が減っても続けられる」仕組みづくりが必要です。ICTの活用や行政の支援は、その第一歩です。
松本市の取り組みの特徴と意義
地域支援担当職員の増員とブロック制での配置
松本市は2024年度から、町内会の運営支援を強化するために「地域支援担当職員」を4人から7人に増員しました。加えて、市内を7つのブロックに分け、それぞれに1人ずつ担当者を配置する体制を整えています。これにより、町内会ごとの個別事情に応じた支援が可能になり、課題の把握や対応もきめ細かくなりました。自治体の多くは一括対応や書面での相談が中心で、現場への関与が限定的ですが、松本市は「担当者が地域に根を下ろす」姿勢を明確に示しています。これは、行政が単なる支援主体ではなく、住民とともに考え、動く存在へと変わりつつある証といえるでしょう。
市職員が会議や課題整理に参加する「現場密着型支援」
担当職員は、単に制度や予算を案内するのではなく、町内会の会合に実際に出席し、話し合いのファシリテーションや課題の言語化を行う役割を担っています。これにより、地域内に埋もれていた「声にならない不満」や「やりたくてもできない理由」などが可視化され、町内会内部での認識の共有や役割の再設計が進みやすくなります。これまで、町内会改革は各会の自主性に委ねられることが多く、孤立や疲弊を招いていました。しかし市職員が伴走することで、住民間の対話が促され、「自分たちで変えられる」という実感が芽生える土壌が育ちます。これは、単なる業務支援を超えた「地域関係の再構築」でもあります。
補助金制度(最大20万円)の新設で町内会改革を後押し
松本市は2024年度から、「町内会の課題解決や活性化を図る」ための補助金制度を新設し、1団体あたり最大20万円の支援を始めました。この制度は、単にイベント費用や消耗品の補填にとどまらず、デジタル化の推進や新しい取り組みの後押しとして機能しています。たとえば、紙の回覧板をLINEや掲示板アプリに切り替える費用、イベントの運営マニュアル化、若年層向けの説明会開催など、従来なら予算確保が難しかった取り組みに使えることが特徴です。金額自体は大きくはありませんが、「市が応援している」という姿勢が伝わることで、町内会側も前向きに動きやすくなる好循環を生み出しています。
「令和の地域像」を行政と住民が共に描く姿勢
臥雲義尚市長は「共働きや共育てを前提とした令和の地域のあり方を、皆さんと一緒に模索していきたい」と公言しています。この言葉には、行政が一方的に方針を示すのではなく、市民と並走しながら地域の未来像を描いていくという明確な意思が表れています。町内会を「古い仕組み」として終わらせるのではなく、生活の変化に合わせて柔軟に再構築していくこと。そのためには、多様な価値観や生活スタイルを持つ人々の参加が不可欠であり、そこにこそICTや制度支援の出番があります。松本市の取り組みは、「変える側」ではなく「共に変わる側」として行政があるべき姿を示す好例といえるでしょう。



町内会の課題は、仕組みだけでなく「関係性の再構築」にもあります。松本市のように、行政が地域に入ってともに考える姿勢は、全国の自治体にとって有効なヒントになるはずです。デジタルと人の力を両輪に進める地域づくりこそ、これからのスタンダードです。
デジタル活用の可能性と課題
紙の回覧板からデジタル連絡網へ:LINE、メール、掲示板アプリなど
町内会の連絡手段として長年使われてきた紙の回覧板は、物理的な移動や受け渡しの手間、留守世帯による滞留など、現代のライフスタイルとは合わない側面が顕在化しています。そこで注目されているのが、LINEのグループ機能、メール一斉送信、地域向け掲示板アプリ(例:ピアッザ、まちコミなど)といったデジタル連絡網の活用です。これらはリアルタイムで情報を届けることができ、特定の世帯に届かないといったトラブルを減らす利点があります。また、既読機能により、情報が伝わったかどうかが可視化されることも特徴です。松本市でもこのようなデジタル化の推進を想定し、補助金の活用先として具体的に想定されています。
デジタル化がもたらす「可視化」「時短」「世代間接続」
デジタル連絡網の導入によって得られる最大の効果は、コミュニケーションの「可視化」と「迅速化」です。誰が見たか、いつ配信されたかが記録として残り、伝達ミスや責任の所在が曖昧になることを防げます。また、会議の出欠確認、資料の事前共有、イベント申込の集約などもオンラインで可能となり、役員の作業量は大きく削減されます。さらに、スマートフォンを使い慣れた若年層や子育て世代にとっては、むしろ紙よりもデジタルの方が参加のハードルが低く、地域との関わりの入り口になります。高齢者世帯が中心になりがちな町内会において、若い世代との「接点」が生まれるきっかけにもなり、世代間の交流の可能性も高まるのです。
一方で残るデジタルデバイド(高齢者・ネット環境の不備など)
一方で、すべての世帯がスムーズにデジタル連絡網に移行できるわけではありません。特に高齢者やIT機器に不慣れな人にとっては、LINEやアプリの操作は高いハードルとなり、情報から取り残されるリスクもあります。また、通信機器を持っていてもWi-Fiやモバイル通信が安定していない、またはそもそも使いこなす人がいない世帯も存在します。このような“デジタルデバイド”を放置したままICT化を進めると、地域の分断を生みかねません。デジタルと紙の併用期間を設ける、操作説明会を開催する、ITに詳しい住民がサポート役を担うなど、導入時には丁寧な移行措置と配慮が必要です。ICTは「全員参加」でなければ、かえって格差を拡大させる恐れがあります。
ICT導入の成功には「導入支援」と「運用支援」の両輪が不可欠
ICT導入の失敗は、技術や機器の問題ではなく、「誰が運用し、どう続けるか」の仕組みづくりに失敗するケースが多く見られます。導入当初は意欲的だったが、管理が属人化して情報発信が止まる、管理者が引っ越した途端に機能しなくなる――こうした事例は少なくありません。町内会のように人の入れ替わりがある組織では、「引き継ぎやすさ」や「簡易な仕組み」が求められます。市や外部のICT支援団体が定期的にサポートを行う体制や、複数人での管理体制の構築が必要です。また、単発の導入補助だけでなく、数年単位での「伴走支援」や「相談窓口」の存在が、ICT活用を定着させるカギとなります。
- 紙の回覧板は時間・手間・情報滞留のリスクがある
- LINEや掲示板アプリによる即時・双方向の連絡が可能
- デジタル化は「作業負担の軽減」と「若年層の参加促進」に有効
- 既読確認などで情報の伝達状況が可視化される
- 高齢者やIT不慣れ層の“情報格差”対策が不可欠
- 導入後の放置を避ける「運用支援体制」が重要
- 複数人で管理できるシステム設計が持続性のカギ
- 行政による継続的な伴走・支援がICT活用成功の決め手
他自治体が学ぶべきポイント
ICT導入だけでは解決しない:制度設計と人の支援の重要性
町内会の課題にICTを導入すれば即解決、という考えは極めて短絡的です。ツールの整備がされていても、それを誰が管理し、どう使いこなすのかが曖昧なままでは、結局機能しなくなってしまいます。特に町内会のように自発性とボランティア性が強い組織では、導入後の「制度設計」と「人の支援」が重要です。松本市が行ったように、市職員がブロック担当として入り、会議への参加や課題整理を共に行うといった支援体制は、ICT導入を「地域に根づかせる」上で有効です。他の自治体も、補助金だけでなく“人の支援”を含めた導入計画を立てるべきでしょう。
「町内会の見える化」と「業務の簡素化」の好循環を作る
町内会の現状が外から見えないことは、担い手不足や不信感の要因にもなっています。ICTを通じて情報を発信・共有することで、「何をしている団体なのか」「どんな活動があるのか」が見えるようになれば、新たな参加者の動機づけにもなります。また、イベントの案内や資料配布、出欠確認などをデジタル化すれば、役員の事務作業が簡素化され、心理的・時間的な負担も軽減されます。業務の負担が軽くなれば、役員を引き受けてもよいと考える人が増え、参加者が増えればさらに活動が円滑になる――このような好循環をいかに作るかが、ICT活用の鍵なのです。
成功事例の共有が地域間格差を縮める鍵に
地域によって町内会の活動レベルやICT導入の進度には差があります。ある地域ではうまくいっている取り組みも、別の地域では「何から始めればいいか分からない」という声が上がることもしばしばです。こうした格差を埋めるには、成功事例の「見える化」と「共有」が欠かせません。松本市のように、各町会の工夫を市全体で収集・共有する体制をつくることは、地域間格差の縮小に直結します。他自治体も、「うまくいっている町内会のやり方を他に展開する」ためのプラットフォームや交流会、デジタル上の事例データベースなどを整備していくことが求められます。
担い手不足を「仕組み」で補う視点を持つべき
担い手不足はどの地域でも共通の悩みですが、それを「人がいないからできない」で終わらせていては解決にはつながりません。むしろ、人が減っても回せるような「仕組み化」や「省力化」が重要です。たとえば、役職の分担を細分化して一人あたりの負担を減らす、会議をオンラインにして移動負担を減らす、定型業務はデジタルツールで自動化する、といった工夫が挙げられます。また、担い手が少なくても活動を続けられるための「ローテーションの工夫」「サポート人材の育成」「外部支援の受け入れ」など、制度として持続性を確保する視点が必要です。



ICTは魔法の杖ではありません。しかし、制度や仕組みと結びついたとき、地域活動を確実に前進させる力になります。他自治体も、ICT「だけ」に頼るのではなく、制度設計・人的支援・事例共有という“地に足のついた改革”を模索することが求められます。
松本市の取り組みは、町内会という地域基盤を維持・再構築していく上で、自治体が“外側から支援する存在”ではなく“中に入って協働するパートナー”となることの重要性を教えてくれます。担当職員の増員とブロックごとの配置、課題解決への伴走型支援、そして補助金による後押し――これらはすべて、「自治組織を持続可能な形に進化させていく」という行政の明確な意思表示です。他自治体にとっても、町内会を単に「住民に任せるもの」と捉えるのではなく、制度の更新対象として共に関わっていく姿勢が求められる時代に入ったといえるでしょう。
そのうえで、ICTの活用はあくまで“手段”です。回覧板のデジタル化、情報共有ツールの導入、業務効率化といった目に見える成果の裏には、地域のつながりをどう再設計するかという“見えない構造”への配慮が不可欠です。情報が届きやすくなっただけでは、人は動きません。誰が・どこで・どのように参加できるか、心理的・物理的な壁を取り除く工夫こそが本質です。そして、ICTがその橋渡しの道具となるよう、導入と運用の両面から支える制度設計が求められます。
これからの町内会改革には、自治体、住民、そしてICTに詳しい第三者(技術支援者)の三者連携が不可欠です。行政の支援、住民の実践、技術面の裏付けがそろうことで初めて、持続可能な地域運営が可能になります。そしてその第一歩は、自分たちの地域でも「何ができるか」「何から始めるか」を考えることです。松本市の事例は、全国の自治体にとっての実践的ヒントであり、自分たちの地域の未来を見つめ直すよいきっかけとなるでしょう。
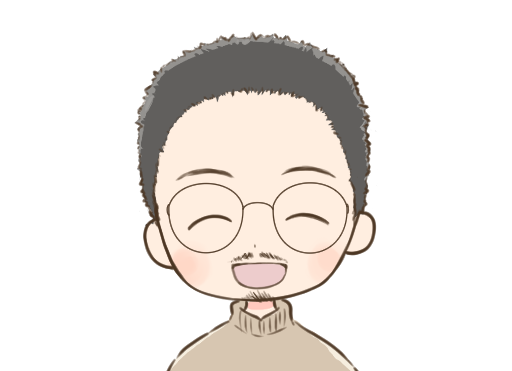
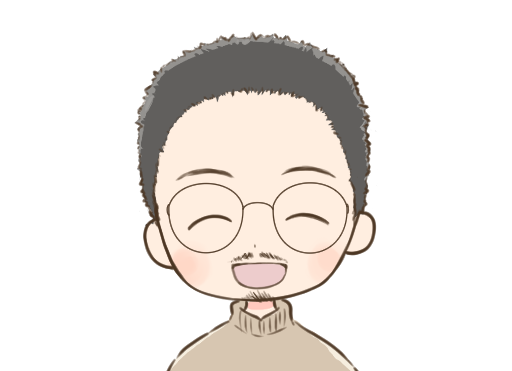
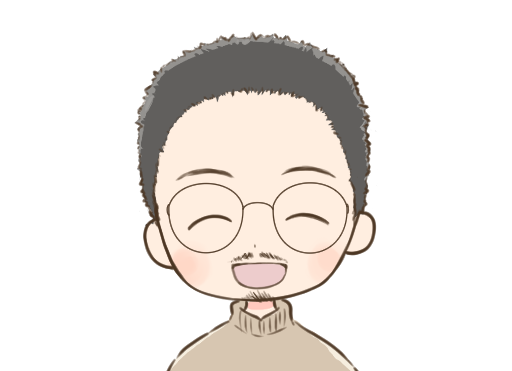
町内会の改革は「人手不足」ではなく「仕組み不足」の問題です。ICTと行政支援を上手く組み合わせることで、地域はもっと楽に、もっと楽しくつながれるようになります。今こそ、自分たちの地域に合ったやり方を見つけるときです。